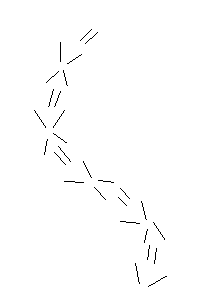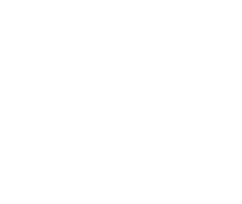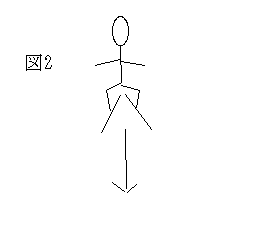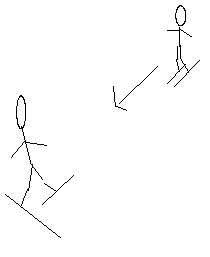�C�����Ȃ����X�L�[�w�Z�ցA���т����K�˂čs�����B
���̃X�L�[��͍��ݑٓ��X�L�[��Ƃ����A���쑺����ɂ���ĉ^�c����Ă���B���������āA�x�z�l��X�L�[�w�Z���ȂǁA��v�����o�[�͖���̐E���ƌ������ɂȂ�B�����āA���ɂƂ���2�����Ԃ�̃X�L�[���n�܂����B
�@�@�@�@�ǂ��v���Ă����́H
�Z���⑼�̃����o�[�Ȃǂ��Љ�ꂽ���A���v���ΊF�A���̎����ǂ��v���Ă����̂��낤�B���т���̎q���ŁA�R�����œ����Ă��āA��ォ��V�тɂ����E�E�E�Ƃ����Ƃ��납�B
�N��l�A���6�N�Ԃ��̌����������ʼn߂����A�X�L�[�̎w�����ɂȂ�Ƃ͎v���Ă����Ȃ��������낤�B�Ȃɂ���{�l�ł����A����Ȏ����v���Ă��Ȃ������̂�����B
�d���̍��Ԃɂ́A���т����X�L�[�w�Z�̘A�������܂��Ă��ꂽ�B
���܂��ƌ����Ă��A�X�L�[�������Ă��ꂽ��ł͂Ȃ��B
�@�Ȃɂ���A���̂Ƃ��̎��̓X�L�[��������Ƃ��A�����Ƃ������V�����m�ł͂Ȃ������̂��B
�@�@�@�@�Ԃ̉^�]�ɂ͒��ӂ��悤
�i�C�^�[���I���A�X�L�[�w�Z�Ŏ����݂��n�܂����B
���낢��Șb�ŁA����オ�����悤�Ɏv�����A���ɂ́A���l���̌��t�������ł����A�������̂��o���Ă���B
�ٓ��p�[�N�z�e��(�����h��)�ֈړ����邱��ɂ́A�~��o�����嗱�̐��
���\�ς���A����������鏬�т���̎Ԃ�����n�߂�ƁA�ׂ̎Ԑ�(�Ό��Ԑ��j���A���@���`�̎Ԃ��҃X�s�[�h�Œǂ��z���Ă������B
�u�����^�[�{���v�ƌ������t�Ɠ����ɁA�A�N�Z���̓��ݍ��܂ꂽ���т���̎Ԃ́E�E�E��̕ǂւƓ˂�����ł������B�R�l�ʼn������������Ƃ͂��Ȃ��B
�₪�āA��łт���G��ɂȂ�������F�������ɂ����E�E�E�ᓹ�ł̉^�]�ɂ͏\�����ӂ��܂��傤�B
�@�@�@�@���Ȃ��Ǝ��͈Ⴄ�@
���āA�X�L�[�͍��E�ɉ��Ȃ��犊��~��čs���̂����A�\�l�\�F�ƌ�����悤�ɁA���ꂼ��̐l�����o�I�ɕ߂炦�Ă���B
���������āA���t�ŕ\���ƃo���o���ɂȂ�B
2���ڂɂȂ�u�E�����o�V���Ɠ��ނv�Ə��т���Ɍ������K�����邪�A����ɃX�L�[�͉��Ȃ��B�E�����o�V���Ɠ��݃X�L�[�����A���͍������o�V���Ɠ��߂A�A�����ă^�[���o����ƌ����̂��B���ꂪ�A���ꂼ��̐l�������o�Ȃ̂��B
�@�ł́A�Ȃ����ɂ͂ł��Ȃ��̂��H
���т���̑��͎���3�{�����낤���Ƃ��������ŁA���߂���p���[���Ⴄ�悤�ȋC�������B�̌`���Ⴄ�B�ނ́A�P�U�T�����V�O�����A���͂P�V�T�����U�O����������A���o�I�ɈႤ�͓̂�����O�ł���B
����ł����x���J��Ԃ��ɂ��v�������邤���ɁA�Q�C�R��]�o����悤�ɂȂ����B�Ȃɂ��Ƃ��K����芵���A�q���̂��납��X�L�[�����Ă���l�������A�������Ȃ��^�[����A��������悤�ɁA�Ƃɂ������Ԃ���艽�x�����鎖������B
�����āA���낢��Ȑl�̊��o���A���̒����玩���̊��o�ɋ߂����̂������o�����B�o�V���������l�́A�S�̒��Ńo�V���A�o�V���ƌ����Ȃ��犊��B�����āA��������������̊��o���������B
�@�@
�@�@�@����ŁE�E�E�킩��́H
�����ł����s����ȏ�ԂŊ���Ȃ���ł͊m���ɓ���̂����A���̌�A�w�����Ƃ��Ďw������悤�ɂȂ芴�����B
�l�Ԃ̑̂́A���Ŗ��߂��o�������ƌ��������悭�킩���Ăق����B�r�̋Ȃ��L�����g���܂��傤�ƌ���ꂽ�Ƃ��悤�B�����̒��Ȃ�A���ɐK���������炢����A�w�L�т���܂œ������낤�B�������A�����Ă���Œ��͂ǂ����낤�A�قƂ�Ǔ����Ȃ��̂��B
�X�L�[���t�����́A���̓������������܂��Ƃ��Č��Ă��邩��킩�邪�A��B��ڎw���Ȃ�A�����̒��œ����Ă���Ƃ������o�ȏ�ɓ������Ă݂悤�B
�@���Ȃ��Ə�肢�l�ł͑̂̎g�������Ⴄ�̂��B
�V���Ȋ��o��g�ɂ��悤�Ƃ���̂ɁA���܂łƓ��������������Ă����̂ł́A���̊��o���ǂ̂悤�Ȃ��̂��H�E�E�E�킩��͂����Ȃ��B
���v�I�̂͏���Ɏ��Ȗh�q���Ă����B����ȏ㓮���Γ]�ԂƎv���Ƃ���ŁA��߂Ă����B
�@�@
�@�@�@��l�͐����I
��肭�Ȃ肽���ƌ������́A�o���Ȃ������o����悤�ɂ��鎖���B
�X�L�[�ł́A�o���Ȃ���������Γ]��œ�����O�ł͂Ȃ����B�������āA�]�Ԏ��������߂���킯�ł͂Ȃ����A���߂ăX�L�[�������Ƃ��A�����Ă�������A�]��ł��鎞�Ԃ̕������������l���������낤�B
���܂ŏo���Ȃ��������ɒ��킷��̂����瓖�R�̌��ʂł���B
�X�L�[���t�́A���Ȃ��������ł����������悤�A�ǂ�������������l���Ă���B�킩��Ȃ��Ƃ��̓X�L�[�w�Z�ɓ��낤�B
��ɁA���̗F�l���X�L�[�ɘA��Ă����̂����A���߂Ċ��邱�̓�l�͐����������B��l�͖����ɂȂ�ς��ɑς��āA�Ƃ��Ƃ��A�邱��ɂ́A�Ȃ��Ȃ��ǂ����Ċ����悤�ɂȂ��Ă��܂��A�A��ࢃX�L�[�͊y�����A�܂��s�������B�v�ƌ����Ă����B
������l�́A�u���͂��̔N�ɂȂ��āA����ȂɃ~�W���Ȏv���͏��߂Ă�A��x�ƃX�L�[�͂���B�v�Ƃ����A��{����ƍŌ�܂ŎԂŐQ�Ă����B
�ނ̕@����A�Q�O�����͂��낤���Ƃ����@��������Ă����̂��A���܂ł��o���Ă���B
�@���߂ăX�L�[������l�̂��ׂĂ��A�O�҂ł���E�E�Ɗ肤�������͍s���܂��B
�������A�X�L�[���t�����́A�ԈႢ�Ȃ������v���Ă���B�����āA���߂Ă̐l�ɁA�o�������m�b���o���B
�@��l�ł������̐l���A�X�L�[�������Ă����悤�ɂȂ邽�߂ɁB
�@�@�@�@�j���m�̑厖�Șb
���āA�b��߂����B
����ڂ̖�A��X�͍Z���ƂƂ��ɊX�֏o���B
�����i�݁A���̂Ƃ��̉�b�͂������B���܂ł��A�Z���Ǝ������ނƁA
�@�m�@�u�Z���������ƌ�������ł���v
�@�Z���u�X�L�[�ł��Ȃ���ɁA����Ȃ��ƌ����킯�Ȃ����낤�v
�@�m�@�u�������A�m���Ɍ����܂����v
�@�Z���u����Ȃ��v
���̌J��Ԃ��ł���B
���܂ł��A���̋L���̂ق����������Ǝv���Ă͂��邪�E�E�B
�@�Z���u�N�́A�~��ɂȂ낤�v
�@�m�@�u���܂́A���z���������Ă��܂��v
�@�Z���u�X�L�[�A��肭�Ȃ肽�����낤�v
�@�m�@�u���܂̂܂܂ł��A�����Ǝv���܂��v
�@�Z���u�ł��A�N�͉��肾��v
�@�m�@�u����ł���������Ȃ��ł����v
�Z���u���肾��A��肭�Ȃ肽�����낤�v
�����܂Ō�����ƁA���������炩������Ȃ����A��肭�Ȃ肽���Ǝv������s�v�c�ł���B
�@�m�@�u��邩��ɂ́A��肭�Ȃ肽���ł��v
�@�Z���u��肭�Ȃ肽��������A�����֗��Ȃ����v
�@�m�@�u�͂��v�@�@�@
����Ȋ����������Ǝv���B
�Z���������������Ō����Ă����̂�������Ȃ����H
�@�����ė����A���ւƋA�����B
�@
�@�@�@�@�����Ă��́H
1984�N11���A21��7�����B
�ĎR�V�[�Y�����I���A���֖߂菬�т���Ɠ~�̘b�����Ă����B
�����ŁA�����@�_���Љ�Ă������B��Ɋזv���܂ƌ����������̂��j�ł���B(����30�j
��͂�R���ԂŁA�������т���Ɂu�ٓ��ɂ́A�����������́H�v�ƕ����ƁA���̉��Łu���˂��ȁA����������d�����߂Ă��₪���āB�v�ƂȂ����B�ނ͏d�@�̖Ƌ������A�u���h�[�U�[�Ȃǂ̃v���h���C�o�[�ŁA�����(�R�[�X�����p�̎ԁj�ɏ��Ȃ����q�˂鎖�ɂȂ����B
������A�������𑗂�̗p�����܂�B�@
���ɂ���A���ł�3���̒i�K�Ō��܂��Ă�����̂Ǝv���Ă������A��ŕ������Z���Ə��т���̉�b�́A
�@���сu�m���s���ƌ����Ă܂����B�v
�@�Z���u����ƌ����Ă��A�X�L�[�o���Ȃ����낤�B�v
�@���сu�Z�����A�����ƌ�������Ȃ���ł����H�v
�@�Z���u�X�L�[�o���Ȃ��̂ɁA����Ȏ������킯�Ȃ�����Ȃ����B�v
��͂�A���̎��̍Z���͐����Ă����ɈႢ�Ȃ��B
�����đ�����ł́A�ό��ے��ƍZ���̊ԂŁA
�@�ے��u�m�N�́A�������o����悤������A�H���Ŏg����������Ȃ����B�v
�@�Z���u�������A�p�g���[���Ŏg���܂��B�v
�@�ے��u�X�L�[�̏o���Ȃ��l�Ԃ��g���āA������������A���܂����B�v
�Ƃ�������肪�������炵���B
�@�@�@�@���i
���āA�����m�̕��������Ǝv�����A�X�L�[�ɂ̓o�b�W�e�X�g�A�w�����A�p�g���[���Ȃǂ̎��i������A�d���ɂ��K�v�Ȏ��i���قȂ��Ă���B
����͗L���i�҂̕s���Ȃǂ���A1���A�Q���������̂����K���ƌ����`�ŏ]�����Ă���ꍇ������������B
�@�p�g���[���͓��R�̎������A�l���ɂ������d���ł���A��ςȎ��������B
�ٓ��X�L�[��ł͓����A�Z�������ӔC�҂ƌ����`�ŁA���F�p�g���[���̎��i�������A���ё����̂��ƃp�g���[�������Ґ�����Ă����B
���B�A���K���͓��X�p�g���[���ɕK�v�ȃX�L�[�Z�p�̑��A�~�}�@�Ȃǂ�@�����܂�čs���B
���ё����͂��̑O�̔N����ĂP���ɍ��i���Ă���A���̎��M�ɖ�����ꂽ����͂Ȃ��Ȃ��̂��̂������B
�����ł�����l�A���̑�̊w���ō����ƌ����j���Љ�悤�B
�N�͎��Ɠ����A�������P���A�A���o�C�g�Ńp�g���[�������鎖�ɂȂ��Ă����B
�P�Q���Q5�����߂��A��������Q�����f�̌���肪�n�܂�B
�ނƃ��t�g�ɏ��(���̔N�y�A���t�g���V�݂��ꂽ�j�b���Ă����B
�@�����u�m����́A�P���ł����H�v
�@�m�@�u����A���������ĂȂ��B�v
�@�����u�����Ȃ��̂ɁA�悭�ق��Ă��炦�܂����ˁB�v
�������āA�Ƃɂ���������肭�Ȃ鎖�����ӂ����B
�@�@�@�@�n���̈��K�L
�d���̍��Ԃɗ��K������X�������B
�����܂����Z���������Z�C�{�E�́A���w���̂Ƃ��P�����Ƃ����n���̈��K�L�œ��j���ɂ̓p�g���[���̎�`���ɗ��Ă����B
�u�m����A�R�u�������E�F�[�f�������o�����B�v�ƌ����̂����A���́u�R�u�Ȃɓ���A����ǂ��낶��˂���B�v�Ɠ��S�v�����B
�@�������A����̐l�B���ׂĂ����̎t�ł���B�Q�����f���̓R�u������Γ����čs���̂����A����ƁA3�A4��A������x�̎��Ɋ����킯���Ȃ������B
�@�m�@�u�Z�C�{�E�A���������ɂ́A�ǂ����ǂ������������́H��@
�@�Z�C�{�E�@�u���[��A����Ă�ł��邳�B�v
�@�m�@�u�E�E�E�E�v
���̂����肪�A�q���̂��납��X�L�[�����Ă���l�Ƃ̑傫�ȈႢ��������Ȃ��B
�ނ�́A�C�������Ƃ��ɂ͏o���Ă����̂ł���B
�����A�R�u�Ζʂɓ��������Ă��邾���ŁE�E�E�E�B
�@���̂���̎��̋Z�p���x�������A������x�X�L�[�����낦�Đ���]�ł���悤�ɂȂ��Ă����Ǝv���B�����֗��Ė�P�����A�p�g���[���Ƃ����d����A�������A�傫���J�����v���[�N�Ńu���[�L�������Ȃ��犊�邱�Ƃ́A��肭�s���悤�ɂȂ��Ă����B
�@�@�@�@
�@�@�@
�@�@�@�����܂Ő^������ȁ@�@�@�@
�t�Ɍb�܂�A���Ɍb�܂ꏇ���ɏ�B���Ă����킯�����A��Ɏ��͑傫���J���Ă��Ȃ�������Ȃ��A�ڂɏĂ��t���Ȃ�������Ȃ��B��肢�l���b���Ă���Ƃ��A�����ɂƂ��đ傫�ȃq���g�ɂȂ邱�Ƃ����邩�炾�B
��l��l�A���o���Ⴄ�̂ł���B
�N�̊��o�������ɋ߂��̂����f���Ȃ�������Ȃ��B�^�[�������t�ŕ\���������A�u�L���[���v�Ƃ��u�L�[���v�Ƃ��u�K�[�v�Ƃ����낢�낾�Ǝv���B
�Ȃ��A���̐l�́u�L���[���v�Ȃ̂Ɏ����́u�K�[�v�Ȃ̂��A���~�߂̂Ȃ������������A�����Ƃ͊��o���Ⴄ�����肢�̂ł͂Ȃ����E�E�E�B
�����āA���̐l�̊����ڂɏĂ��t����̂��B
���ۂɂ͑S�R�Ⴄ�Ƃ��Ă��A���̐l�ɂȂ肫��̂ł���B���ɂƂ��ẮA�Z���������B�Ƃɂ����A���ׂĂ�^�������B
�Ђ���Ƃ���ƁA���퐶���܂Ő^������������Ȃ��B
���w�����A�w�����Ɛi�ނ����A���x�����x���L�w���悤�Ɍ���ꂽ�B
�������A���������ɒ���Ȃ������B�c�Ȃ��Ȃ�A�Z�����L�w�������̂ł���B
�@�@�@�@�搶������
�@���āA�F����̒��ɂ��A�X�L�[�w�Z�𗘗p�����o�����������̕�������Ǝv���B
�X�L�[���t�B�͖��������A�O���������A�u����ȂƂ��́A�ǂ�������B�v�u����ȕ��ɁA��������ǂ����v�ȂǂƁA�Ƃɂ�����荇���B
�@��������A�u�����́A���k�͉����q�������B�v�Ȃǂƌ����b���o��B�@
�Ƃɂ����A�M���̂ł���B
�@�����āA�l����肭�������A��������肭�Ȃ肽���Ƃ����v�����Ԃ������B
���b�X���̎��́A���̎v���k����ɂԂ���B
�@������A�F����������ɂ�����������Ȃ����A�킩��Ȃ����́u�킩��܂���B�v�Ǝv�����Ԃ��Ăق����B
�F���킩��Ȃ��̂Ȃ�A����͋������������̂ł���B
�u�X�L�[���J���āA�����d���ģ�Ȃǂƌ����Ă��A���ꂼ�ꊴ�o���Ⴄ�B
�u���ł́A�킩���Ă���̂ł����A�̂����������Ȃ��B�v�ȂǂƂ悭�����邪�A����ȃo�J�Șb������Ȃ��B
���k��l��l�̊��o�ɍ����������o���Ă��Ȃ������Ȃ̂��B
�������A�Ȃɂ�����Ȃ���A���t�͊F���킩�������̂Ƃ��āA���b�X����i�߂Ă��܂��̂ł͂Ȃ����낤���H
�@�@�@�@���ł����ɂ���́H
�X�L�[�w�Z�́A��Ɣ��̍u�t�ɂ��^�c����Ă���B
��u�t�͖����X�L�[�w�Z�ɂ��邪�A���u�t�͎����̎d�����x�݂̓��ɁA�X�L�[���t�Ƃ��ĊF����ɃX�L�[�������Ă���B
��͂���j���Ȃǂ̓X�L�[���[�̐��������A�X�L�[���t�̐l�����K�v�ɂȂ��Ă���B
�@�ł͔��u�t�B�́A���j�������X�L�[�����Ȃ��̂��ƌ����ƁA�����ł͂Ȃ��B�킴�킴�i�C�^�[�ɗ��K���邽�߂ɂ���Ă���B
�@���̂����ٓ��X�L�[��ł́A���b�X���I�����4�����납��ƁA�i�C�^�[��7�����납��A�w�����A���w�����A�p�g���[�����Q�����Č��C���s���Ă����B
���낻��Q���ɂȂ낤���ƌ�������A���́A����ɎQ�����邱�Ƃ𖽂���ꂽ�B
�����A���ς��i��ς����낢��ȗ��K������̂����A���̓��̓V���e���^�[���̎R�J���A�J�J���Ȃǂ�����Ă����B
�Z��������A���Ō��Ă��钆���X�Ɋ����Ă����E�E�����Ȃ��̂��B
���͓��S�u���̐l�B�́A�����Ă��炤�K�v������̂��ȁH�v�Ǝv���Ă����B
�����āA�Ȃɂ���������̌�A���̔ԂɂȂ�B
�@�Z���@�u�m�A�����Ă鎖�A���邩�H�v
�@�m�@�@�u�����ς�A����܂���B�v
�@�Z���@�u�܂�������A�O�̐l�̂��̌��Ă��ȁB�^�����Ă���Ă݂�B�v
�@�m�@�@�u�͂��v
���̎��A�Z���͍Ō�܂ŏ�ɂ����B
����o�������͖���킩�炸�J����������肵�Ȃ���A���ŕ���ł���搶���߂����ē˂�����ł������B�ǂ����A���̌��ʂ͑S���������ʂ��������悤�ŁA�������Ɠ����ăQ�����f�e�̐V��ɂ͂܂蓮���Ȃ��������āE�E�E���Ă����B
�l���Ă݂�Z���͂Ȃ��A���̎�������ɂ����̂��낤�H�@
�d�����I���Ɠ���X�L�[�p��̂킩��Ȃ����ɁA���ё���������̖{�������o�����B���{�X�L�[�����ł���B
�ɂ�����Ƃ����ǂ݁A���̂����p����o���Ă������B
�@�@�@�@���芅�сE�E�J�b�R�C�C�I�@�@�@�@
�@���̍��ɂȂ�Ƃ��q����̑O�œ]�Ԏ��͂قƂ�ǂȂ������̂����E�E�E�B
�ٓ��X�L�[��̃��t�g�́A�Q�����f�̒[�ɒ����Ă�����̂͂Ȃ��A���q�����t�g���畨�𗎂Ƃ����ꍇ�A�E���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B
���j���A���Ȃ̃��t�g����^���Ԃȃ��b�P�𒅂��p�g���[�����A�V�����Ċ���~��čs���B���t�g����͔���Ɗ�����������A�Ƃɂ����J�b�R�C�C�A����Ă݂����B
�������A���͉����璷�C�𗚂��ď���čs���B
�Ȃ��Ȃ�p�g���[���́A���q����̑O�œ]��ł͂����Ȃ�����B
�@�@�@�@����Ă���̂ɑ��
���̓��̃i�C�^�[������K���n�܂�B
7���ɂ͌��C���n�܂�̂ŁA���Ԃ͂���قǂȂ��B
5��30���ŏI�p�g���[�����I����Ƌ}���ŗ[�H�����A2�{�̃q���������ă��t�g�ɏ��B���̎��Ԃ́A�d�����I���i�C�^�[�ɂ���l���A�܂��Ԃɏ���Ă��鎞�ԂȂ̂ŁA��r�I�l�͏��Ȃ��B
��3�Q�����f��r���܂Ŋ���ƁA���o�����q���Ńr���f�B���O�ƌC�����т���B
�Ȃ����ƌ����ƐV��œ]�уX�L�[���O�ꂽ���A������Ȃ�����ł���B
�Q�����f�̒[�ɃX�L�[���[������Ȃ��悤�l�b�g�������Ă���B
���͂̊m�F(�N�ɂ������Ă��Ȃ���)���\���ɂ��Ă���A�l�b�g��������B
����A�]�ԁE�E�E����A�]�ԁE�E�E�B������7���O�ɂ̓X�L�[�w�Z�֖߂�B
�@�̒��̐���悭�������Ƃ��A�����Ȃ������悤�Ȋ�œ����čs���ƁA�F���琺��������B
�@�u�m�A��ł��~���Ă���̂��H�v
�@�u�������A�����V�C�ł��B�v
�@�u�ȂA����E�E�E�v�@�@���b�P�̃t�[�h�Ɏ������W�܂�B
����H�E�E�E�Ⴊ�����ς��l�܂��Ă����̂��B
�������Ď��̔閧���K�́A�����Ȃ������ɑS���̒m��Ƃ���ƂȂ��Ă��܂����B
���āA�V��͏K����芵���A�Ƃɂ������鎖���B
�X�L�[��ł͊댯�h�~�̂��ߗ�������֎~�̏ꍇ���������A�X�L�[�ɍs���ĉ^�ǂ��E�E�E�H���ɍ�������A�h�ɂ����Ԃ��Ă��Ȃ��ŁA�Ƃɂ������낤�B�@
�p���������ǂ��́A�V���e�����ǂ��̂ƍl���Ă͂����Ȃ��B
������͂ǂ��ł������̂��B
�@��܂��C�����b�P�̃t�[�h���A�ڂ��@�̌������̌����A���ׂĐ�ň�t�ɂ��悤�B�E�E�E�������A�T�O�������炢�̃q��2�{�͂킷�ꂸ�ɁI
���̐V����K���P�O���قǑ�����ƁA�]�Ȃ��Ȃ����B�����A�����I�Ƃɂ������鎖���y�����Ďd���Ȃ��B
�@�@�@�@�����~�I
�����Ė����ł͂Ȃ����A�V�C�̂悢���ɑ����Ă��鎖���������B
����Ԃ̒����Q�����f(��P�O�O�Om�A���ώΓx�P�W�x�j���A�����~���邱�Ƃ��B����ԂŁA���ꂢ�ɐ�������čd�����܂��Ă��鎖������B
�����̂悤�ɑ�����Ƌ��|�����Ȃ��Ȃ�A���ꂽ�����y���݂ɂȂ��Ă���B�����Q�����f�͏㕔���}�ŁA���ԂɊɎΖʁA�������Ăы}�ɂȂ�̂ŁA���炭�ς���ƁA�X�s�[�h�������\���y���߂�悤�ɂȂ����B
���钩�A�Z���ƈɓ��@�t�F�A�����ɌĂю~�߂�ꂽ�B
�u�m�A�����s�����낤�A����A�����Ă����B�v
�Ȃ���E�E�E�ƌ��������������B
2��23�����A�t�F�������Ă������~�p�̃X�L�[���B
�ނ͎��Ɠ����N�ŁA�q���̍����狣�Z�X�L�[�����Ă��āA�����͑�w�̃X�L�[���A�������P���ł���B��ɁA���w��������łQ�O�O���ȏオ���钆�A�V�����łT�Ԃƌ������тō��i����̂��B
�������A�T�����[�}���̂������A�x�݂̓���������Ȃ��Ƃ����ŁE�E�E�B
�@�@�@�@����
�����X�L�[�̂ق����X�s�[�h���オ��̂����A�V�C���������A�����C���B
���͕@�̌�����Ń��t�g�ɏ���Ă����B�����āA����n�߂�B�������A�X�s�[�h���łĂ����悤�����A�\���ς�����B
�����A���̎Ζʂɓ��鎞�A���̗\�z�͑傫������ꂽ�B
�����́A���̂܂܊����Ă���̂����E�E�E��̂ł���B
�@���~�̋��Z�Ȃǂ��A�e���r�ł����ɂȂ������̂�����Ȃ炨�����肾�Ǝv�����A�ɎΖʂ���}�Ζʂɓ��鎞�A�X�s�[�h������Ɛl�Ԃ́E�E�E��Ԃ̂������B
�O�V���O�V���O�V���[�Ɠ]�сA�Е��̃X�L�[���O��A�X�g�b�N���O��A�̂Ŋ���~�肽�����������̂́E�E�E�B
������Ă��钇�ԒB�������B��͂�A�F�����Ȃ鎖�͒m���Ă����炵���B
�@�@�@�@�|���Ȃ���Ύv���ʂ�
�V�Ⴊ���Ƃ��Ȃ�Ǝ���2��23�����B�X�L�[�Ƃ����͖̂{���ɂ悭�����玟�ւƁA�����o���Ă����B
�������A���̖��̓����͂Q�A�R���Ō��������B���̎Ζʂɓ���O�ɁA�S�̏��������邾���ł悩�����B
�@�����A�X�L�[�ł͗\�����鎖����Ȃ̂��B���̓R�u�����瑁���X�L�[�����Ƃ��A���̐�͐Ⴊ�d����������A��������G�b�W���g�����Ƃ��E�E�B�����āA���ۂɊ��������̂Ɣ�C�����Ă����悢�B
���āA�����~���������Ă���A���̃X�L�[�͑傫���ω����n�߂��悤�Ɏv���B���Ȃ���~��čs���ꍇ�A�����~�����X�s�[�h���o�Ȃ��B���������āA���|�����Ȃ��B
�X�L�[�̓X�s�[�h�Ƃ̐킢�ł���A�|���Ǝv��Ȃ��Ȃ�A�����͎v���ǂ���s���悤�ɂȂ邩��s�v�c���B
��ʃX�L�[���[�́A�Ȃ��Ȃ��N�����Ȃ��Q�����f������@����Ȃ��Ƃ͎v�����A���ꂽ���ɂ́A�Ƃɂ����N����������ԂɃ��t�g�ɏ�낤�B
������Ƃ��l���Ă͂����Ȃ��B�����A���܂Ő^�������Ɋ���~��悤�I�I
����ɂ͏\�����ӂ��āA�������Ȃ��ƁA����������肭�Ȃ��ƌ����̂ɁA�V�[�Y����_�ɐU���Ă��܂���������Ȃ�����B
�]�Ƃ��́A��̎��Ȃ��ċ����������B�@
���v�I�����ȒP�ɍ��܂Ȃǂ��Ȃ�����B�����A���������ɂ��͉̂䖝���悤�B
�@�@�@�@�E�F�[�f����
�@�Q���ɂ͂���ƁA��������u�m�A�p�������͌����_�Œ����Ƃ���͂Ȃ��B�v�ƌ���ꊴ���������̂��B�����Ȃ�ƁA�E�F�[�f����(�����)�ł���B
�}�Ζʂ��A�`���b�A�`���A�`���b�Ɗ����B
�@�@�@�@���[��A�J�b�R�C�C�I
�@�i�C�^�[�ő������狳���Ă��炤�B
�@�����u�R�X�L�[�̃A�E�g�G�b�W����A�C���G�b�W�փo�V���ƒ@������B�v
�o�V���A�o�V���@����A�S�̒��řꂫ�Ȃ���@�������Ƃ��A�O�V���[�I�s���[���E�E�E�C�����]�����B�X�L�[�����ł������B
���������艽�Ƃ��X�L�[�����A�����̂Ƃ���܂ō~��čs���B
�ނ������ɂ́A���̓���P�Om���炢�܂ŁA�ԉ̂悤�Ɉ꒼���ɃX�L�[���オ��A�Ђ�Ђ�Ɨ����Ă���ƕ\�����Ă����B
�@�����u���̂����A�ł���悤�ɂȂ��B�v
���́A�����@�N���搶�̏o�ԁB
�X�L�[���͂̎��ɂ��Č��݂ɑ̏d���悹�čs���A���E���݂ɉ����o���������B����͏�����肭�������B���A������Ə������A�X�L�[���߂Â��Ă���ƌ����̂����A���������ɋ߂Â��Ă͂��Ȃ������B
�@�@�@�@�@
�@�@�@�@���̂ĂȂ��ł�I
�����̒��ԁA���ɃQ�����f�ɂ͈����Ƃ�����Ȃ���l�ŗ��K���Ă���ƁA�Z���������Ă����̂Łu�Z���A�E�F�[�f���������Ă��������B�v�Ƃ����ƁA�ȒP�ɂn�j���Ă��ꂽ�B
�X�L�[���͂̎��ɊJ���āA�㉺�����g���Ȃ����ƌ������ŁA�r�̋Ȃ��L����A�������Ȃ���X�L�[�ɉd���Ă����B
�ꎞ�Ԃ�����Ɓc�B
�@�Z���u���̂����o����悤�ɂȂ邩��A������ȁB�v
�@�m�@�u�E�E�E�E�v
���̂Ă�ꂽ�B���̂����ł͂Ȃ��A�����ł���悤�ɂȂ肽�������B
�Z���������ɂ́A�Ȃ��Đ�ʂ𑨂��A�L���ăX�L�[���čs���̂����A���̏ꍇ�A���x����Ă����ɂȂ�炵�������B
��͂莩���̊��o�Ƃ��āA�����ł��Ȃ������̂��B
�����͊F����ɂƂ��āA�傫�ȃe�[�}���Ǝv�����A�����猩�Ă���Ώ�̂͏�ɉ��������A��ϓ��������Ȃ������鎖���낤�B�������A�����ڂ��x����Ă͂����Ȃ��B
�f�����A��������X�L�[���Ȃ�������Ȃ��̂��B
�����Ƃ��Ă��Ă��A�X�L�[�Ȃlj��킯���Ȃ��B
�@��������X�L�[���̂�����A��������̂����͓̂��R�̎����B
�@�@�@�@�����ƊȒP����
�X�L�[���͂̎��ɊJ������Ԃł����Ƃ��Ă���A���Ȃ��̑̂͂Q�{�̃X�L�[�̐^���ɂ���B���̂܂܂Ȃ�E�ɂ����ɂ����Ȃ��B
�����ŏ�̂��E�ɌX���悤�A����ƃX�L�[�����ɉ�̂͂Ȃ����H�@�@
�ŏ�����E�̃X�L�[�͍��Ɍ����Ă��邩��A�̏d�̃o�����X������邾���ʼn���Ă��܂��̂��B�ĂсA��̂�^�������ɂ��Ĕ��ɌX���悤�A���x�͔��ɉ��A���̌J��Ԃ��ł���B
�Ƃɂ����ȒP�ɍl���Ăق����B���̓��������������Α���A�f�������Ώ����E�E�E�B�����l����̂��B
�F����͏�̂���ɉ��Ɍ����ĂȂǂƍl���Ă��邩������Ȃ��B
�������A����Ȏ����l����K�v�͂Ȃ��B
�Ȃ��Ȃ�A�����͉�]���a���������̂ŁA������X�L�[�͑��������������ɂȂ�B���R�A��̂����ĉ����������Ԃ������Ȃ�ł͂Ȃ����B
�@�@�@�@�����ł�����B�
���āA���̂Ă�ꂽ���͂��̍��A�Ƃɂ��������A�ǂ��֍s���Ă�����肾�����B
�v���y���^�[���Ƃ����̂������m���낤���H
�W�����v���ăX�L�[�̌�����ς���A�����A�����čs���̂��B������Ζʂł��ƁA�ǂ�ǂ�X�s�[�h���o�Čʂ��傫���Ȃ�B
�傫���Ȃ�Ώ����ł͂Ȃ����A�v���y���^�[���ł��Ȃ��B
�����ŎΖʂ���ɏオ���čs�����K�������B�m���Ɉ�x�̒��n�Ŏ~�܂��悤�ɁA���x�����x�����K�����B
�m���Ɏ~�܂��ƌ������́A�X�s�[�h���o�Ȃ��B
�X�s�[�h���o�Ȃ���A�ʂ͑傫���Ȃ�Ȃ��̂ł́E�E�E�����l�����̂ł���B
���̈ʋɒ[�ɍl���A�ɒ[�ɑ̂����ƁA����炵���Ȃ邩��s�v�c�ł���B������A��������ł������Z���ɁA
�u�m�A�i�C�^�[�ŃE�F�[�f��������Ă�����Ȃ����A����ł�����B�v�ƌ���ꂽ�B
���ɂ�����I�E�F�[�f�������ł����̂��B
�@�@�@�@���Ȃ����g���킩��₷���l��M���悤�@
�`�Ȃǂ��ł������B
�Ƃɂ����A�Z���G�b�W���O�Ŏ~�܂銴�o�����ގ����B
���Ȃ����g���킩��₷���A�\�����₷�����o�����ނ̂��B
���͍Z���̌����A�Ȃ��Đ�ʂ𑨂���ƌ������o���A�W�����v���Ē��n���鎞�ɁA�m���Ɏ~�܂�ƌ������o�ŗ����ł����B
���x���\���グ�Ă��邪�A��l��l���o���Ⴄ�̂��B
�����āA���̊��o�̈Ⴂ���A���낢��Ȑl��X�L�[���t�ɕ����Ă݂�����B
���̒��Ŏ����̊��o�ɋ߂��l�̊�����A���̖ڂɏĂ��t����̂��B
�����āA�����̂��̂ɂ���̂��B���ȏ��̂悤�ȓ�����Ԃ��l��������A����Ȃ��͖̂�����������B
�@�Ƃɂ������Ȃ��̕�����₷��������Ԃ��Ă����l��M���悤�B
�@�@�@�@�����N�����đ��v�Ȃ́H
�����Đ�����A�����Q�����f�ŃP�K�l�����̘A�������蒼�s�����B
�ǂ����Փˎ��̂炵���A�ْ�������B�s���Ă݂�ƁA�����@�_���|��Ă���B����̃X�L�[���[�͑傫�ȉ�����Ȃ��A����S�ł���B
�������A�ނ̊�͂ǂ����A����ꂠ�����Ă���B�a�@�֒��s�A���@�ƌ������ɂȂ����B���̒j�́A�Q�����f�����̎d�������ɂ����̂����A�����N�������āA�����ɃX�L�[�ɔR���Ă����B�{�C�ŗ��K���Ă����̂��B
�ނ��܂����Ɠ����悤�ɁA�X�L�[�ȂǏo���Ȃ������̂����A���̍��ɂȂ�ƁA�啪�����悤�ɂȂ��Ă����B
�@�`���ł��������Ƃ���A�זv���܂ł���B
��p�̂��ߓ����ۂ߁A�o�Ƃ����悤�������B�a�@�ɂ���ԃX�L�[��ł́A�J���{�c�ƊF���Ă�ł����B�u�J���{�c���C���������H�v�@�@
�@����������A�����l�́A�K�����̂悤�ɕ����ꂽ�B�����āA�މ@��ɂ́u�`���l���v�ɉ������ꂽ�B
�`���l���́A��ɂȂ�ƃX�g���[�Ńr�[�������ށB
�܂��傫�Ȍ����J���ƒɂ��炵���B
�@���ꂩ�琔��������ƁA�������ю��̖X�q�����Ԃ�A���ƂȂ�������`���l���̎p���Q�����f�Ō�����悤�ɂȂ����E�E�E����ׂ��I
�@�@�@�@�j��ő�̃��C�o��
�Q�������{�ɂȂ�ƁA���C�o�������Ɣ�r����鎖�������Ȃ��Ă����B
���̒j�����̑傾�������Đ��̂ł����j���B
�@���ӋZ�̓o�N�]�B�Ȃ�Ɛ�̏�ŁA�X�L�[�C�𗚂����܂܃o�N�]���ł���̂��B
�@�Z���u�N���A���O���A�m�̂ق�����肢��Ȃ����H�v
�@�����u�m�͏�肭�Ȃ�܂�������B�v
���܂��݂�I�E�E�E�N�̂������ł��B
���́A�V���ő̈�̋��t�����Ă���炵���B��͂�A���̂ł������ŋ����Ă���̂��낤���H
�@�@�@�@���肭��֎�I�@�@�@�@
���̍�����u�����^�[�{���v�́A���@���`(�P���j�Ƃ悭���K�����B
�ނ͑ٓ��p�[�N�z�e���ɋ߂Ă��āA���Z�ł́A���o�ŃC���^�[�n�C�܂ōs�����Ƃ����l���ŁA��X�͊֎�ƌĂ�ł����B�i�N�͈��j
��ɏ��w�����A�w�����Ƃ��ׂĂ��Ƃ��Ɏ��A�Ƃ��ɍ��i����̂��B
���w��������̍��i���\�̒��A��������킹�������b�͌�ŏ������ɂ��悤�B
�ނ̊���́A�֎�ƌ������̂Ƃ���h�[���Ɣ����Ă���悤���A���̒����Q�����f������������B
�Ƃɂ����A�~��Ă���̂������猩�Ă���ƁA���ރh�h�h�[�Ɖ�����������悤�������B�z�e���ł̋Ζ����Ȃ����ɂ́A�����͂��������ق��������A�����͂������A�ƃA�h�o�C�X�𑗂荇���ō��̗F�ł������B
�������ނƂ��̑傫�ȑ̂ŁA�u�傫�ȌI�̖̉��ţ�ƌ����̂�U������Ȃ���̂��A���̑O�ŏ����̂悤�Ɏ�����킹�鎞�̂������낳�A����������̂��B
�@�@�@�@
�@�@�@�@�����H���ꂪ�閧����@�@�@�@
�ŋ߂ł͓~�ɂȂ��Ă��Ⴊ���Ȃ��A�ǂ̃X�L�[�����s���ō����Ă���悤�����A���̍��͂Ƃɂ����悭�~�����B
����≮���̐�~�낵�Ȃǂ͑�ς����A�Q�����f�ɐႪ������p�g���[���ɂ͂��肪�����B���A�i���֎~�̊Ŕ�l�b�g�Ȃǂ��ƃP�K�l���o�Ȃ�����d���͏��Ȃ��B
���̂Ƃ��傫�Ȏd���Ƃ����A�Q�����f�̏���ł���B
����ƌ����X�L�[���A�X�g�b�N�������Ċ���B�p�g���[���̓X�R�b�v�Ȃǂ����������čs�����������A�X�g�b�N�����Ɗ������Ȃ�B
���̍��悭����ꂽ�̂��A�X�g�b�N�̏o�����ꂾ�B
�܂�ŒK�������������悤�ɁA���܂��Ă͏o�����J��Ԃ��J�b�R�����B
���@������͂U�ΔN��ł������w�����A�ڂ��傫���̂ŁA���͖ڋʂ̃}�[����ƌĂ�ł����B
�X�L�[�Z�p�I�茠�Ƃ����̂������m���낤���A�X�L�[���t�B�̑��ł���B���̑��ŏ�ʂɓ��܂����l�B���f�����X�g���[�^�[�ɂȂ��čs���B�ނ͂��̑��ŐV�����\�I��˔j�������Ƃ�����A�V��������{�I�ɂ͂Q�T�[�R�O�����i�݁A���̂����T�C�U�����f���ɂȂ��Ă��邩��A�ǂꂾ������悩�킩�邾�낤�B
�}�[���A�킽���̃X�g�b�N�����߁A�閧���������Ă��ꂽ�B
����́A�q���̗����ɗւ�����Ă���A����ʂ��̂��B
���x�悢�����ɍ��ꂽ���̕���̎g�����́A�̂̑O�ł����s�[���ƒ����Ă���悢�B������A���g�͂Ȃ����ł͂Ȃ��A��������Ă���̂��B�@
����Ȃ��Ƃ����Ă���ƁA��ʂ̃X�L�[���[�͂ǂ��v���̂��낤�A�u�n���݂����v��������Ȃ��B�������A����Ȏ����l���Ă͂����Ȃ��A�X�L�[���t�B�͎����̈����Ƃ�������߂ɕK���Ȃ̂��B
�������āA���낢��ȍH�v�����Ȃ���A�����̊���𗝑z�ɋ߂Â��čs���B
�@�@�@�@����ꂽ���A�Y��Ȃ��ŁI
�X�L�[�w�Z�ɓ���ƁA�u���O�ɏo���āB��Ȃǂƒ��ӂ������������Ǝv���B�X�L�[���t�͂��Ȃ������O�ɏo�����ɂ���āA�����ł��O�ɏ���悤�ɂƎv���A����Ȓ��ӂ�����B
�������A�����̐l������o���Ƃ����ɖY��A�肪�������Ă��܂��B
��ɓ��̒��ɒu���ČJ��Ԃ����ő̂��o���Ă��܂��B
�C�������Ƃ��Ɏ����̎v���ʂ�̏��ɂ���悤�ɂȂ�A�Y��Ă��܂��Ă��܂�Ȃ��B��x�̂��o���Ă��܂��Α��v�A���Ȃ����J�b�R�悭�\������悤�ɂȂ��Ă���B
�Ȃ��A����o���ƖY��Ă��܂��̂��H�@���̂��Ƃ��l���邩�炾�B
�X�L�[���t�͍��̂��Ȃ��ɂƂ��Ĉ�ԑ�Ȏ����A�h�o�C�X����B
���̎��͍l�����A����ꂽ�������ɏW�����悤�B
�@�@�@�u��肭�Ȃ������v
�@���̍��A�悭�Z���Ɗ������B�@
���낢�닳����ƁA�Z���͏�肭�o���Ȃ����ɁA�u�o�J�����[�A���肭���v�����Ȃ������B
�@���x�����ɂ���ƁA����ė����v�Ƃ����āA�������̑O�������Ă������B����čs���B�Z���̃V���v�[���̏���悤�ɉ���Ă�����肾���A�ǂ����Ă�����čs���B���t�g�ɏ���
�@�Z���u�m�A����������H�v
�@�m�@�u�͂��v�@�@�@�����āA�u�v���Ԃ�Ɉ�t��邩�B�v�ƁA���Ƃ��₵�����ȁA�����Ċ��������Ȋ�Ō����̂��B
�@��肢�l�̌�𒅂��Ă䂭�Ɨ�����čs���̂͂Ȃ����H
����Ă��鎖���Ⴄ�̂ł���A�G�b�W�̎g�������Ⴄ�̂��B
���̎��������m��̂͂���������A���w�����ɂȂ������������Ǝv���B
�����āA���{������ƃ`�������W�R�[�X�ɓ����Ă������B
�����͑ٓ��X�L�[��ł���Ԃ̓�ŁA�Γx�R�O�x�ȏ�A�傫�ȃR�u���s�K���ɕ���ł���B
�Z�������Ō��Ă��钆�A���͂����̂Ƃ��芊���Ă������B
�u�m�A��肭�Ȃ����ȁv�ƍZ�����|�c���ƌ������B
�u�����A�����Ă܂�����v�Ɠ��������́A�T���O���X�̉��ł��ӂꂻ���ɂȂ���̂�K���ł��炦���B
�F����A�m���ɃX�L�[�͓���B
�������A������߂��ɗ��K����A�K���o����悤�ɂȂ�B
�@�ǂ�Ȃɏ�肢�l�ł��A���܂ꂽ�����犊���킯�ł͂Ȃ��A�R�u������Ă͂����Ȃ��A�Ƃɂ������x�����킷�鎖������B
�@�@�@�@�`�������W�R�[�X�͒T�����H
�@���́A��������Ԃɏo�čs���ƁA�X�L�[�w�Z�ɂ́A�قƂ�ǖ߂�Ȃ������B�悭�A�����ŌĂꂽ�肵���B(���N����A�g�����V�[�o�[�̌g�т𖽂�����B)
�u���O�́A���ł������牽���ɂ��邩�킩��Ȃ��v�Ƃ悭������B
�@�Z���̓Q�����f�����ĉ��Ȃ���A�����N���ǂ��ɂ��邩�m�F���Ă����B�ǂ��ʼn������Ă��邩�m���Ă����B
�@�������A���͉����ɂ��邩�킩��Ȃ��E�E�E
�@�����A�����`�������W�R�[�X�ɂ����̂��B
�@�@�@�@
�@�@�@�@
�@�@�@�@���������邾������
���āA������x����鐶�k����Ɂu�R�u�Ζʂ́A�ǂ�����̂ł����H�v�Ƃ悭�������B
�u�R�u�̓��ŕ�������ŁA�J�ŐL���̂ł����H�v�ȂǂƎ��₳���B
�{���ɂ悭�����Ă���Ǝv���B������͗ǂ��킩��Ȃ����A���ȏ��ǂ���ɓ�����A�����������ɂȂ邾�낤�B
�@�������A�{���ɂ������낤���H�F���R�u�̓��ŕ��������ɂ́A�R���S���A�R�u���Ă��܂��ĂȂ����낤���B�����Ă��܂��Ă���A���Ƃ͉����o���Ȃ��E�E�E�E�ɂ��v��������Ɍ��܂��Ă���B
���ȏ��̎��͏�肭�Ȃ������ɕK�������ł��邩��S�z���Ȃ��Ă����B
���́A�Ђ�����R�u�����Đ��n���ꂽ�ΖʂƎv�����݁A�����Ɍ�����������悤�ɂ����B�����̃��Y���Ń^�[����A��������A��鎞�ɂ��܂��܃R�u����������A�Ȃ�������̐��E�ł���B
��肭�o���Ȃ��āA�]�Ԃ͓̂�����O�B
�������X�L�[���܂킻���Ƃ������A���܂���������Ύv�������X�L�[�����Ȃ��A���ǂ���Ύv�������X�L�[��������肷��B����ŏ\���A�R�u�ɍ��킹�ď�肭�����Ă���悤�Ɍ�����B
����\�����āA�����ɑ̂��������Ă����悤�ȏ㋉�҂ɂȂ�Ȃ�����A�R�u�̓��ŕ�������ŁE�E�E�Ȃǂƍl���Ă�����A�m���ɒʂ肷���Ă��܂��B
�����A�X�s�[�h���o�ăA�E�g�ł���B
�F����́A�w�����͏�肢����A����Ȃ��Ƃ��ł���̂��E�E�E�Ǝv����������Ȃ��B�������A�ǂ��l���Ăق����A�R�u�̓��ŁE�E�E�ƍl����̂ƁA���i�̎����ɂł��邱�ƁE�E�E�ƍl����̂ƁA�ǂ��炪�ȒP�ȍl�����낤�B
�����Ȃ��́A�R�u�Ζʂł̊���������̊��o�Ƃ��Ď����Ă��Ȃ��̂��B
�����Ă��Ȃ����o�Ŋ��낤�Ƃ���E�E�E�o����킯���Ȃ��ł͂Ȃ����A����l���Ă͂����Ȃ��B
������͒N�����ďo���Ȃ��ł͂Ȃ����A�C�y�ɍs�����I�@�@
���Ȃ��ɃR�u�Ζʂł̐V�������o���g�ɂ����Ƃ��A���ȏ����v���o���Ă���Ă݂悤�B�K���킩��悤�ɂȂ��Ă��邩��B�����āA���ȏ��ǂ���̊��o���������邤���Ɉ��A���Ƃ͂��̉𑝂₵�Ă��������B
�X�L�[���t�����āA�������钆�A���ׂĂ���肭�o���͂��Ȃ��B
��肭��������s���Ȃ������肷��Ȃ��ŁA�����̊��o�ɂȂ�܂ŁA�����Ɖ䖝���Ă��邩��A�����������邾�����B
�����������肾�Ǝv���B
�R�u�̓��ŕ������ށA�Ƃ����̂��A���Ȃ��̊��o�Ƃ��Ă��ނ̂��B
���̊��o�ł́A�������܂Ȃ��B�r�ɂ͊߂�����B
�R�u�ɂԂ���A����ɋȂ���Ȃ����낤���H�@�@�Ȃ����Ă��܂��̂ł���B
���Ȃ����猩�āA�����̋Ȃ����Ă��܂����r�́A��������ł���悤�Ɍ����Ȃ����낤���H
�@�@�@�@
�@�@�@�@���Ȃ��̊��o����ԑ��
����l����K�v�͂Ȃ��A�����J�ɂ�邾���ł����B
�n���̈��K�L�����́u����Ă�A�ł��邳�B�v�Ƃ����A���ꂪ�ނ�̊��o�Ȃ̂��B�ł́A���Ȃ��̊��o�͂ǂ����낤�B
�X�L�[�G���Ȃǂ̘A���ʐ^���v�������ׂĂ������������B
���̂R�R�}�ڂ����Ȃ������Ő^�������̊��o�͂ǂ����낤�B�ǂ��ɗ͂�����A�ǂ��������ƈႤ�̂������ނ̂��B
�����āA����Ɠ������o�ɂȂ�悤�A���Ȃ��̓��ő̂ɖ��߂���B
���߂𑱂��邤���ɑ̂��o���Ă����B�����Ȃ�A�������߂���K�v�͂Ȃ��A���ꂢ�����ς�Y��Ċy�������낤�B
�@���ȏ��ǂ����鎖���A���Ȃ��������̊��o�Ƃ��āA���ގ�����ԑ�Ȃ̂��B
�@�@�@�@
�@�@�@�@����������肵�Ȃ��ŁI
�ٓ��X�L�[��̃i�C�^�[�͑��A���A��O�Q�����f�ʼnc�Ƃ��Ă���B
���̑�O�Q�����f�̉����Ζʂ�����Q�����f�֑����Ζʂ́A����Ԃ��o��Ȃ��̂ŁA�}�ΖʂɐV�Ⴊ�c��B��X�́A�����y����ł����������Ă����B
������i�C�^�[�I����A�Q�����f���ɂ��q�����Ȃ������m�F���Ȃ���~��čs���ƁA�r���ɍZ���������B
�u�m�A�����A���q��������Ȃ�����A��������w�Z�܂Œ����~���Ă݂�B�v�@
�u�͂��v�Ɠ������킽���́A�����V����y���ގΖʂɌ���������o���B
����������Q�����f������A���b�W�O�ŃJ�b�R�ǂ��~�܂鎖���C���[�W���āB
����e���Q�����f�A���\����������Q�����f�E�E�E�������Ȏ����N����͂��ȂǂȂ��B
�Ƃ��낪�A���͗���ꂽ�B
��O�Q�����f���瑱���}�Ζʂ������Ă���͂��Ȃ̂ɁE�E�E���ł����B
���n�������́A���̏u�ԁA���|�������Ζʂ̐�ɂ����݂��B
���b���炢�o�������낤���A������Ȃɂ��ۂ����̂��������l�����A�삯�オ���Ă���E�E�E�Z���ł���B�ނ̎������́E�E�E���W���[�������B
�X�L�[�w�Z������ƁA�����炢�����̐l�e��������A�����Ə��Ă���̂��낤�B
�Z���̓��W���[�̒[�����Ɏ�������Ɓu�m�A��яo�����Ƃ���܂œo���Ă݂�B�v�ƌ������B�����Čv�����ꂽ�����́E�E�E�R�R���������B
�X�L�[���t�B�͊F��������D�����B
���̌o������A���̒��x�ۑ��^���Ă��ƁA����Ȍ��ʂɂȂ�ƌ������Ƃ��킩���Ă���B�����āA���̒ʂ�̌��ʂɂȂ�Ƒ�ϊ�ԁB
�Ƃɂ����X�L�[�Ɋւ��Ă͑�ϒP���ɔ������čs���B
�w�����B������قǒP���ɃX�L�[�𗝉����Ă���̂��A�F����ɂƂ��ăX�L�[�́A�����Ƃ����ƊȒP�ł���ׂ��ł͂Ȃ����낤���B
�����ƒP���ɁA�ȒP�ɍl���������悤�A�u����܂��ɂ����āv�ƌ���ꂽ��A�Ƃɂ�����������o���Ă݂悤�B
���߂ăX�L�[������l�ɂƂ��āA�m���ɓ�������낵����������Ȃ��B�����炱���A�ȒP�ɍl���悤�B
�@�@�@�@�s�^���Ƃ���Β��ȒP�@�@�@�@�@
�����������ė����Ă����Ȃ��A����͂��Ȃ��������̂ł͂Ȃ��B
��̏�Ńc���c������X�L�[�𗚂��āA���̏�Ζʂɗ��Ƃ��Ƃ����̂����瓖����O�̎��B�X�L�[�𗚂��ĎΖʂɗ��ƌ������o���A�����̒��Ő������鎖���B���̏�ɗ��̂Ɖ��������Ⴄ�͂��ł���A���̉������Ⴄ�������ގ����B
�ʂ����ăX�L�[���t�B�́A�u�搶�͂ǂ�Ȋ��o�ŁA�����Ă���̂ł����H��ƕ����ꂽ���A�������邾�낤���A�u�R���̃G�b�W���g���āv�ȂǂƓ����邩������Ȃ��B�������A���̂��Ȃ��ɕK�v�Ȃ̂͂���Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B
�Ⴆ�u���W���x�[�ɂȂ�������Łv�Ƃ����̂͂ǂ����낤�B
�����A���ꂪ���Ȃ��̊��o�Ƀs�^���Ƃ���A�ȒP�ɗ��Ă�̂ł���B
�@�@�@
�@�@�@�@�Ă݂Ȃ����킩��Ȃ�
�����ĂR���ɓ���A�����͗p���Ŏ��ƂA�鎖�ɂȂ�x�݂�������B
��̂��Ƃ��Z���Ǝ�������ł���ƁA
�@�Z���u�m�A�������ĂQ����B�v
�@�m�@�u�����ł���B�v
�@�Z���u�������Ď��Ȃ���A���T�P�����Ȃ���B�v
���̗��T�ƌ��������A�ٓ��ł͍Ō�̃o�b�W�e�X�g�������B
�@�m�@�u���M�Ȃ��ł��B�v
�@�Z���u�Ō�̃e�X�g�Ŏ��Ȃ���A���O���N�N�r����B�_���Ȃ�A�悻�̃X�L�[��֍s���Ăł��A���N���Ɏ��Ȃ�����߂��B�v
�@�m�@�u�E�E�E�E�v
�@�Z���u�����������������v���B�v
�@�m�@�u�{���ɑ��v�ł����H�v
�Z���u�Ă݂Ȃ���A�킩��Ȃ���B�v
����Ȃ����̌�A�킽���̎͌��߂�ꂽ�B
�@�Z���u���낻��Q�邩�B�v
�m�@�u�E�E�E�v
�z�c�ɓ��肱�݁A�������̌��t���悤�Ƃ������A�Z���͂������̒��ɂ���悤�������B
�@�@�@�@��2���@�@����@�@�����Ē��ԓ���
�@�@�@�@���M��������
�Ƃ��Ƃ��R��1�O���A�Q���̓��ɂȂ����B
�o�b�W�e�X�g�������̂�����������Ǝv�����A��ϋْ�������̂ł���B����ԂŃQ�����f�̏�����I���A�X�L�[�w�Z�ɖ߂�ƊF�y���������B
��C�u�t�̘a�c����ɂ́u�m�A�_�̑���Ȃ����́A�P�_�P�O�O�O�~�ł�������E�E�E�v�Ƃ����Ă��炩��ꂽ�B�ނ͂Ƃɂ����ׂ��̂����A���Q�̃X�L�[�Z���X�����j�ŁA������ˑR��肭�Ȃ��Ă����ƌ����l��������Ȃ��B���ۂɂ̓R�c�R�c���K���Ă������E�E�E�B�Ƃɂ����S���Ńv���b�V���[�������Ă����B
�p�g���[���̃��b�P�ȊO�X�L�[�E�F�A�Ȃǎ����Ă��Ȃ����ɁA�Z�[�^�[�ƖX�q�A�S�[�O�����݂��o���ꂽ�B
�u�m�A���̃Z�[�^�[�݂�����A�g�b�v���i���Ȃ��Ⴞ�߂�����ˁI�v
��u�t�̒��A�g��_�A�O�コ��̂����t���������������́A�[�b�P���P�Ԃ����҂̗�ɓ����Ă������B
�P�C�Q���҂Ɏg�p�ΖʁA���ԂȂǂ��������ꃊ�t�g�ŏオ���čs���B
���t�g�W�̕������B�������̎��͒m���Ă��āA�撣��悤�Ɍ����Ă����B�@
�ŏ��̎�ڃp�������^�[���B
���R�[�b�P���P�Ԃ��犊��B����͖{�ԁ@�������C������Ɏn�߂�ꂽ�B����́A�����j�R�j�R���Ă��Ď����D�����B���ꂩ��o�b�W�e�X�g��ڎw�����ɂƂ��đ�ϋ����̂���Ƃ��낾�Ǝv�����A���蒆�͉����ǂ��������A�܂������o���Ă��Ȃ��̂ŏ��������o���Ȃ��B
�悭�A�������̋߂��ɍs���Ă���A���������A���������B��Ƃ��u����o���͑���̂ق����_���o�������������Ŋ������B�v�ȂǂƁA�����m�Řb���Ă���̂����ɂ��鎖�����邪�A���̍��̎��ɂƂ��Ă͐M�����Ȃ����Ƃ������B
���̏ꍇ�A�u����Ă������v�Ǝv���A���̂��Ƃ������ɂȂ��������A��m���ɍ~��čs�����v�Ǝv���A�m���ɁA�m���ɂƓ��̒��ŌJ��Ԃ��Ă���̂�����t�������B�ƂĂ��ł͂Ȃ����u�R��]�����珬�������āv�Ȃǂƍl�����Ȃ������B
����ƌ������ŁA�����ł����ْ����Ă���̂��B
������Ƃ��l����܂��܂��ْ�����ł͂Ȃ����A��������l����K�v�͂Ȃ��B�������Ȃ����ςݏd�˂Ă������̂��A���̊���ɏW���̂��B
�@�����A���M�������āI
�@�@�@�@�_��������������
���Ȃ�����i�Ȃǂ���킯���Ȃ��B���ʂ��o��A�_�������Ȃ��ɑ���Ȃ����̂������Ă����I�܂����K���Ď�����ł͂Ȃ����B
������͏�Ɍ��C��ł��̖ڂ�{���Ă���A�o���ꂽ�_���͑f���ɐM���Ă悢�B�Ⴆ�����ڂłU�W�_�������Ƃ��悤�A���̌��ʂ��ǂ��~�߂邩�H�u�����͂����ƁA��̂����J�[�r���O�Ŋ����̂ł����A�R��]�ڂ�����Ă��܂��āB�v�Ȃǂƌ����l������B����Ȏ��͂��肦�Ȃ��A�����o���鎖�����o���Ȃ��̂��B3��]�ڂ��ǂ��̂����̂ł͂Ȃ��A���ׂă_���Ȃ̂ł���B����1���̌���ŁA���ׂẴ^�[����͋����������J�[�r���O�ŁE�E�E�Ȃǂƌ�������A���i�҂ȂǏo�Ȃ��B
���x�������悤�Ɏw���������āA���ׂẴ^�[���������ɂȂǂł��Ȃ��̂��B����Ȏ��������l�́A���̍l���������߂�K�v������B������͕������Ă��̎��i�����B�u�����A���̐l��3��]�ڂɎ��s��������_���B�v�Ƃ����A
68�_���o�����Ȃǂ��肦�Ȃ��A�X�L�[�͎��s���ē�����O�Ȃ̂�����B�@
�@�@�@�@�]���đ��v�I
�ɒ[�Șb�A1��ڂ��炢�]���đ��v�A���i�_�͏o��̂ł���B
�������́A�w��������̎��Q��ڂœ]��ł��܂����B�������A������ƍ��i���Ă���B(�ڂ������͌��)
�P���̌���ł��T��ڂقǂ��钆�A���̎҂����łV�Q�_�ς��ďo���͂��������Ƃ��悤�B�S��ڂ��I���ĂW�_�I�[�o�[�T��ڂ߂œ]��łU�U�_���ł��B���������v�_�͂S�_�I�[�o�[�A�����ȍ��i�ł͂Ȃ����B�������S�_�I�[�o�[���邭�炢���A�����Ƃ���肢�ƌ����Ȃ����낤���B�����A�ׂ������͍l���Ȃ��Ă����B
�X�L�[���t�Ɂu�o�b�W�e�X�g�����������B�v�ƌ����đ��k��������B
�X�L�[���t�͂��Ȃ������i���邽�߂ɑ���Ȃ����̂��A�ڂ̑O�łS��]�����Ă����A���ׂČ����o���Ă����B
�@�����āA�u�������Ȃ����v�ƌ���ꂽ��E�E�E�����܂œǂݐi�߂Ă����������킩�肾�Ǝv���A�X�L�[���t�̐����������̊��o�Ƃ��ė������A�\�����čs���悢�B�ق�A�����ڂ̑O�ɍ��i�������Ă������낤�B
�@�@�@�@�Q�����i
�Q���̌�����I���A�X�L�[�w�Z�ɖ߂�p�g���[���̃��b�P�ɒ��ւ���ƁA�����������������A�ʎ��ł͓��_�̏W�v���n�܂��Ă���B
���͉��Ƃ������Ȃ��C���ŎR�������U�Q�����f��ڎw�����B
��U�Q�����f�̉��ɏ����ȃp�g���[���l�ߏ�������A���j���ɂ͏펞�Q�l�̃p�g���[��������B�����̎�A����(�������P���j�͍Z���̒�ŁA�d�����x�݂̓��j���ɂ͎R�ɏオ���Ă��ăp�g���[��������B
�u�m�A����I������H�v�@�u�͂��A�����܂����B�v����������ƁA����ȏ�͉����������Ƃ��Ȃ������B���́A��ԉ��ɍ���Ƌ�������n�߂��炵���A�Ƃɂ����N�^�N�^�ɔ��Ă����B
�����č��i���\�̎��ԂɂȂ�A�X�L�[�w�Z�ɂ͌��ʂ�����o����邪�A���͂������瓮���Ȃ��܂܁A���t�g�^�]�I�����ԂɂȂ�B
��U�Q�����f����R���ɏオ��ƁA�X�L�[�w�Z�ƃp�g���[�����W�����Ă����B���̂Ƃ�������オ���Ă���A���͂�����ʂ�m���Ă���B�Ȃ����A�F�₵�����ȖڂŎ������āu���i���Ă��B�v�ƌ������肷��̂ŁA���M�̂Ȃ����͂������ĕs���ɂȂ��Ă��܂��B
�����Ĉ�Ԏ��Ԃ̂�����ъԃR�[�X��[���̒��~��Ă������B
�X�L�[�w�Z�ɖ߂�ƁA�O�コ�u�m�A�������������ɗ��Ȃ���_������Ȃ��A�P�_�P�O�O�O�~������T�O�O�O�~�ˁB�v���͓��S�A�T�_������Ȃ��̂��E�E�Ǝv�����B
�@�����߂����Ȃ肩�������A�e�[�u���̏�ɍ��i�ƃo�b�W�A���ѕ\���u���ꂽ�B
�@�Q�X�Q�_�A�P�Q�_�I�[�o�[�̃g�b�v���i�������B
�@�@�@
�@�@�@�@�X�L�[��͉��N�H
���āA�܂���������Ȃ��l���P�V�[�Y����2���A1���ƍ��i����A����Ȏ��͂��蓾�Ȃ��Ǝv����������Ȃ��B�������A���͓��R�̎����Ǝv���B
��ʂ̃X�L�[���[���N�ԂP�T������Ƃ��悤�A������i�C�^�[�܂ŁA�H���Ȃǂ̎��Ԃ������Ė�P�O���Ԋ���A�P�T���~�P�O���ԁ��P�T�O���ԁB
���͂ƌ����ƁA�P�Q���Q�T������R���P�O���܂Ŗ�Q�������A���ۂɃX�L�[�Ŋ��鎞�Ԃ��T���ԂƂ��悤�A5���ԁ~�V�T�����R�V�T���ԁA�ǂ����낤���ʂ̐l�̂Q�N���ȏ㊊���Ă���̂��B
���������āA�F����͍��̏�Ԃő����Ă��A�R�N�ڂɂ͊m���ɂP���ɍ��i�ł���Ƃ������Ƃł͂Ȃ����B
����ł�����̂͂Ȃ����H�@���K���@���Ԉ���Ă��邩�A�l�������Ⴄ�̂��B�܂��A�Q�����Ƃ�ȑO�̎��̖ڕW�́H�@�����܂œǂݐi�߂Ă������������ɂ́A��������̃q���g���������Ǝv���B
����̍s����Ζʂ��S��]�Ŋ��鎖�ł��V���e���^�[���ł��A���肩�珬���ɂ��鎖�ł��Ȃ��̂��B
���ɂ̓��t�g�̉�(�V��)��]���Ɋ��鎖�A�R�u�Ζʂ�]���Ɋ��鎖�A�����Q�����f���~���鎖�E�E�E���K���@�͉��x�����x���J��Ԃ����������B
�����炱���A���낢��Ȋ��o���g�ɕt�����̂ł͂Ȃ����낤���B�V���e���^�[���������Ă�����Ă��A�E�F�[�f�����������Ă�����Ă��o���Ȃ������B�������A�V���������������K���@��m��Ɛ�����ɂ͏o����悤�ɂȂ����B
�F����́A�ǂ̂悤�ȂƂ���ł��]���Ɋ���Ƃ��������ڕW���낤���H�@�����ڂ�Z�p�̂��Ƃ���l���Ă��Ȃ����낤���A�X�L�[���o���鎞�ɑ�Ȏ��͉����H����͌o���ł���B
�q���B���N�ɋ����ł��Ȃ��A���̂܂ɂ���肭�Ȃ��čs���͉̂��̂��A�]���ɒ��ԒB��葬�����܂ō~��鎖���l����B�����āA��������������邽�߂ɍH�v������̂��A���̍H�v���Z�p�Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���B
�܂��A�]�Ȃ����߂ɃX�L�[���͂̎��ɂ���A�������邽�߂ɕ��s�ɋ߂Â���A�}�ΖʂŃX�s�[�h���o�߂��ē]�Ԏ����Ȃ��悤�ɍׂ������B
�����A�F������q���ɖ߂낤�B�e�N�j�b�N����ɑ��炸�A�]���Ɋ��鎖�������l���āB�������q���ɖ߂��Ă��R�N��ɂ͂P��������B
���łɉ��N���X�L�[�𑱂��Ă���l�Ȃ�A���̎��Ԃ͂����ƒZ�k�ł���ɈႢ�Ȃ����A�N�Ԃ̊������������Ȃ��l�́A�����₤���߂ɃX�L�[�w�Z�𗘗p��������B
�X�L�[���t�͏����ł������A���Ȃ�����肭�Ȃ�̂ɕK�v�Ȃ��Ƃ��A�h�o�C�X���Ă����B���̃A�h�o�C�X�����Ȃ����A���Ȃ����g�̊��o�Ƃ��ė�������̂��B�����čĂѕǂɂԂ�������A�A�h�o�C�X�����߂悤�B
��x�ɑ�����]��ł��_�����A�ЂƂЂƂ����̕��ɂ��čs�����B
�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@����͖{���ɍ��i�j���ł����H
�X�L�[���t�͖{���ɒP�����B���̖�A��X�̗��ō��i�j���ł���B
���������ɏ\���l�����荞�݁A�������ށB�X�L�[���t�B�́A�������R�����Ă͎������݂���������������Ȃ��B�����̃X�L�[�w�Z�ł��A�����o�[�����w������w��������ɍ��i������i�j��������Ǝv�����A�������Q�����B�Q���ł��̑����ł���B
�����ƁA�����Q���ɍ��i����ƌ������́A�g���̒N�����i�@�����Ɏ����悤�Ȃ��̂�������Ȃ��B
�����i�ݐ���オ��ƁA�����Q���̍��i�j���͖Y����A���T�̂P���Ɍ������A��v���b�V���[���ւƕϐg���čs���̂������B
�@�@�@�@�P���O�����ʍu�K�a�x�Z���������}�[����
��������Ăѕs���Ƃ̐킢���n�܂�B
�����ĂP�T�ԁA�R���P�U������O���̎��������B���̃p�g���[�����I���X�L�[�w�Z�֖߂������ɁA
�@�Z���u�m�A�����͌��肾���牴�Ɛ������b�X�����Ă��B�ߑO�͐��A�ߌ�͉����B�v
�@�m�@�u���肪�Ƃ��������܂��B�v
�P�O���ɂȂ�A�킽���̓}�[����ƃ��t�g�ɏ�����B
�Ȃɂ���A���̂Q�l���}���c�[�}���ŋ����Ă����̂�����A�撣��Ȃ���B
�@���@�u�m�A�ߑO���̓t�����X�̊������邩��B�v
�m�@�u�͂��A���肢���܂��B�v
���E���̊e���ɂ́A���ꂼ��������������X�L�[���\�b�h������A�X�L�[�𗝉����鎞�ɖ𗧂B���E���̃X�L�[���t���W�܂�A�e���̃X�L�[���\�b�h�\����C���^�[�X�L�[�Ƃ����̂������A���̔N���J�ÔN��������������Ȃ��B�悭�X�L�[�w�Z�ł́A���̃r�f�I�����Ă����B
���̓J�i�_�̊��肪�D���ŁA�ڂɏĂ��t���^�����Ă����悤�Ɏv���B
�X�L�[�̓X�L�[�B�ǂ�Ȏ����������S�Ɋm���Ɋ���~��čs���Ηǂ��̂����A�ڂ̑O�Ŏw�������狳��������̊��������Ԃ����悤�Ɏv���Ă���B
�}�[����̌��������ȒP�ɍČ��ł���킯�ł͂Ȃ����A���������^�����Ċ���̂������B�����āA�������Ɠ�����������B
�ߌ�ɂȂ�Z���ƃ��t�g�ɏ��B
�@�Z���u�m�A�ߌ�̓h�C�c�̊���ɂ��悤�B�v
�@�m�@�u�͂��v
���x���������Ǝv�����A�X�L�[���t�B�͍����̐l�ɂǂ̂悤�ȉۑ��^����Ƃǂ̂悤�Ȍ��ʂɂȂ�̂����킩���Ă���B���̂Ƃ��̍Z���ƃ}�[����������������Ǝv���B�Ȃɂ����l������ő�܂��߂ɋ����Ă����̂�����A���͂ǂ���̃X�L�[���}�X�^�[��������̂������A����Ȃ��Ȃ����B
���܂ł���Ă��������t�����X��h�C�c�̂ق��������̂��ȁH�ȂǂƎv���n�߂�̂��B
�F����Ɍ��������̂́A�X�L�[�̓X�L�[�B���낢��ȋZ�p���g���A���낢��ȏ����鎖���ڕW�Ȃ̂��B������x��肭�Ȃ�Α����̊��o�����ނ��߂ɂ��A���낢��Ȋ���ɒ��킵�Ă��������̂��B
���̓��Q�l���A���Ɉ�ԋ������������̂͂��̂��Ƃ��Ǝv���B
�����ĂR���R�O���A�}�[������������ăQ�����f�̒[�ŁB
�@�Z���u�m�A���Ƃ����������H�v
�m�@�u�����͂��߂܂���������K���܂��B�t�����X�ƃh�C�c�̂ǂ��炪������ł����H�v�@
��l����������킹�ď����E�E�E����ȗ\��������B
�@�Z���u�m�A������������͍��̌N�ɂ܂������W�Ȃ�����S���Y��Ȃ����B�v
�m�@�u�E�E�E���肪�Ƃ��������܂����H�v
�����āA��l�͒����Q�����f�̂悤�Ɋ���~��Ă������̂������B
���̌�p�����߂鎄�̓��̒��́E�E�E�^�����ɂȂ����B
�@�ŏI�p�g���[�����I�������́A�����ɔ������K���邽�߁A�Q�ĂăX�L�[�w�Z���o�悤�Ƃ����B
�@�Z���u�m�A�d�����I��������t��邩��A��ł��p�ӂ��Ƃ��Ă���B�v
�@�m�@�u�ł��A�����͌��肾�����K���Ȃ��ƁB�v
�@�Z���u���܂������Ă����ʂ�����A���C�ł������Ă�����肵��B�v
�@�m�@�u�ł��E�E�E�v
�@�Z���u��������A��B�����̓X�L�[������_�����B�v
�@�m�@�u�͂��A����Ɏ��炵�܂��B�v�����āA�����ɖ߂��̗p�ӂ����ĊF���d�����I����̂�҂����B�����̂悤�Ɏ����݂��n�܂�B
�@�m�@�u�}�[����A�ǂ����ăt�����X��������ł����H�v
�@���@�u�Z�����A�t�����X�ɂ�����Č������炳�B�v
�@�m�@�u�ǂ����ăh�C�c��������ł����H�v
�@�Z���u�ʂɈӖ��͂Ȃ���B�v
�@�m�@�u��������A�X�e�b�v�^�[���̂ق����ǂ�������Ȃ��ł����H�v
�Z���u�o�J�A�X�e�b�v�^�[�����ւ���������Ȃ���A�����͎����̊������������́B�����X�e�b�v�^�[���̎��ɐm���h�C�c�̊�������Ă��A��肩�����獇�i�����B�v
�m���ɁA����͊F����ɂƂ��đ傫�ȖڕW��������Ȃ��B�������A���܂�ɂ���ڂɂ�����肷������K�͗ǂ��Ȃ��B���ꂼ��̎�ڂ������ڂŔ��f����̂ł͂Ȃ��A���x���J��Ԃ����������g�̊��o�Ƃ��ė������鎖����Ȃ̂��B
���ɂ������鎞�A��Ō`�𐮂���̂����A���т��Ȃ�����ɂ���͍��Ȃ��B���̂��т������̊��o���Ǝv���悢�B��Ɍ`����낤�Ƃ��Ă��A��肭�s���͂����Ȃ��̂��B
�����̊��o���o���Ă���A�`�𐮂��čs�����B
���ԁA�^�����ɂȂ����������A���̂��Ƃ����������ł����悤�Ɏv���B�������A
�����͂P���̌��肾�I�قƂ�ǖ��ꂸ�ɒ����}���邱�ƂɂȂ����B
�@�@�@�@�o�b�W�e�X�g�ƐS�\���I
�R���P�V���A��T�Ɠ����悤�ɒ��̎d�����I���X�L�[�w�Z�֖߂�ƁA��T�Ƃ͈Ⴄ�Z�[�^�[���p�ӂ���Ă����B
�X�L�[���t�B�͌�y��k�̏�B�������̎��̂悤�Ɋ�ԁB
���J��搶�͂T�O���Ă������A����������B���Ă���̂�����ƁA�u�Y�������A������B�v(�W���ƌ��������������Ȃ�j�ƌ����āA�{���Ɋ��������Ȋ�ŏ��Ă��ꂽ�B
�@���Č�����͍Z������C�ɒ��J�삳��ƍ����@�N������A�E�F�[�f�����̗��K�œo�ꂵ���B�{�Ԃ̓��e�́A�Q���̎��Ɠ����ł��܂�o���Ă��Ȃ��B���i����Ă���悤�Ɋ������������B
�o�b�W�e�X�g��ڎw�����Ɍ��������̂́A�Ƃɂ���������͍l�����A�����Ɠ��������S�����鎖�B�O���Ɍ���̃|�C���g���������悤�Ȗ{��ǂ݁A�{�ԂŋC�ɂ��Ă����ʂȎ����B
���̕��͋C�̒��ŁA���������ď�ɍl���Ȃ��犊��Ȃ�ďo����킯���Ȃ��B�������ꂪ�ł����Ƃ��Ă��A���Ȃ��̋r�͈�x�����߂��ꂽ���̂Ȃ��������A���̎��������Ă����킯���Ȃ��B���x�����x�����߂��Ă��̓�����̂Ɋo�����܂��āA���߂ďo����悤�ɂȂ�̂�����B
���Ȃ��̐ςݏd�˂Ă������̂�����Ɍ����A����ȉ��ł�����ȏ�ł��Ȃ��B���܂��܃[�b�P���P�Ԃ̐l������I������Ƃ��ɑ�Ⴊ�~��n�߂��B�������̌�Ɋ���l���S���s���i�������Ƃ��Ă��A�P�Ԃ̐l�͉^���ǂ������킯�ł��Ȃ�ł��Ȃ��B
�����Ă������낤�A�X�L�[�͐Ⴊ�Ȃ���ł��Ȃ��̂�����B
����������Ƃ���A�s���i�������l�B�͂��܂�ɂ�����ɂ������A����Ɏg����Ǝv����ΖʂŁA����p�̊��������K���Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B
���x�������悤�ɂ��ꂼ��̎�ڂ��A�`�����^���Ă��_�����B
���Ȃ��̊��o�ŗ������A�\�����Ȃ���B�������g�̊��o���������肵�Ă���A�Ⴊ�~�낤���W�͂Ȃ��B����Ȃ̂Ɍ���p�̖{��ǂ݁A���̂Ƃ��芊�낤�Ƃ��肷��B�ǂ��l���Ăق����A���̂悤�Ȗ{�������̂͏�肢�l�Ȃ̂ł���B�@
�@���̐l�̌��t�𗝉�����ɂ́A���̐l�̃��x���ɒB���Ă���łȂ���Ώo����킯���Ȃ��ł͂Ȃ����B�����炱���A���̂��Ȃ��̊��o�ŗ������鎖����ԑ�Ȃ̂��B
�@
�@�@�@�@�ςݏd�˂Ă������̂��������Ȃ���I
���ɂ��Q�l�̎q�������邪�A�q���ɕ�����������Ƃ��悤�B�ނ�̓y���̎���������m��Ȃ��̂�����A�����ȂǏ�����킯���Ȃ��B�������A�e���m��Ȃ������Ƀy�������悤�ɂȂ�B�����A�����Ől�̐^�������āA�y���������o�����ނ̂��B�����Ď��R�ɓ�������悤�ɂȂ�B
�����܂ł���Ε�������������B�X�L�[�����ē��������B�X�L�[���t�ɏo���鎖�́A���Ȃ������Ȃ����g�̊��o�����ނ��߂ɒm�b���o�����ƂȂ̂��B���������āA���Ȃ����g�̊��o�Ƃ��Ă��܂��鎖�̏o���Ȃ��X�L�[���t�Ȃǎ��i�Ȃ̂��B
�ʂ����ăX�L�[�w�Z�ɓ���l�B�́A�����Łu�����A����͍��܂łƈႤ�I��ƌ������o�Ă���̂��낤���H�X�L�[���t�Ɂu�͂��A����ł����ł��B�v�ƌ�����ƁA����ł����Ǝv���Ă���̂ł͂Ȃ����낤���H
���̎��A��������肭�Ȃ��������������Ă���̂��낤���H
���������������Ă��Ȃ��̂ɔ[�����Ă͂����Ȃ��B�����������ăX�L�[�w�Z�ɓ���̂�����A�������o���ċA��Ȃ�������Ȃ��B
���̉����Ƃ́H�@�������g�̊��o�Ƃ��Ă��ގ��Ȃ̂��B
���ɂ́A�u��肭�Ȃ����Ǝv����u�Ԃ��A���x���������B�v����͌���p�̊��肪�o�������ł͂Ȃ��A�V���]���ɍ~���ꂽ���ȂǂɊ������B����]������ԂɎ����̂悢�Ǝv�����o���A���x���A�����ďo�������Ɋ������肵���B�������ď����������̊��o�����߂čs���̂��B
���肾���ē������A�����������Ď���̂�����A������̂��@�����f���K�v�ȂǂȂ��B����̊���������Ă��B�v�ʂ̋C�����Ŏ�Ηǂ��A����̃|�C���g�Ƃ����悤�ȍׂ��������l����K�v�ȂǂȂ��B
�Ȃɂ��둊��̓v���Ȃ̂�����A���Ȃ��̊���f����͂��\���Ɏ����Ă���B
���x�������悤�ɁA���Ȃ����ςݏd�˂Ă������̂����A������ɂ͌����Ȃ��̂ł���B
�@�@�@�@����������Ă���肭�Ȃ�Ȃ���I
�����܂ł̓��e����z�������Ǝv�����A���͂��̓��P���ɍ��i����B
����́A���K�����Ď������ʂł���A�t�Ɍb�܂�A���Ɍb�܂ꂽ���ʂȂ̂��B�����������A���̊��ɓ��荞�ގ������Ȃ�������ǂ����낤�H�Ԉ���������̎d�������Ă�����ǂ����낤�H
�������R�����łP���Ȃǎ���͂����Ȃ��B
���Ȃ��͎d���������A�x�݂𗘗p���ăX�L�[�ɍs���B��邩��ɂ͏�肭�Ȃ肽���A�o�b�W�e�X�g�ɂ����i�������B�P�������l���e�N�j�J������肽���Ǝv���͓̂��R�̎����B
����Ȃ̂ɁA���Ȃ��́u�x�݂����Ȃ��āv�Ƃ��u���̃X�L�[���t�̌��������킩��Ȃ��v�Ȃǂƌ����ĂȂ����낤���H�����ł͉����l�����A�X�L�[���t�̌����������̂܂ܗ������悤�Ƃ���E�E�E�B
���Ȃ��̊��o�͉����ɂ���́H�������Ȃ��̒��ɂ���̂��B�����̓����g���������g�̊��o�ŗ������悤�A����������Ă������ς��Ȃ��̂��B�ǂ�ȂɃX�L�[���o���鎞�Ԃ��Z���Ă��A�R�N������P���͎���̂ł���B
�����A���Ȃ������̊ԉ����l���A�ǂ̂悤�ɗ��K���邩���Ԉ��Ȃ���I�@���̕ӂŘb��߂����B
��̂��Ƃ��u�P�_������v�Ȃǂƌ����Ȃ���A���i���\�̎��ԂɂȂ�B���̂Ƃ��̎��́A���i�A�s���i�ɑ��ĕs���ȂǂȂ��Ȃ��Ă����B�����̂����̊��肪�]�������̂��A�_���Ȃ��̂̓_���A�������̂͂����̂�����B
�X�L�[�w�Z�̑O�ɒ���o����鐬�ѕ\���A���̎҂ƂƂ��Ɍ��鎖���o�����B�R�U�O�_�P�O�_�I�[�o�[�̍��i�ł������B���ɂP����������B����ƒ��ԓ��肪�o�����B�X�L�[���t�ɂȂ邽�߂̃X�^�[�g���C���ɗ������̂ł���B
�̂̑ٓ��X�L�[�w�Z�ł͂P���̍��i�j���ɁA���i�҂͑�Q�Q�����f�̒����~����炳�ꂽ�炵���B(�X�L�[�w�Z�W�҂����j
�����́A�}�ΖʂɃR�u�����тȂ��Ȃ��苭���B����l�͌��肪�I��荇�i����ɂ������̓��A�������炳�ꍜ�܁A�����Ȃ�P���ɍ��i�������ɕa�@����ɂȂ��Ă��܂����炵���B
�{���ɃX�L�[���t�B�̓C�^�Y���D���ł���B
���̎��́A���i����F���y���߂�悤�Ȏ�����炳��Ă����̂ŁA����͖Ə����ꂽ�悤���B
�@���̓����܂���T�ɑ����A�F�����������A���i�j���Ƃ����ẮE�E�E���ݑ�����̂ł������B
�@�@�@�@�ЂƂЂƂ����g���Ď����̕��ɂ��悤�I
���ꂩ���B��ڎw������X�L�[���͂��߂悤�Ǝv�����Ɍ��������B���낢��Ȏ�����x�ɂ�낤�Ƃ��Ă��_�����B
�Ⴆ�A�����ăX�b�g�b�N�����āA�G�b�W���O���ĂȂǂƂ����Ă��o���Ȃ��ē�����O���B
���x�����x���J��Ԃ����A�X�L�[���t�͂��Ȃ��ɍ���ԕK�v�Ǝv���鎖���Ă���B���������āA����ꂽ�������ɏW����������B
�u�G���܂���v�ƌ�����ΕG���Ȃ��鎖�������l���A�G�ɖ��߂���B
���̖��߂͂P�x��Q�x�ŕG���o������̂ł͂Ȃ��A���x�����߂��Ďv���ǂ��蓮���悤�ɂȂ�A�Y��Ă����B�����āA���̎����o�����܂��čs���B
���̂��ƌ����Ύ��̂悤�ɖ�������҂ł��A�P�x�ɂ��낢��o����悤�ɂȂ�Ȃ��̂ɁA�T�ɂP�x��������Ȃ��l������ȏ�̂��Ƃ��l���Ă��A������̂��Ȃ��������Ȃ邾�����B
���������낤�Ƃ��Ă��o���Ȃ��̂�������O�Ȃ̂�����A�����Ƃ����ƊȒP�ɍl���悤�B�X�L�[����肭�Ȃ�Ȃ��̂́A�����̊��o�Ƃ��ĂƂ炦�鎖���o���Ȃ������̎��A�����Ɠ����g�����B
�@�����g���ƌ����Ă��A�V���e���^�[���͐؊����ŎR�X�L�[���͂̎��ɊJ���āA�����ĉ��A�Ƃ��������o����̂ł͂Ȃ��A���o�Ƃ��Ă��ނ̂��B
���Ȃ��ɂƂ��Ă̓q���C�q���C��������Ȃ��A���ɂ̓O�j���[�ƊJ���ă|�[���ƌ����������낤���B
�@�O�ɂ����������A�֎悪�����Ă���̂������\������A�u�h�[�v�ƂȂ邪�A�ނɌ��킹��Ɓu�L�[���v�������肷��A��l��l���o�͈Ⴄ�͂����B
�@�����炱���A�F����̊��o���ɂ��Ăق����B�����̊��o�Ƃ��ė����ł���܂ŁA���x���������K�𑱂��Ă������������I
�@�@�@�@�N�����ė��K����Ύw�����ɂȂ���I
���āA�������Ď��̍ŏ��̃V�[�Y���͏I�����}����B
�����͎Q�l�ɂȂ������낤���H�܂��܂��w�����ւ̓��͒����B���������S�N�ƌ����邯��ǁA���̂Ƃ��̎��ɂ́A�܂����w�������牓�����E�������B
�����X�L�[�������ƌ������A���ʂ��ƌ����Ă͎�������ł����B
�u�m�����N�A������N�l�q�����ď��w�������ȁB�v
�Z�����|�c���ƌ������B
�Ђ�Ƃ���ƁA�����w�����ɂȂ�邩������Ȃ��H�Ɠ��S�v�����B
�Q�����P�������ׂāA�Z���̌����Ƃ��荇�i�ł����̂�����B
�@�Ō�̒��A���B�͉ו����Ԃɐςݍ��݁A�����b�ɂȂ����l�B�Ɉ��A���I�����B���t�g�̕������B�̓��C���[���烊�t�g�����O����Ƃ��n�߂Ă���A�Q�����f�̐�������A�Ƃ���ǂ��두�������n�߂Ă����B
�o���̎��Ԃ��B
���͏�������̃X�C�b�`������ƁA�u�p�g���[���ł��B�F���낢�날�肪�Ƃ��������܂����B�܂��A���V�[�Y���K���A���Ă��܂��B�T���E�i���B�v�ƃ}�C�N�Ɍ��������B
�����ĎԂɏ�肱�ނƁA��������������������H���A���Ɍ����đ����čs���̂������B�i1986�A4�j
�@�@
�@�@
�@
�@�@�@��3���@�@�@���w�����ւ̓�
�P�X�W5�N�P�Q���A�Q�Q�ƂW�����B�@���ɂƂ��ăX�L�[��ʼn߂����Q�V�[�Y���ڂ��K�ꂽ�B���̔N���܂��Ă͎R�ʼn߂��������A�Ƃɂ��������~���҂��ʂ��������B
���āA��V�[�Y���P���ɍ��i�������́A�{���̈Ӗ��ł̏�B�͂��̔N����n�܂�B�قƂ�Ǔ]�Ԏ����Ȃ��A�ǂ̂悤�ȎΖʂł�����~��čs����悤�ɂȂ�A�������玩���̊���ɓ��t�������Đ��������čs���i�K�Ȃ̂��B
�P���̏�ɂ̓e�N�j�J���v���C�Y�A�N���E���v���C�Y�Ƃ����ŏド���N�̃o�b�W�e�X�g������B
����ɑ����w�����A�w�����Ƃ����̂́A�X�L�[���t�Ƃ��ē������߂̎��i�ŁA�w�����@�Ȃǂ��w��ōs�����ɂȂ�B���w�����A�w�����������Ȃ���A�e�N�j�J����N���E������l������悤���B
�X�L�[���t�͓��R�A���k����ɗ������₷���悤�Ɋ����Č�����́A���Z�͂�w���͂��K�v���B
���B�̂悤�Ɏw������ڎw���҂́A����Ȃ�̊������v�������B
�X�L�[�w�Z�Ŏd��������l�������A���X�X�L�[�ɑ���l������A������ɏ�肢�ƌ��߂邩�Ȃǂ�@�����܂�čs���B�������A�N���E����e�N�j�J����ڎw���l�B�͋x�݂𗘗p���ė��K������������A���̎��𗝉����ɂ����s���i���J��Ԃ����������Ǝv���B
���̃��x���ɂȂ�ƃX�L�[�G���Ȃǂ�ǂ݁A��ϕ����Ă�����������B
�������A�ǂ�قǕ����Č��t����ׂĂ��_���Ȏ��͉��x���\���グ�Ă���B�@�@�@�@
���Ȃ́A�u�X�L�[�̊J������ǂ��̣�u�O���X���ǂ��́v�ƌ�����ƁA�u������͗ǂ��킩��Ȃ��v�ƌ��������Ȃ�B�v����Ɏ����̊��o�Ƃ��Ă���ł���Ηǂ��̂ł����āA���̈�ԑ�ȕ��������Ă��Ă͏�肭�Ȃ�͂����Ȃ��B
�u�^�[���̌㔼�ɂ�������ƃX�L�[�ɏ���āv�Ƃ����Ă��A�ǂ�����X�L�[�ɏ���̂����킩��Ȃ���A�����o���Ȃ��B
������Ă��s���i�ɂȂ�l�́A�����ł̓X�L�[�ɂ����������Ă������ł��A���ʂ͏��Ă��Ȃ����߂ɕs���i�Ȃ̂��B���̂��Ƃ𗝉��ł��Ȃ��l�́A�u�R��]�ڂɃX�L�[������Ă��܂�������v�Ȃǂƌ����̂ł͂Ȃ����낤���B
���ꂩ��P����e�N�j�J���A�N���E����ڎw���l�́A�����ł������l������ς��悤�B�����ƍ������x���Ŏ����̊��o���čs�����B
���̂܂܊����Ă���Γ]�Ԏ����Ȃ��ǂ�ȎΖʂł��~��čs����A����ȏ㋉�ҒB�������ɂȂ��V�������o��g�ɂ��悤�ƍ��ȏ�̂��Ƃ�����Βɂ��v��������B����ł��X�L�[�͗����ł͂Ȃ��A�����̊��o���グ�čs�������Ȃ��B
���̍��̎��̓X�s�[�h�ƃo�����X�����߂鎖�����l���Ă��Ȃ������B�Q�O�ŏ��߂ăX�L�[�𗚂����l�Ԃ��A�q���̍����犈�A�f�����X�g���[�^�[�ɂȂ����胏�[���h�J�b�v�ɂł��肷��l�B�ɒǂ������͕s�\���낤�B
�������A��B��ڎw���Ȃ班���ł��߂Â��Ȃ���E�E�E���̎v�������͖Y��Ă͂����Ȃ��B
���͂��̍������̌��E�X�s�[�h���グ�邱�ƂƁA�����̈����Ƃ�������邱�Ƃ�����H�����B���E�X�s�[�h������������ƁA���̃X�s�[�h�������Ȃ�Ȃ���ɂ��v��������B
���ꂽ���͒����Q�����f�Œ����~�����Ȃ���A�r���ŕБ����グ�Ă݂��肷��̂������B
�@�@�@�@���������������悤
�X�s�[�h�ƂƂ��ɁA�o�����X��{�����ߏ����̈����Ƃ�������낤�B��̍~�������̓��ɂ́A�K���`�������W�R�[�X�֍s�����B
�i�D���Z�p���W�Ȃ��A�]���ɍ~��鎖�������l����B
�[��̓X�L�[���͂̎��ɂ��Ă��Ă͊���Ȃ�����A�o������肻�낦�鎖���l����悤�ɂȂ�B�ł��A�s�b�^�����낦��K�v���Ȃ����������Ă���B
�Ȃ��Ȃ���肭�X�L�[�����Ȃ�����A�������g�b�v������������Ă܂킻���Ƃ���B�O�ɏ������A���ɏ�����肷��̂ŁA�����p���p���ɂȂ��Ă��邵�A�O�ɏ�肷����ƃg�b�v������ŁA�炩��˂����ނ��ƂɂȂ�B
���̂��Ƃ������ŗ����ł���A���̒i�K�ɐi�߂�B�O�ɏ���Ă���ρA���ɏ��Δ��Ă��܂��A�u�������A�^���ɂ̂�����̂��v
�o�������^���ɏ�낤�Ƃ���Ȃ�A���i�̊���Ɖ����ς��Ȃ��ł͂Ȃ����B��������^���ɏ���킯�ł͂Ȃ��B�������A���܂܂Ő��n���ꂽ�ΖʂƂ͈Ⴄ�Ǝv���Ă������A�������o�Ƃ��ė����ł���悤�ɂȂ�B
���Ȃ��̊��o���A�b�v����A�ǂ�ȎΖʂ��������o�Ŋ����悤�ɂȂ�B�������ē������o�Ŋ����悤�ɂȂ�ƁA�܂��܂��X�L�[�͊ȒP�ɂȂ�Ȃ����낤���H�@�@
���̍��̎��́A���q�����t�g���畨�𗎂Ƃ��̂��������āA�N���������E���ɍs�����B��܂�X�q�Ȃǂ͊ȒP�ŁA���ʂɂ��ׂ�����B�������A���܂ɃX�L�[�𗎂Ƃ��l�������B
����͏�����������ŁA�V����X�L�[�������Ȃ��犊��̂�����A�Ȃ��Ȃ��苭���B�]�ׂ��t�g����������������A��ϒp���������B���K���邵���Ȃ��I
�`�������W�R�[�X�փX�R�b�v�������čs���A�]���ɍ~��čs����������v�B���łɕБ��̃X�L�[���͂����Ă���Ă݂邪�A�܂������o�����ɂ�����߂��B
�F����ɓ`�������̂́A��肭�Ȃ�����u�R�u�Ζʂ����낤��Ƃ��u�V������낤�v�ȂǂƎv���Ă��Ă��A������肭�Ȃ��Ă����֍s���ƕK���]�Ԃƌ��������B����Ȃ班���ł����������čs�����B
�����āA�����ł��������炻�̊��o������ł��܂����B�悭�A����Ȃ��̂ɏ㋉�R�[�X�֓���A������߂ĕ����č~���l�����邪�A����͐�ɂ���Ă͂����Ȃ��B
����Ȃ��̂ɏ㋉�R�[�X�֍s���̂������Ȃ��ƌ����Ă���̂ł͂Ȃ��A�����č~��鎖�������Ȃ��ƌ����Ă���̂��B
���Ȃ��̓X�L�[��Ɋ��邽�߂ɗ����̂��B
�X�L�[��ɕ������߂ɗ����̂ł͂Ȃ����낤�B���Ƃ͒��킠��̂݁A�ǂ����Ă��|��������A���߂ĕБ������ł��X�L�[�͒����Ă������A����ł������̓G�b�W�̎g����������͂����B
�X�s�[�h�ƃo�����X�A���̓�������������B�����āA�����ł͂��邪�A��{�I�ȑ���A�v���[�N�{�[�Q���Ȃǂ����K���čs�����B
�s�v�c�Ȃ��̂ŁA���Ȃ��̌��E�X�s�[�h�������炩�オ���Ă���ƁA���܂ŏo���Ȃ����������ȒP�ɏo�����肷�邵�A�����Ă�����Ȃ����������ȒP�ɂ킩�����肷��B�m���ɐV�������o���A���Ȃ��̒��ɐ��܂�Ă���̂��B
�@�����ɂP�������A���w�����Ɍ����ė��K������X�A�Ƃɂ������낢��Ȏ���������B��y�B�͂��낢��ȗ��K���@��m���Ă���A�Ƃɂ������ł�����Ă݂悤�B���ɂ́A�ƂĂ����K�Ƃ͎v���Ȃ����̂����邩������Ȃ����H
�@�@�@�@���K���@
���āA���K�@�����A�������o���鎞�ɂ͏�̂Ƌr�̋t�Ђ˂���ӎ����邽�ߋ}��������K������A�͂̎��ʼn�銴�o�����ނ��߂ɁA�G����������肷��Ȃǂ��낢�낾�B
���ȏ������邵�A�X�L�[���t�B�����Ȃ��ɕK�v�ȗ��K���@���A�h�o�C�X���Ă���邾�낤�B���R��X�̂������E�ł́A�Б��Ŋ�������ƌ������K�͂��邪�A��肭�Ȃ������x�o���Ă��܂�����܂�Ȃ��B
�����ŁA���������ɏo���āA����̐l���o���Ȃ����Ƃ��l����̂������B
�d�����Ȃ��F�Ŋ����Ă���Ƃ��ɁA��������Ƒ�ϖʔ������A�ǂ�ǂ�G�X�J���[�g����B
�����A�����ɂ����o���Ȃ�����������A��������ԏ�肢�̂�����Ǝv���A���낢��l����B�������A���̓��ɂ͍U������Ă��܂�����A�����Ƃ������Ȃ��Ƃ��l����B
�u�N�����������ŃV���e���^�[�������悤�v�ƌ����o���B�Ζʂ̏�������Ċ���Ȃ���R�J���̃V���e���^�[�����ł���ƁA���͒J�J���A�قƂ�ǂ݂�ȊȒP�ɂ���Ă��܂��B
����ƁA�X�L�[�ɂ���A�J�J�g������̑O�ɂ���ܐ�Ō��݂��݁A����n�߂�B���R�X�L�[�͂�������Œ肳��Ȃ�����A�r���ŊO��ē]�ԁA�]�ׂΊF������B
�����ĉ��������o�����Ǝv���A�u�X�L�[���͂����̂́A�^���ɏ���Ă��Ȃ����炾�B�v�ƂȂ�B�����܂ł���ƈӒn�ɂȂ�A�Â��Ȃ��Ďg��Ȃ��X�L�[�������o�������J���Ȃ����A����ɂ����肷��B�Ō�͂ǂ��Ȃ邩�Ƃ����ƁA�u�X�L�[�̐^���Ƃ́v�ƌ����b�ɂȂ�A������͂������X�L�[�ɂ�����邾���Ŋ���n�߂�E�E�E�o����킯���Ȃ��B
���x�������Ă������A�o���Ȃ������o����悤�ɂ��邽�ߗ��K����̂����A�����܂łƂ���Ɨ��K�Ƃ͌����Ȃ���������Ȃ��H�@����ł��A���X�Ƃ�����ŕK���ōl�����肷��B
���̂����W�����v������A�L�g������]�Ȃǂƌ����o���n�����B
�t���[�X�^�C���X�L�[�ł͂Ȃ�����ǁA�Q���[�g���̃X�L�[�ŗ��K����B�T���O���X�͉������邵�A�痎���đ��͏o���Ȃ����A��ϒɂ��v�����������A����Ȓ��q�ŏW�܂�Ƃ킢�킢����Ă����B
�o�J�Ȏ���������Ȃ����A����Ȃ��Ƃ𑱂��邤���ɁA�X�L�[�̐^���ɏ���Ă���悤�ɂȂ�B�ς�����������悤�Ǝv���A���ł��X�L�[�𑀍�o���鏊�A�܂��ԑ��삵�₷���Ƃ���ɏ���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�Ⴄ�Ƃ���ɏ���Ă����̂ł͂ł��Ȃ��̂��B
�������A����ȃo�J�Ȏ������Ȃ���A�����Ƃ���ɏ���悤�ɂȂ�Ƃ�����A���ꂪ��ԑ�ȗ��K��������Ȃ��B������Ȃ���g�ɂ��̂�����A�o�J�Ȏ��Ǝv�킸�A�q���̂悤�Ɋy����ł݂�̂��悢���낤�A�ĊO�o�J�ɂ������̂ł��Ȃ��Ǝv���B
�@�@�@�@
�@�@�@���܂ˑ���I
���̍��y���݂Ȃ���͂����Ă����̂��A���܂˂Ɣ�Ԏ��������B�J�b�R�Ȃǂǂ��ł��ǂ��A�Ƃɂ�����Ԃ̂��B�F����͑��̃X�L�[���[�����āA�댯������̂ŗǂ����ӂ��āA�o���鎞�ɂ���Ă݂悤�B
���ł��ʔ��������̂��A�W�����v�̐^�����B
�e���r�ł����������͂Ȃ����A���[�W�q���Ƃ��X���[���q���Ƃ���������B���̎��̓W�����v�̑I��ɂȂ肫�낤�B��яo������X�L�[���u���ɂ��āA���n���鎞�́A�X�L�[��O��ɊJ�������傫���J���B�o����A�~�܂����炷���ɃX�L�[���͂����A�I��B���J�����Ɍ������X�L�[�̃f�U�C����������悤�ȂƂ���܂Ő^�����悤�B
�������Ȏ��Ǝv���邩������Ȃ����A���낢��Ȑl���ώ@���^���鎖�ŁA���܂łƈ�������o���g�ɂ��B�Ⴆ�A��̍\����ς��邾���ō��܂ł̎����̃o�����X�͊m���ɕ���Ă��܂��A��U���ɕς���Ɖ��Ȃ��Ȃ����肷�邩��ʔ����̂��B
���낢��Ȑl�̓�����^����Ǝ����͊���ɂ����Ďd���Ȃ��̂ɁA���̐l�͏�肭�����Ă���B���o�͐l���ꂼ��Ȃ̂��B
�u����ȕ��Ɋ����Ă݂Ȃ����v�ƌ���ꂽ���A�������̎����o�Ŋ���ƁA���肩�猩�ĉ����ς���Ă��Ȃ��B����ł́A��肭�Ȃ��Ă��Ȃ��A�o���Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B�܂��āA�w���҂�ڎw���Ȃ�A���̐��k���������₷������������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���i����A���낢��Ȑl�̐^�������Ď����̊��o�Ƃ̈Ⴂ���m���߂悤�B
���܂˂́A�{�l�̑O�ł�������B
�u���́A����ȃJ�b�R�Ŋ����ĂȂ��棂ƌ���ꂽ�畷���Ă݂�A�u�ǂ�Ȋ����Ŋ����Ă���̂ł����H��@��������ƁA�����̊��o��������Ă����B
�@����������̊��o�ɂ��������A���낢��ȏ��������Ă݂悤�A���̂����ɉ����āA�ǂ�����Έ�Ԉ��肵�Ċ���邩���킩���Ă���B
�@�@�@�@
�͂��߂Ď����̂��ׂ��������I
�����֗��ĂQ�V�[�Y���ځA���͏��߂Ď����̊�������鎖�ɂȂ����B
�搶���́A���܂Ƀr�f�I���B���Ă̓X�L�[�w�Z�Ō��Ă������A�ŏ��̔N�A���͂��̂悤�ȂƂ���ɓ����čs�����Ƃ��o���Ȃ������B
�����Q�����f�̒[�Ɉ�{���t�g���������Ă��āA�y���̐l���������������B���t�g�̒�~�ɔ������t�g�̎x�������Ɉ���Ԉ�䕪�����}�Ζʂ����������̂������B
�������ɂ̓��t�g�̎x��������댯�����炨�q����͊���Ȃ��B
�����ł�����j���̗[���r�f�I���B���Ă����B
���̓Z�C�{�E�Ə��ɒʂ肩�������̂Ŋ��点�Ă�������B���S���قǂ����Ȃ��̂œ��R�����Ŋ���B��{����Ǝd���ɖ߂����B
�ŏI�p�g���[�����I���X�L�[�w�Z�ɍs���ƊF�Ńr�f�I�����Ă���B
���������̊�����������z�́A�m���ɃJ�b�R�͈������Ǐ\���ɏ�肢�Ǝv��ꂽ�B�����Ă���Œ��̓o�^�o�^���đS�R�_���Ȋ�������������ǁA���ۂɂ͂�����Ɗ���~��Ă���B�����Ďv�킸
�@�m�@�u�����āA���\��肢��ł��ˁv�ƃ}�[����Ɍ������B�����
�@���@�u������������m���X�L�[�w�Z�ň�ԏ�肢��������Ȃ��ȁA�J�b�R�������ǃ��t�g�̉��ł��ǂ��ł���ɓ]�Ȃ�����ȁv
���̍����́A�N�����Ȃ����ɂ͎����̌��E�X�s�[�h���グ�邽�߂ɁA�R�u�Ζʂ����͈ȏ�ɔ�����肵�ē]�Ԏ������傿�イ���������A�N��������Ƃ��ɂ͐�ɓ]�Ȃ��悤�ɂ��Ă����B
��������K���Ă���p�g���[���ł��A���t�g�̉��֍s���[��̒����X�L�[�������Ċ���Γ]�Ԏ����������A��܂Ȃǂł��]��ł��܂����Ƃ�����B
���������ď�肢�ƌ��߂邩�ƌ�������]�Ȃ����Ȃ�A�������ĂȂ��Ȃ���肢���ɂȂ�B
������̊�͂��̒ʂ肾��������A����ȂɊ��������͂Ȃ��B
���̎��A�}�[����⎄����肢�Ƃ����̂́A�����ĒN������肢�̂ł��Ȃ��A�P���̃��x���ɂ���̂ł��Ȃ��A�������R�Ə�肢�̂ł����āA�����ɂ͎w�������ǂ��̂����̂Ƃ������̂͑S���Ȃ��B
���Ɏ����̊���������̂͏��w�����ɍ��i�������̔N�������Ǝv���B���̎��͎����̃C���[�W����f���ƈႢ�����āA��x�Ǝ����̊���͌������Ȃ��Ǝv�����B
�܂��P���̂Ƃ��́A�������ǂ�Ȏp�Ŋ����Ă���̂��ƌ����C���[�W���N���ł͂Ȃ��������A��肭�Ȃ�ɏ]���A���ꂪ���̒��ɑN���ɕ����Ԃ悤�ɂȂ�B�����Ȃ�Ǝ����̊�������Ă������肷�鎖�ɂȂ�B
�����āA�w�����ɍ��i������Ɍ����Ƃ��́A�Ăя�肢�Ǝv����悤�ɂȂ��Ă����B�����̓��ɂ���C���[�W�Ɋm���ɋ߂Â��Ă����̂������B
���̎��A�����ł͑O�ɍs��������ɍs������A�X�g�b�N�̓X���[�Y�ɂłȂ����A�X�L�[�͊J������Ə�肭�s��������ł͂Ȃ������B
����Ȃ̂ɁA�B��ꂽ�f���͑傫�ȗ�����Ȃ��A�������v���Ă������́A�͂邩�ɗǂ����肾�����B
���̎��A�{���ɋC�������B�����̊��o�Ŋ���A�͍̂��܂ŗ��K���Ă������Ƃ��Č����Ă����ƌ������ƂɁE�E�E�B�����g���r�f�I�����Ĕ������Ǝv����̂�����A���Ō��Ă���l�ɂ�����������ɈႢ�Ȃ��B�����o�����܂������ʂ��A�����S�̂̎p�Ƃ��Č���ė���̂��B
�F����������炸�Ɉ���o���Ă����Ăق����B�@�@
�@�@�@�@��Ƃɂ����x�߁v
�@���̍��̎��̓���ƌ����A��N�Ɠ����Œ���ԂɃQ�����f�����ɍs���B
�������O���̗l�q���̏�Ԃ��画�f���āA�d�������Ȃ��悤�Ȃ璩��Ԃ͒����Q�����f��`�������W�R�[�X���B
�@�����A�p�g���[���͎d�����������R�Ɋ����Ă��肢���Ȃ��B�����炸���ƃX�R�b�v�������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ����������A�P���Ɉ�������Ԋ����Ƃ������̂ł��Ȃ��B12���ɖ߂�ƒ��H���ς܂�12��30���ɂ̓Q�����f�ɏo�āA�ŏI�p�g���[�����I���Η[�H�A�����ɗ��K�ƌ������X���B
�Z���͉�X�̕���(�㖱���j�Ɋ���o���ƁA�O�֏o�悤�Ƃ��鎄�Ɂu�m�A�Ƃɂ����x�߁v�ƌ����B���̓X�L�[�C��E���Ƌx�ރt�������邪�A���������Ԃ����Ƃ��Ă��Ȃ��Z��(���i�j���o�čs���ƁA�����ɗp�ӂ��ăQ�����f�Ɍ������B�@
�������̒��q������A�Z���͎��̊������Ɓu�Ƃɂ����x�ߣ��A�����鎖�ɂȂ�B
�����̎���1���ŁA�搶���Ɍ����鎖������o���Ȃ��āA�Ƃɂ������K���邵���Ȃ������B���낢��Ȏ�����炳��邯��ǁA�ǂ��������o���Ȃ�����1��24���Ԃƌ����̂͒Z�����邭�炢�������B
�������Șb�����A���w�����ɍ��i���ċA���Ă���ƁA����܂Łu�������A�������v�Ƌ����Ă���Ă������w�����̐搶���́A�ꏏ�Ɋ��鎖�������Ă��u�������A�������v�Ƃ͌����Ă���Ȃ��Ȃ�B�w�����ɍ��i���ċA���Ă���Ύw�����̐搶�����������B
�������A�܂�1�����������́A�ߑO���ɋ����Ă�����������o���Ȃ������ɁA�ߌ�ɂ͈Ⴄ�����w�E����Ă��܂��B�܂��A�����̊��o���������肵�Ă��Ȃ����A��肭�Ȃ��������O�������ɍl���o����悤�ɂȂ��킯���Ȃ��B�@
�Ƃɂ����K�v�Ȃ̂́A�킩��Ȃ�������������ŋ����Ă����搶�ł��A�X�L�[�����ł��Ȃ��B�����Ă�����������A�����̑̂Ɋo�����܂��鎞�Ԃ������B
���x�������Ă�������ǁA�ꎞ�Ԃ��Ԃ������Ă��炤�Ȃ��ŁA�ق�̐��b�̂��Ƃ�������Ȃ��B
�u����Ȋ������ȁH�v�Ǝv�����������x�����x���J��Ԃ������A�����悤�ɂȂ铹�͂Ȃ��B
�u�������āA�������āv�ƌ���ꂽ�ʂ�ɍČ��ł���ƌ����A�����Ƃ����Ə�肭�Ȃ��Ă���̘b���B
�܂�����ȗ͂̂Ȃ����ɁA�Z���́u�o�J�����[���肭���v�ƌ����A�C���C�����Ȃ���X�L�[�������A�x�݂Ȃ����葱���ĉ��Ă��܂�Ȃ����ƁA�S�z���Ȃ��猩����Ă��Ă��ꂽ�ɈႢ�Ȃ��B
����Ɏ�����肭�o�����ɔY��ł��鎖���������肨���ʂ��ŁA��������ł���Șb���肵�Ă��ꂽ�̂��낤�B�������Ŏ��́A�ǂ�Ȃɏo���Ȃ��ĉ������v�������Ă��A�����y�����߂������킯���B
�@�������X�L�[���B�u�y�������������Ȃ����v�ȂǂƁA���ł������ď����Ă����邪�A��l�ŏ�郊�t�g�̏�ʼn��x�܂𗬂��������낤�B
����Ă�����Ă��o���Ȃ��āA��y�X�L�[���t�̋����Ă���鎖���痝���ł����A�������v�������鎖�𐔂����炫�肪�Ȃ��B
�����炭���ł��A���̍���菭���܂��ɂȂ��������ŁA�S�����������B
�F����ɂ����邩������Ȃ��B
�u���ꂩ�ȁv�ƌ������̂������A���t�g�̏�Łu���������Ȃ����ȁv�ƃC���C���������B��������Ȃ��ƖY��Ă��܂���Ȃ����ƁA�v�����肷��B
�������A��J�̌��������́A��������Ă���肭�s���Ȃ����������B
���C�Ȃ������b�N�X�����C���Ŋ������Ƃ��ɁA��肭�s��������������A�K���ɋx�ގ����l���悤�B�@�@���܂�ɂ��꒼���ł͑�ς��I
�@�@�@�X�L�[���t�̓��b�X���Ŏ����̊��o�������Ă���
�F���猩��ƁA�C���X�g���N�^�[�͊F��肭�ăJ�b�R�C�C���낤�B�����悤�Ɍ����邩������Ȃ��B�������A��X����l��l�Ⴄ���o�������Ă���A���̎���ǂ��������Ăق����B
�O���⑀��������K����̂ł͂Ȃ��A�����̊��o�Ƃ̈Ⴂ�𗝉����āA�����̊��o�Ƃ��Ă��ނ̂��B���b�X���̒��Łu����͍��܂łƈႤ�v�ƌ������̂����߂���A���̊��o���Č����邾�����B
������������Ă��A���Ȃ��͎�ɗ͂���ꂽ���ɏ�肭�����Ɗ����Ă��A���̐l�͗͂������ɏ�肭�����Ɗ����邩������Ȃ��B�X�L�[���t�����Ă��āu���̊����������ł��v�ƌ��������̊��o�����Ȃ��ɂƂ��Ĉ�ԗ������₷�����́A���̐V�������o���ɂ��悤�B�ł͐V�������o�����Ȃ��ɂƂ��ĐS�n�悢���̂��ǂ����H
�X�L�[���t�́A���̂��Ȃ��Ɉ�ԑ�Ǝv���邱�Ƃ��Ă���B�����炭�V�������o��荡�܂ł̊��o�̂ق����A���Ȃ��ɂƂ��Ă͎��R������y���Ǝv���B�Ⴄ���o�Ŋ��낤�Ƃ�����܂łƈႤ�Ƃ���ɗ͂���ꂽ��A��ɓ��Ŗ��߂�����ő�ς��낤�B
�ł����v�I�@�@���Ȃ��͍��V�������o��m�鎖���o�����̂��B����قǒ������Ԃ��g��Ȃ��Ă��A���炭�̊ԑ̂ɖ��߂��鎖�ł��Ȃ��̑̂��o���Ă����B
�����Ȃ�ΖY��Ă��܂����B�܂��V�������o���o���čs�����B��肭�Ȃ肽����A����������̂ɖ��߂��悤�B
�ЂƂЂƂo�����܂��A�o�����疽�߂��͂����čs�����B
�@�@�@�@���J���Ɣ�
���܂ɂ́A�p�E�_�[�X�m�[�ɏo���킵�������Ȃ鎖������B
����Ȏ��́A��������Ă���肭�s�����A�ˑR��肭�Ȃ����悤�ȋC�ɂȂ�B���̂悤�ȏ�Ԃ͖�������킯�ł��Ȃ�����A�^�ǂ�����ȓ��ɓ���������A�x�ނ܂��Ȃ����葱���悤�B
�@�Ƃɂ����X�L�[���y�������B����Ȏ��ɗ��K�̂�̎����l���Ă͂����Ȃ��B�����ƁA�X�L�[�̐_�l�����Ȃ��̎������Ă��āA�撣���Ă��邩�炲�J�������ꂽ�ɈႢ�Ȃ��B
���J���̎��͔����҂��Ă���B
���낢��ȎΖʁA�Ꮏ����K���Ă����̂ɁA��������Ă���肭�s���Ȃ��������邯��ǁA�ʂɔߊς��鎖�͂Ȃ��B���܂��܁A���̎Ζʂɍ������o���������킹�Ă��Ȃ������������B
���̎��A�����͊���ɂ�������x�����Ȃǂƍl���Ă͂����Ȃ��B
�������Ă��銴�o�̒�����A��ԍ������̂�T�����B�������Ȃ������āA���x���o�����Ă���͂����B
�������钆�ŁA��x������肭�������Ƃ������o�E�E�E�����T���̂��B
��x�ł������炱�̊��o�����ނ̂��B���Ƃ́A����𑝂₵�čs���������B
�Q�x�A�R�x�Əo����悤�ɂȂ鍠�ɂ́A���܂Ŋ���Ȃ������Ζʂ����銴�o���g�ɂ��n�߂Ă���B
�����܂ł�����߂����̂��A��͑̂��o���Ă��܂��܂Ŋ��葱���悤�B
�@�@�@�@�o�b�W�e�X�g�͂ǂ���������̂��낤�H
�����Ō���ɂ��ď����Ă������B
���ꂼ��̋��ɂ���āA���낢��Ȏ�ڂ�������A���낢��Ȋ���̒�����A���̐l�̋Z�p�͂����邽�߂ō��i�A�s���i�����߂邽�߂ɂ͎d���̂Ȃ�����������Ȃ��B�������A���ꂼ��̎�ڂ��܂������ʂ̊�����ƍl���Ă͂����Ȃ��A�X�L�[�͂���Ȃɓ�����̂ł͂Ȃ��B
���Ȃ����A�������莩���̊��o�Ƃ��ĂƂ炦�Ă�������̂ł���B
�Ⴆ�Α�ϊɂ��ΖʂŃp�������^�[�������悤�Ƃ��Ă���肭�����Ȃ����A�t�ɋ}�Ζʂō����X�s�[�h�̒��A�v���[�N�{�[�Q�������悤�Ƃ��Ă����������B�Γx��X�s�[�h�̏����������āA���߂Ă��낢��Ȋ�������o����̂��B
�F����́A�ɂ��Ζʂœ]�ԐS�z���Ȃ�����A���K�����₷���Ǝv����������Ȃ��B�������A�X�s�[�h���Ȃ���Ύ����̑����ł�������ƃX�L�[���Ȃ�������Ȃ��A���������āA��������Ƃ����Z�p���v�������̂��B
�����A�P���̌�����قƂ�ǃX�s�[�h���łȂ��A�ɂ��Ζʂōs������ǂ��Ȃ邾�낤�A�u�������낦�đ�����������Ƃ����X�s�[�h�ł���Ă��������v�ȂǂƏ��������āB
�����������肾�낤�A���i�҂ȂǏo�Ȃ��̂ł���B�����炱���A���ꂼ��̋��ɂ���Ď�ڂ��Ζʂ��Ⴄ�̂��B�X�L�[�͂��̏ɉ����Ă��낢��Ȋ����������K�v�����邱�Ƃ�ǂ��킩���Ăق����B����Ȃ̂ɁA��������Ŏg����Ζʂœ���������J��Ԃ����Ȃ��A����ł͐i�����Ȃ��ł͂Ȃ����H������ڂł����낢��ȏ����ŗ��K���鎖�ɂ��A���Ȃ��̑̂����̏����ɂ������������Č����Ă����悤�ɂȂ�B
�X�s�[�h�̏o�Ȃ��ΖʂŁA�X�L�[�����낦�ĉ�鎖�͓������A�X�L�[���J���o�����̓����₤�B
��肢�l�́A�ǂ�ȃX�s�[�h�ł��ǂ�ȎΖʂł��A����炵�������Ă��邾�낤�B�������F����́A���������Ă��܂��K�v�͂Ȃ��B���̎�ڂɓK�����X�s�[�h�i�����̒��Łj���������B�������ł́A������芊��Ƃ������肵���Z�p���v�������A�����X�s�[�h���グ�Ē��킵�悤�B�������A�����̂��Ȃ��̊��o��\������Ηǂ��B����Ƃ͂����������̂��I
����͌����Ĉꔭ�����ł͂Ȃ��B���܂���肭���������獇�i����Ȃǂƌ������͂��肦�Ȃ��A���Ȃ����ςݏd�˂Ă������̂��]�������A���R�X�s�[�h�I�[�o�[�Ńo���o���ɂȂ��Ă͌�����B���������āA�ЂƂЂƂ��J�Ɋ��낤�B
���i�́A�����̌��E�X�s�[�h���グ����K�����āA�{�Ԃł́A�V�C�W���̗͂Ŋ��낤�B�����čő�̃R�c�́A����l���Ȃ������I���x���\���グ�邪�A�����̂Ƃ��芊��Ηǂ��B���̒��ł��������̃R�c�������Ă݂悤�B��قǂ��������ʂ�A���̊���ɍ����X�s�[�h��S�����鎖���B����ƁA������������ɂȂ�������ōl���Ă݂悤�A���X�L�[���͂̎��ɊJ���o���ĉ��Ƃ��悤�A�Ζʂɑ��̂��^���������Ă��܂��قǃX�L�[�����݊J���o���̂ƁA�������������J���o���̂ł́A�ǂ��炪���Ō��Ă��錟����ɂƂ��āA�J���o�����ƌ��������������₷�����낤�B
�������藿���̂�����A���Ȃ��̕\�����鎖�������ɂ�����茩���₷���ق��������Ɍ��܂��Ă���B�����A���Ȃ��̊���������Ă��̂��B
�@�@�@�@�X�L�[�w�Z�A�閧���p�@�I
�X�L�[�w�Z�̃��b�X���͊y�����ق����������낤�B�������A���ꂾ���ł̓_�����Ǝv���B��X�X�L�[���t�ɂƂ��ĊF����͑�Ȃ��q�l���B�������ċA���Ē����Ȃ��Ă͂����Ȃ��B���͎��Ɂu�����������Ă���̂�����A�����Ɗ����₷���Ȃ��Ă��������A�F���������g�ŐV�������o�����߂Ȃ��Ȃ�A�X�L�[�w�Z�ɓ���Ӗ����Ȃ��v�Ƌ��������Ō������肵���B�����Ă������낤�A�F���X�L�[�w�Z�ɓ��邱�ƂŁA���B�͋��������炤�B
�������A�Q���Ԃ̃��b�X�����I���F���Ȃɂ����߂Ȃ���A��X�ɋ����Ȃǂ��炤���i�͂Ȃ��B�X�L�[���t���K���ŋ����Ă���A�F������K���ʼn���������łق����B�F����̏�肭�Ȃ肽���ƌ����C�����ƁA��X�̋C��������ɂȂ������A�����悤�Ȑ��ʂ����܂��̂��B
�����K���Ă��鎖���o����悤�ɂȂ�����A���łɏo���鎖�K���悤�B�K�����܂łƈႤ���o�ŏo����͂����B�킩��Ȃ����̓X�L�[���t�ɕ��������A�K�����̂��Ȃ��Ɉ�ԕK�v�Ȏ����Ă��Ă����B�������u����ł����ł��v�ƌ����Ă��A���������܂łƈႤ���o�łȂ���A���x�ł������Ă݂悤�A�u�Q���̃��x���Ȃ炻��ł����v�ƌ����̂Ȃ���邪�A�����u����ł����v�Ƃ������t��������A���̋��t�͎��i���B
�����Ă��炤�K�v�ȂǂȂ��A��ɂ��Ȃ��Ɉ����̊��o�������Ă���鋳�t��T�����I
�@�@�@�@�Q�Q�ɂȂ��Ă����K�L�͈��K�L��
���āA���̔N���͂Ƃɂ��������������Ă���Ɗy���������B�Ⴆ�A�i���֎~�������鎖�Ȃǂ��B�ǂ��l���Ă݂�ƁA�n���̈������������p�g���[���̖ڂ𓐂�œ����čs���悤�ɁA�N�ł���������ʂ�̂�������Ȃ��B�Q�Q�ɂ��Ȃ��ĂƎv���Ă��d���Ȃ��B
�ǂ��炩�ƌ����A���͈�����������j�~���闧�ꂾ�������A������Z���̖ڂ𓐂�ł͒P�Ȃ鈫�K�L�ɂȂ��Ă����B���[�C�h���Ƃ����ĒN����ԑ����]���ɉ��܂ōs�����������q���B�̂悤�ɁA�ꏏ�ɂ�钇�Ԃ͂��Ȃ���������ǁA���������Ă����悤�Ɏv���B�����A�X�L�[�Ƃ͊ȒP�Ȃ��̂Ȃ̂��B
�N����ԑ������I��ԑ����]���ɉ��܂Ŋ���~�肽�l����ԏ�肢�̂��B�R�u�Ζʂł��Ȃ�ł��A��Ԑ�ɓ]���ɍ~�肽�l����ԏ�肢�̂��B
�O�ɂ����������A���͒����~�������������ς��n�߂��B���܂ŏo���Ȃ����������A���Ƃ����₷���o�����肵���B�Ƃɂ��������ł����������悤�ɂȂ낤�I�K�����Ȃ��̒��ʼn������A�ς��͂����B
�����ƊȒP�ɁA�����ƒP���ɃX�L�[���Ƃ炦�悤�B����l����̂́A���Ȃ��������Ə�肭�Ȃ��Ă���ł����B
�@
�@�@�@���������Ⴞ�߂���
���āA3���ɂȂ�V�[�Y�����I���ɋ߂Â������A�X�L�[�w�Z�ɓ��Z����l�����Ȃ��A�X�L�[�w�Z�̃����o�[�ƃp�g���[���\���l�Ŋ����Ă����B�Ƃɂ����y���������Ă����B�`�������W�R�[�X�֊F�ōs���A���͂˂���S���q���ɖ߂����悤�������B
���������Ō��Ă��钆�A�Ō�ɑ����������Ă���B���q�悭�r���܂ł���ƃX�L�[���͂��ꂽ�B�]�����Ď~�܂��������́A�ォ�痬��Ă���X�L�[�Ɏ��L�����B���̂Ƃ��́A����̒��q�����������̂�������Ȃ����A�X�g�b�p�[(����~�߁j����肭�����Ȃ������悤�ŁA�����͗���������ƕ@���𗬂��Ă����B�i������͕@���Ɍ�����)�������A�~��Ă��������́A�@�̉��ɃX�L�[�����������炵���O�ƕ@�̊Ԃ���Ă����B
�{�l�́u�����𒆂���Ȃ߂�ƁA�オ�O�֏o��B�v�ƌ����̂����A�����܂łЂǂ��͂Ȃ��B���̂܂܊y�����X�L�[�͒��~�A�a�@�ɍs���R�A4�j�D�����B���ł��������݁A�炪�Ԃ��Ȃ�ƁA��������������ƕ����т�����A���̍����v���o���B
�X�L�[��100�����S�Ƃ͂����Ȃ��B
�܂��Ď����̃X�s�[�h���オ��A����Ζʂɍs���قǁB����̒����Ȃǂ��A�X�L�[�Z�p�ƂƂ��Ɋo���čs�����B�������āA�c��̐��T�Ԃ��߂����X�L�[�V�[�Y�����I����Ă䂫�A�S���̏�{�ɂ͗��V�[�Y�����y���݂ɑ��A���Ă������B
�@�@�@�@�X�L�[���[�͐Ⴊ�Ȃ��Ɛh���ˁI
�P�X�W�U�N�P�Q���Q�R�ƂW�����A�����֗��ĂR�x�ڂ̃V�[�Y�����K�ꂽ�B�������A���̔N�͑�ώ₵���N�ɂȂ����B�Ⴊ�~��Ȃ��̂ł���B
�P�Q�����Q�T�����߂������ꕔ�ʼnc�Ƃ��Ă����B
���̔N�A���Ƒ����Ɨ��`�̏��w���������܂��Ă����̂����A������Ȃ��v�����芊�鎖�͏o���Ȃ��B�Ⴊ���Ȃ��ƃp�g���[���͎d���������A����������鎖�ɂȂ�B
����Ȓ��A�P�Q���R�P���̌ߌ�A�R���ŔP���������q�����āA���t�g�ɏ悹���܂ō~��Ă��炤���ɂ������A���̐l�����t�g�ɏ悹�������������ꂩ�痎���Ă��܂����B�����̂悤�ɐႪ�������������قǂȂ��A�������������Ȃ����E�E�E���̔N�͐Ⴊ���Ȃ������B
���q�����t�g�ō~��A���̌��ɂ��܂�A����Ƃ̎v���Ń��t�g�̊Ď������܂œo���������́A�����̎��オ�����E�������āu�m�A�܂�Ă邩�ȁH�v�ƕ������B��l�Ƃ��p�g���[���A���낢��ȉ�������Ă���B�܂�Ă��邩�܂�Ă��Ȃ�����̂̎��͉���B
���̂Ƃ������������A�܂�Ă��鎖���m�M���Ă����Ǝv���B�������A�������Ŕے肵�����Ă��̂悤�ɕ������̂�������Ȃ��B
����Ȏ�����l�����S�����邽�߁u�����A�P�����Ǝv���܂����A�O�̂��ߌŒ肵�Ă����܂�����A�����g�Q�����B���Ă�����Ă��������B�v�ƌ������������B���̂Ƃ��̎��́u�Ђǂ��P�����Ǝv���v�Ƃ��������Ȃ������B����Ƒ����́u�{���ɂ����v�����A���O�̊�ɂ͐܂�Ă���ď����Ă��飂ƌ������̂������B
���́u�܂�Ă�Ǝv���܂��v�Ɠ��������A�������ė܂��o�����������B�����܂ʼn��N�����K���Ă��āA���ł��ꏏ�ɗ��K���Ă��āA���ɃX�L�[�������Ă��ꂽ�l�����A�V�[�Y����_�ɐU�낤�Ƃ��Ă���̂��B���������ɂ܂Ō������w�����̑�ȃV�[�Y�����B
�a�@�ł̐f�f���ʂ͂�͂荜�܂ŁA��������ƌŒ肳�ꏼ�t������A���Ă��������������������������A���������͂����Ƃ����Ɖ����������ɈႢ�Ȃ��B�Q�C�R��������ƁA�X�L�[�w�Z�̎�t�Ȃǂ̎d�������Ȃ���A�����͎��������čs���ƌĂъA�A�h�o�C�X���Ă����̂������B���͂��̂Ƃ����w��������ɂP�O�Ԉȓ��ō��i���鎖�����S�����B
���ɃX�L�[�������A�����͎���o�����ɁA�l�̎��������邵���Ȃ������̂��߂ɂ��A�K����ʂō��i����̂��B���w�����͐��я��Ƀ��C�Z���X�̔ԍ���������A�K���P�O�Ԉȓ��ō��i����̂��B
�N�������җ��K���n�܂����E�E�ƌ��������Ƃ��낾���A�Ⴊ�~�炸�X�L�[��͕����R�ƂȂ�A�����X�R�b�v�������Q�����f�������ĉ����������Ă����B�P�������{�ɂȂ�Ⴊ�~��Ȃ�Ƃ����������B��ɂȂ�Ƒ����͉䖝�ł����Ɉ��݂͂��߁A�����y���Ƃ����Ă̓M�u�X���͂������̂�����A���Ă��܂��ē���Ȃ��Ȃ�����ő�������B
����ł���͏��Ȃ����K�ǂ��납�A�X�m�[�{�[�g�ɐ���悹�Ă̓Q�����f���̐�̏��Ȃ��Ƃ���ߑ����閈���������B�֎�(���`�j�́A���������d�����x�݂̓��ɗ��K�ɂ��Ă��A�X�R�b�v����ŗ��K�ł��Ȃ��B�������A����������Ă��n�܂�Ȃ��A���܂̏̒��ŗ��K�����邵���Ȃ��̂�����B�}�Ζʂ͂قƂ�NJ���Ȃ��̂ŁA�ɂ�����ƊɎΖʂɍs���v���[�N�{�[�Q���Ȃǂ̗��K�����Ă����B
�E������(�������w�����j�́A��͂�Ⴂ���A�I�茠�Ō���\�ɂȂ�����������A���ł����B�̊�����u�����������v�ƌ����ė_�߂Ă��ꂽ�B
����Ȏ������炱���A�����ɗ��K�ł��Ȃ��������炱���A�]�v�Ɏ��M�ɂȂ���B���v�A�E������肢�ƌ����Ă����̂�����A����ȋC�ɂ�����ꂽ�B
�@���̎��A���Ɗ֎悪���w�����A�z�{����(���Ȃ��a��j���w����������T���Ă����B
�@�@�@�@�ٍ��̃X�L�[
���̍����T�������ƕz�{����́A�h�X�L�[�w�Z�֏C�w���s�̎�`���ɍs�����ɂȂ����B
�����͓�����~�[�e�B���O���I���A�P�O�����烌�b�X�����J�n���ꂽ�B
���b�X���I����A�����œ����I�[�X�g���A�̋��t�ɂ�錤�C������̂ŎQ�����Ă��������Ƃ������ƂŁA��X�͎Q�������B���Z����������̐l����`���ɗ��Ă������Q�����Ȃ������悤�ŁA�X�b�^�t�̂`����̒ʖ�Ŏn�߂���B
�I�[�X�g���A�̋��t�́u�㉺�����g���āv�ƌ����̂����A���̊�������Ă������ɂ͏㉺���Ƃ͎v���Ȃ������B�݂�ȋȂ�����L�����肵�Ȃ��犊���Ă����̂����A���͎����̌����ʂ�A�������ʂ�Ɋ����Ă������B���̎��u�f�n�n�c�C�f�n�n�c�v�Ɨ_�߂�ꂽ�̂��o���Ă���B
�ނ͏㉺���ƕ\�����Ă����̂����A���ɂ͂����������A�㉺���ƌ������A��̂ƎΖʂ̊p�x���܂������ς����Ɋ����Ă���悤�Ɍ������B
���ꂪ�㉺�����Ƃ炦�����̎����̊��o�������B�F����������̊��o���ɂ��Ăق����B�@
�X�L�[�����t�����̒ʂ藝�����悤�Ƃ��Ă��A��ɏ�肭�s���Ȃ��B���ꂼ��Ƃ炦���͈���ē�����O�Ȃ̂�����A�����̊��o��M���邵���Ȃ��ł͂Ȃ����B
�X�L�[���t�̌������Ƃ������̊��o�ɒu�������āA�������Ăق����B�����Ă������낤�A�l�Ԃ͎����ŗ����ł��Ȃ������A�\�����鎖���l�ɓ`���鎖���o����͂����Ȃ��B���͂܂���肭����Ȃ��Ă��A�܂������C�ɂ���K�v�ȂǂȂ��B���Ȃ����A���Ȃ����g�̊��o�ŗ��������K�𑱂���A�K����肭�o����悤�ɂȂ�B
�@�@�@�@�{���u�K��
�@�Q����{�A���w�����{���u�K��ɎQ�������B����͏��w��������҂�Ώۂɍ��h�Œb���グ�鎖��ړI�ɍs����B���͎��Z�A��͊w�Ȃƌ����悤�ɁA�R���ԃJ���l�߂ŃX�L�[�̂��ƈȊO�͍l�����Ȃ���Ԃ������B���̎����߂āA���͊O�̐��E��m��̂��B�Ⴆ�Α��̃X�L�[�w�Z�̘A���Ƙb������A�f�����X�g���[�^�[�������肷��̂��B���̏�A��X�̎w���ɓ�����̂͌����̃f���⌳�f���������肷�邩�犴������B���B�͂����ŁA���̊����ڂɏĂ��t���邱�ƂɂȂ�B
���ču�K�̓��e�ƌ����A��ڂ̗��K������̂����A�}�Ζʂł͂Ƃɂ������������u���ꂶ��A���Ō��Ă邩��E�F�[�f�����Ŋ����Ă��āv�ƌ������u�t�́A�������낻��~�܂邾�낤�Ɨ\�����Ă���n�_��ʂ肷���Ă��A�~�܂�C�z���Ȃ��u���������A��k���낤�v�Ȃǂƌ����Ă���ԂɌ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�d���Ȃ��̂ŁA���B�͏��Ԃɍ~��čs���̂����E�E�E�B�T�O�O�����U�O�O�������ŗ����Ă��āA��X���[�G�[�G�����Ă�Ɓu���̂��炢�Ńo�e��́H�v�Ȃǂƌ����āA�����Ɋ���o���̂��B
����Ȓ��q�ŌߑO�ߌ�Ƃ������ꂽ��́A�w�Ȃ̖͋[�������҂��Ă���̂������B���h���I���ƌ���ōĊJ���鎖����āA���ꂼ��̃X�L�[�w�Z�֖ڂ��P�����Ȃ���A���čs���̂��B
�@�@�@�@�ςݏd�˂����̂����Ȃ��I
�����ĂQ�������{�ɂȂ�ĂуX�L�[��̉c�Ƃ͈ꕔ�ɂȂ��Ă��܂��B��X�͐�̂��鏊�֍s���ẮA����]������K�𑱂��Ă����B�����āA����ȗ��K����o���Ȃ��Ȃ�A���h�ɍs�����ƌ������ɂȂ����B���ё����̒m�l�̕ʑ�������ɂ���A�^�_�Ŏg�킹�Ă���鎖�ɂȂ����̂����A�c�O�Ȃ���֎�͎d���ŎQ���ł��Ȃ������B
���������낻�늊���悤�ɂȂ��Ă��āA�y�j���̖铞��������X���H���̏������n�߂�ƃK�X����Ă��܂����B�����͓̂d�q�����W�������B����łT�l���̃��[�����Ɨ��Ă��H�����A���Ƃ̓r�[��������̂ŏ\���������B
�����A�E��ŃQ�����f�֏o��ƁA���j���ƌ����������胊�t�g�͑҂�����邵�A�l�������{�C�Ŋ��鎖���o�����A�ɎΖʂŗ��K���邱�ƂɂȂ�B
���̓��A���悻�_�߂����̂Ȃ��Z�����u��������Ȃ����v�ƌ����Ă����B
���͂�A���K�s�����ǂ����鎖���o���Ȃ��A���M�������Ď��邵���Ȃ��̂��B���i�ςݏd�˂����̂�����Ɍ����B�������A���̐ςݏd�˂����Ȃ��A���Ȃ���Εʂ̂Ƃ��납�玝���Ă��Ȃ�������Ȃ��B�Ƃɂ������M���������Ȃ��B
�@�@�@�@���w��������n�܂�
�����ĂR���P���A���Ɗ֎�͍Z���̎ԂŌ�����̐V�ԑq�X�L�[����������B�Z���͌�����Ȃ̂ŁA�A��͂R�l�ŋA���悤�����̎Ԃ�u���āA��ɏo�����Ă����B
�u�������A�ǂ��炩����������A�����ԂŋA��̂͐h���ȣ�Ȃǂƌ����Ȃ���A�����Ă������̂����ł��o���Ă���B
�O���ɒ��������B�́A��̂�������Q�����f�������Ă����B����邱�Ƃ��y�����āA�ׂ������Ƃ��l����]�T�ȂǂȂ��B�[���A�{���Ŏ�t���ς܂��Ɩʐڂ��I���ďh�֖߂�A�y���r�[���Ȃǂ����݂Ȃ���[�H���I���A��X�̓X�L�[������ǂ݂Ȃ��疰��ɓ����Ă������B
�@���肩��o�߂�ƁA���悢����Z�̌��肪�n�܂�B���X������[�b�P���̏��Ɍ��߂�ꂽ��ڂւƌ������B���̍��̏��w��������͎��Z���P�O��ځA�w�ȂƖʐڂ������B���H��ڂƂ��āA�p�������^�[���A�E�F�[�f�����A�������~�A�X�e�b�v�^�[���A�������~�B�w����ڂƂ��āA�v���[�N�{�[�Q���i���ݏo���`�A���ڂ�`�j�V���e���^�[���i�R�J���A�J�J���j�����^�[���̓W�J�ƂȂ��Ă����B
�@���Č���ɓ���ƁA��͂��ϋْ��������A���ł��o���Ă����ڂɂ��ď����Ă������B�������~�͊�^�C���̂P�Q�O���ȓ������i�A�������A���̊�^�C���ƌ����̂́A�����̃f�����ڂ̑O��{�C�Ŋ����čs������s���ɂȂ�B����ł���^�C�����Q�O�b�Ȃ�Q�S�b�ȓ��ł����̂�����A�܂��傫�Ȏ��s���Ȃ���Α��v���B
�@�������~�̓X�^�[�g�n�_����ɂ��Ζʂ������A�T�O���قǐ�Ƀ|�[�����Q�{���ĂĂ������B���̊Ԃ�ʂ�Ƌ}�ΖʂɂȂ�A�܂��Γx��������B�X�^�[�g�n�_����́A�Ζʂ��ǂ��Ȃ��Ă���̂��킩��Ȃ��̂����E�E�E�B���͂Ƃɂ�������čs�����Ǝv���A�����Ȃǂ��Ȃ��łR��]�ō~��čs�����ɂ����B���Ƃ͉����l���Ȃ��A�}�Ζʂ̒��قǂ����]���͂��߁A�R��]�ڂɓ������Ƃ���ŃS�[���ɒB�����E�E�E�v�Z�ǂ���A���M�̎��Ă銊�肪�o�����B
�@�E�F�[�f�����́A�R�O�O�l�߂������邽�߉����T���Čł߂��Ă͂������A���̎��ɂ͂����ԍr��Ă����Ǝv���B�Ƃɂ����m���Ɋ��鎖�������l���A�ЂƂЂƂ��J�Ɋ���~��Ă������B�p�������^�[���͂����̂Ƃ���A�����l�����S�[����ڎw�����B�v���[�N�{�[�Q���ł͍Z����������ŁA�u�K�`�K�`�̃��{�b�g�݂����������v�ƏI����Ă��猾���Ă��܂����B����Ȓ��q�łQ���ԁA�S��ڂ��I�������̂������B�����Ċw�Ȏ������I����ƁA�h�֖߂�֎�Ɗ��t�����B
�@���������\�̒��A��ςȎ����N�����Ă��܂��B
���H���Ƃ�R�[�q�[�����݂Ȃ���G�k�����X�̊ԂɁA�ꖇ�̑傫�ȉԂт炪�q���q���Ɨ����Ă����B��l�͊�������킹��Ɩ{���ɕs���ȋC�����ɂȂ�A�ǂ��炩��Ƃ��Ȃ��u�_����������Ȃ��v�Ȃǂƌ����A�������C�����̂܂܍��i���\���Ɍ������̂������B
�@�@�@�@���w����
�@���w��������͐��я��Ŕ��\�����B�P�O�Ԉȓ����ڕW���������́A�����������̂Ȃ��悤�ɐ������B�������P�O�Ԃ܂łɖ��O���Ă�鎖�͂Ȃ������B����Ȃ�Q�O�Ԉȓ��Ǝv�������_���B����ƂR�R�ԖڂɌĂꂽ�B�����x��Ċ֎���Ă�A��������킹�z�b�Ƃ����̂������B
���̉Ԃт�͍K�^�̈����悤���B
�@�葱�����I�������o��ƁA��X�͐���ď��w�����ɂȂ��Ă����B�h�A��ו���ςݍ��ނƁA�{���܂ōZ�����}���ɍs���R�l�ō����ɏ��B���̓��̍Z���́A�Ԃɏ��ƃo�J�Ȏ����茾���Ă����悤�Ɏv���B
�ٓ��ɖ߂�ƊF���o�}���Ă����B
�u���݂܂���A�R�R�Ԃł����B�v�ƌ��������ɁA�u�o�J�����[�v�ƌ������������{���Ɋ��������Ȋ�����Ă����B����O�ɂ́A�u�P�O�Ԉȓ��Ŏ��Ȃ�������A�т�����܂��v�Ȃǂƌ����Ă����������A�搶���͂��̎��ɂ͒N��l�G�ꂸ�ɁA�F�{���Ɋ��������������B
�z�{����������Ɏw�����ɍ��i���A���i�j�����n�܂�B�p�[�N�z�e���̉����ɂ́A�R�O���ʏW�܂������낤���A��ςȑ����ɂȂ������͌����܂ł��Ȃ����낤�B
�@�������ʼn�鎄�ɒN�����A�u���̐m�����w�����˂��E�E�E�v�ƂQ�N�O�̎p���v���o���Ȃ���Ԕt���Ă����̂������B�����čŌ�́A��̂��Ƃ����N���鏬�ё����ւ̑�v���b�V���[���ւƕς���čs���̂��B���̎����Ɗ֎�́A���߂ăv���b�V���[��������ق��ɂȂ���ł���A�u���т���A���w�����͓����v�ƌ������B�ɁA�����́u���O���v���b�V���[������Ƃ͂P�O�O�N������v�ƌ����Ȃ�����������Ȋ�������B
�������āA�����̓P�K�̂��ߎł��Ȃ������̂����A�ٓ��X�L�[��ɗ��ĂR�V�[�Y���ځA���͏��w�����ɍ��i�����B
�R�����{�ɂȂ�ƁA�F�V�[�Y���̔�ꂪ�o�ė��āA�̂�т�߂����悤�ɂȂ�B���͂ƌ����Ɠ�����͍l�����A�������͂˂��肵�Ċ����Ă����悤�Ɏv���B�ٓ��X�L�[�w�Z�ł͂P�����X�L�[�w�Z�ŋ����鎖�͏��Ȃ��A�F�p�g���[������n�ߏ��w����������ď��߂ăX�L�[���t�Ƃ��ăf�r���[���čs���B
�g�D�I�ɂ͍Z�������ӔC�҂œ��������A�X�L�[�w�Z�ƃp�g���[���ɂ͂��ꂼ��ʂ̕���������A����܂ł̎��̓X�L�[�w�Z�ŃR�[�q�[������ŋx�ނȂǂƌ����A���ꑽ���������������A���̍��ɂ͕��C�ɂȂ����B���̕ӂ̂Ƃ���́A�͂����肵�Ă��Ċ֎�͍��i���Ă���X�L�[�w�Z�̃X�^�b�t�ƂȂ����B
�@���́A���̂܂܃p�g���[���𑱂��Ă����B�m���Ƀp�g���[���́A�J�̓�����̓����A�O�ɏo�Ă���̂��d���Őh���������邪�A�����ȂƂ��뎄�̓p�g���[���̂ق����D���������B�g�����V�[�o�[�ł��ł��Ăяo����Ă��܂�����ǁA�d�����Ȃ���Q�����f�̏���ԑ�Ȃ̂�����B���Ɉ����Ƃ��낪����Β����̂��d���ŁA����Ԃɂ͂��ׂẴQ�����f������Ȃ�������Ȃ��B���Ȃ́A���t�g�������o���Ǝ�ւ�����Ă���������̂悤���B���葱���čs���s���A�����̉Ƃ��킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B
�@����ԁA�ЂƂƂ��茩�ĉ��ƈ�l�Œ�����Ƃ���͒����A�������K�v�Ȏ��͘A��������Ǝ�`���ɗ��Ă����B�����Ȃ���A��������܂���̂��B���̎����ɂȂ�A���q��������Ȃ��Q�����f�����t�g�������̕��̂悤�ŁA����܂����Ĕ�ꂽ��A�X�L�[�w�Z�ɖ߂��ċx�߂����B
�P�O�����ɂȂ�ƊF���o�Ă���B���b�X���̂Ȃ��搶�����W�܂��Ċ����Ă���ƍ������Ċ��鎖�����������A����������Ă��鎞�͗���čs���B�V�C�̂������͏��ԂŊ������肷��Ƒ҂��Ȃ�������Ȃ��̂ŁA�܂�Ȃ��B����������́A�X�s�[�h���o���ĕ�����Ċ���̂��D���������B�ƌ����Ă��y���������Ă��邾���ł͂Ȃ��A�u�����Ə������Ȃ��Ă݂悤��Ƃ��u�����������ɏ���Ă݂悤�v�Ƃ��A�����l���Ȃ��牽�{�����{������̂��B���̍��ɂ͑��������\���Ă��āA��l�Ŋ����Ă����B�N�^�N�^�ɂȂ��āu�[�G�[�G�v�����Ȃ��犊�葱����̂��B
�l���Ă݂�A�q�����Ȃ��Ƃ��炱���֗��Ă��܂������A�����������������B�ނ́u�R���������ĂāA�R�ŕ�炷�v�ƌ����A�V���A�R�`�̌����ł���іL�A��ɓo��n�߂��B��������̎��Ƃ��V���ƌ�����������A�܂������m��Ȃ��킯�ł͂Ȃ��������A���쑺���ꂪ�Ǘ�����R�����ōZ���B�ƒm�荇���B
��̒��q�Łu���ьN�͓~��d���Ȃ����낤�A�X�L�[�o���邩�H�v�ȂǂƍZ���Ɍ����X�L�[��œ������ɂȂ����炵���B
����ȑO�͎u�ꍂ���ŃA���o�C�g���Ă����̂ŁA�܂���������Ȃ��킯�ł͂Ȃ��������A�悭�Z���͎�������ł��鎞�Ɂu�����Ђǂ��������ǁA�m�Ȃ���قǂƂ͎v��Ȃ������v�Ȃǂƌ����Ă�������A�������Ђǂ������̂��낤�B
���ł́A�Ђǂ��̂ƁA�����ƂЂǂ��̂��p�g���[���Ƃ��Ĕ�т܂���Ă���A���������ǂ�ȃX�L�[�ꂾ�낤�B
�P�K�������l��w�����Ċ�������A�X�m�[�{�[�g�ɃP�K�����l���̂��āA�}�Ζʂ����낵�Ă��邱�Ƃ��o����قǏ�肭�Ȃ����B�Ђ���Ƃ���Ƒٓ��X�L�[�w�Z�̖ʁX�̓X�L�[��������V�˂�������Ȃ��B
�����Ĉꎞ�ׂ��Ȃ��������̑����A���X�ɂ��Ƃ̑����ɂȂ�n�߂����A�X�L�[��͕������B���V�[�Y�����d�����I���A��X�͑ٓ��X�L�[�����ɂ���̂������B
�@�����͂��̔N���葫��Ȃ������̂��낤�A�u�̒r�Ŋ����čs�����v�ƌ������ɂȂ�A�����̗F�l�̓������b�W���������B�����S����{�A����ǂ��Ȃ�����ǁA��X�ɂƂ��Ă͌y���Ⴞ�B��͂�A��ւ�����Ă���������̂悤�Ɋ������B
�@�R�N�O���߂Ċ������X�L�[�ꂾ���A�����������̎��Ƃ͈Ⴂ�ȒP�Ɋ����B�Y���Y���ƐK�ō~�肽�n�̔w�R�[�X�ł����ō��̎Ζʂ��B�R�u�Ζʂ�}�Ζʂł́A�~����ő����̐l�����߂���Ă��āA����������ƊF�ɒ��ڂ����B���ꂪ�y�����̂��B
�@�����A���Ȃ��͎����̊��o�����߁A���K���鎖�ɂ���ĕς���čs���B�m���ɏ�肭�Ȃ��Ă���B�����āA���Ȃ����ς��ΎΖʂ��ς��̂��B���܂܂ŕ|���Ċ���Ȃ������Ζʂ��A�}�ΖʂłȂ��Ȃ�B
��肢�l�����Ďw�����킦�Ă������Ȃ�������n�߂�ƁA����̐l���w�����킦�Č��Ă����悤�ɂȂ�B
�@�m���ɓ�������������邩������Ȃ��B�������A�����̊��o����������͂݁A���K�𑱂���ΕK�������悤�ɂȂ�B�����y���݂Ȃ�����K�𑱂��悤�B
�@�������Ď��ɂƂ��Ă̂R�V�[�Y���ڂ͏I���A���V�[�Y������́A�w������ڎw���Ă̗��K���n�܂�̂������B
�@��S�́@�w�����Ƃ�
�@�w�����̓X�L�[�E�̐�B�Ƃ��āA���̕��y�A���W�ɓw�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
����͓��{�X�L�[�����w�����K���̏��߂ɏ�����Ă��镶�����A���������āA���o�ƌւ�Ȃ̂��B����́A���������ꂾ�����K���Ă����I�ƌ����������ւ�A�����āA�����̐�y�B�ɒb����ꂽ���Ƃ��A���k������y�ɓ`���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�ƌ������o�Ɍq����Ǝ��͎v���Ă���B�{���̂Ƃ���́A�X�L�[�̋��t�ƌ������ŁA�p���������s�ׂ̂Ȃ��悤�ɂƌ����Ӗ��ł�����Ă���̂�������Ȃ����A����͂���ł����B�����ǂ̂悤�ɗ������Ă���̂��ƌ��������B�X�L�[���t�B�́A�S����X�L�[�������Ă���A�F����ɃX�L�[�������Ăق����Ǝv���Ă���B������F������A��肭�Ȃ肽���Ƃ����v�����X�g���[�g�ɂԂ��Ăق����B
�@���Ȃ��̂킩��Ȃ����Ƃ́A�Ȃ�ł������ėǂ��B�X�L�[�w�Z�ɓ��������A���t�ƂP�P�ȂǂƂ������Ƃ͏��Ȃ��Ǝv�����A�܂������m��Ȃ��l�ƈꏏ�ɂȂ莩�����猾�t���邱�Ƃ���ς��Ǝv���B�������A�S���̏�肭�Ȃ肽���ƌ����C�����͓������Ǝv���B�X�L�[���t�͊F��������₷���悤�ɁA���₵�₷���悤�ɕ��͋C����ɂ��Ă���B�������A�����������Ă���̂����痘�p�ł��邾�����p���Ȃ���Α����B
�Q���Ԃ̃��b�X�����I����Ă���ł��������낤�A�Ƃɂ�������Ȃ���������Ε����Ă݂悤�B�����ł͂Ȃ����A���b�X�����̃m�����悭�X�L�[���t���n�C�ȋC���̎�������B����Ȏ��͉�X�����āA�����ƃX�L�[�̘b�������Ă��������A�����Ƌ����Ă������A�����̎��ԊO�J�������Ăł���̂��B���ʂ̉�ЂŌ����Ƃ���̎c�Ƃƌ������̂��H�@
���t�B�͂����ǂ����͋C�ŕ����Ă��炦��悤�ɍl���Ă���B�݂Ȃ�����X�L�[���t���n�C�ȋC���ŋ�������悤�ɁA�l���Ă݂�Ɩʔ������낤�B�����Ǝ��Ԃ��Y��K���ɂȂ��āA�F����ɉ�����͂�ł��炨���Ƃ���͂����B
�@�@�@�@�܂��A�V�[�Y�����n�܂���
�P�X�W�V�N�P�Q��(�Q�S�ƂW�����j�X�L�[��ł������̂��S�V�[�Y���ڂƂȂ����̂����A���܂łň�ԔߎS�ȔN�������B�Ƃɂ����Ⴊ�~��Ȃ��̂��B�X�L�[�ꂪ�I�[�v�����Ȃ���A���j���ƌ����Ă����q����͂��Ȃ����A���̐搶�����R�ɏオ���Ă��Ȃ�����A�₵�����������B
���̔N�A�����Ət������w����������T���Ă����B�w�����͏��w�������i�̔N���܂߂Q�N�Ԏł��Ȃ�����A���Ɗ֎�̎͗��V�[�Y���Ƃ������ƂɂȂ�B�P�Q���Q�O���߂��ɃX�L�[��ɓ��������Ƒ����́A��͂茊���@�����肵�Ă����B
����Ȏ������Ă���ƁA����̍���ے�����W���j�A���[�V���O�`�[���̈����𗊂܂��B�ٓ��X�L�[��ł������̑��̂��߂Ƀ��[�V���O�`�[����������X���K�����Ă���B�q���B�͂��łɓ~�x�݁B
�{���Ȃ疈���X�L�[�𗚂��Ă���͂��ŁA�X�L�[��ō��h�̗\�肾�������A�Ⴊ�Ȃ���X�L�[��ł͂Ȃ��A�����Ō��R�܂ō��h�ɍs�����ɂȂ����̂��B���Ƒ����̓X�L�[���o���邵�A�d�����Ȃ������ň������B�ӔC�҂͍���ے��A�R�[�`�͗E������(�������w�����j���w�Z���璆�w�Z�܂ł̎q���B�R�O���قǂ��o�X�ɏ��A��X�͎q���B�̃X�L�[��ςg���b�N�ɏ��o������B
�X�L�[��ł̓��t�g�ňꏏ�ɂȂ邱�Ƃ����邵�A�q���B���|�[�����K���Ă���Ɖ�X�������čs�����肵�Ă�������A�F��͒m���Ă���B���Ɉ�`����(�Z���̖�����j�Ȃǂ́A�����ƂŎ�������Ő��������Ă����X�����������畡�G�Ȏv����������������Ȃ��B
�����������Ă��邤���ɍ��h���n�܂�A���̊ԉ��l���̎q���Ɂu�m����X�L�[��肭�Ȃ����ˁv�ƌ����ė_�߂��Ă��܂��A����͎q���ł��������Ȃ������̂��B�������ނ�́A�R�N�O�̎��̎p���m���Ă��邩��_�߂Ă����̂��낤�B���̐l���������肷��̂�����r�b�N���Ƃ������\������B�����āA�q���B�͓ˑR��̂��銦���Ƃ���֗������̂�����A���l�����M���o���A���̓X�L�[�ꂩ��A��̈����Ȃ����q�����Ԃ��ďh�܂ŘA��čs���W�B�����́A�܂�ł���ׂ����Ă��悤�ɁA�����玟�ցA�����₵�Ă���^�I�����Ђ�����Ԃ��Ă����B
���h�������ɏI���X�L�[��ɖ߂�����X�́A�V���n�̓���������I���̗n�ځA�p�[�N�z�e���̃��E���W�ŃM�^�[�̒e�����A��A���ɂ̓O�����h�z�e���Ń��[�������������ƁA���낢��Ȏ������ĉ߂����B�p�g���[���͉��ł��o���Ȃ�������Ȃ��B
�@�@�@�@�X�L�[��͉�����
���͂��̔N�A�Ă����������Ă����B
�����͂S�����{����P�P���܂Ŗk�A���v�X�̖k�䍂�����Ƃ������œ����Ă��āA�o�R������l�Ȃ炲���m��������Ȃ����A�W���R�P�O�O���̍����ɎR����������A�h������o�R�҂̐H�����������A�|���������肵�ĉď���߂����Ă����B�L���ȏ㍂�n����k���P�T���Ԃƌ������Ƃ��낾�낤���B
���R�A�W���������̂łV�����܂ł͊����B�������X�L�[��ł͂Ȃ��̂ŁA���t�g�͂Ȃ����A����͂�������イ�A�Γx���Ƃ�ł��Ȃ��̂ł��܂肨���߂ł��Ȃ��B�k�䍂��������Q�C�R���ԉ��������ɟ���Ƃ����Ƃ��낪����A�����ł͂V���ɋ��Z�X�L�[������l�B���L�����v���邱�Ƃ�����B�����U���܂ł́A�o�R�o���̂Ȃ��l�������Ă���͓̂���A�T���̘A�x�O�͎R�����̏]�ƈ�������Ă��邮�炢�łقƂ�Ǔo�R�҂����Ȃ��B�S���܂ł͂��Ȃ�̌o�����Ȃ���Γ���X�L�[�ǂ���ł͂Ȃ��B
��X�͂S���̂Q�O���߂��ɎR�ɏオ��ƁA��ɖ��܂��������𗈂������������@��o���̂������B�X�L�[��C�̓w���R�v�^�[�ʼnחg�����鎞�֏悳���Ă��������B�U���ɓ���Ɵ���ŎR�����]�ƈ��e�r�X�L�[�����N�J����Ă����B�㍂�n�̗��ق�R�����œ����X�L�[�D���Ȑl�B���A�X�L�[��S���ł���Ă���̂��B���͏�̏����ɂ��邩��A�A��͒S���ŏ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����X�L�[�Ŋ����čs���B
�k���͏����̎���ň�Ԋ���₷���Ζʂ����A���̎Γx�ƒ����ɂ͐�������Ă��܂��A�X�L�[��̏㋉�҃R�[�X�ȂǂƂ͔�ׂ悤���Ȃ��B�{���̂��Ƃ������ƁA���߂̂T�|�U�O�O���͕|���Ă܂Ƃ��Ɋ��鎖���o���Ȃ������̂��B���̎����͏��w�����ł���B�����Γx���ɂ��Ȃ��Ă���͏�肭�s�����̂�����ǁA�o��Ƃ��Ζʂɂܐ���R�肱�߂ΕG���������炢�̎Γx������A�|���Ȃ�ĕ�����Ȃ����A�]���ρA���������B
����Ȏ��́u�������w�������B�܂Ƃ��Ɋ���Ȃ�����Ȃ����B�v�ƌ����C���ŁA����������Ȏ���Ɋ�����B
�@���āA�[���ɏW�܂����l�B�̓X�L�[��������A�������肵�Ă������߂����̂����A��͑�ρA�قƂ�ǑS�����f���܂ň��ށB�����A���E�̓��₩�Ȑ��E���痣��Ă��邾�������āA�����܂��������ɂȂ�B�����͊F��������ŃX�L�[���ɂȂ�B���l���̒��Ԃ́A�~��{�C�ŃX�L�[�����Ă��邩��A���\���M����B�|�[�����Z�b�g���Ĉ�{�^�C�������A�D���͐\�����Ő\���^�C���ƂQ�{�ڂ̃^�C�����߂��l���B�����Ė{�C�ŗ��K���Ă���l�B���M���Ȃ�̂��A���b�v�܂łQ�{�ڂ̃^�C���������l�̏����A�ܕi���p�ӂ���Ă���B���̔N�̗D�������́A���Ɣ����X�L�[�w�Z�ŃA�V�X�^���g�����Ă��鐣��(�P���j�̓�l�ɍi���Ă����B
��{�ڂ��I����ƃr�[�����n�����A��������܂Ȃ�������Ȃ��B���̎��Ɋ����Ă�������͎��̐\���^�C�����m�F���āA�����^�C����\������B�|�[���͂Q�O���{���Ă��Ă���B��������Ɠo��n�߂�O�Ɉ��r�[���Ńw���w���ł͂��邪���𐮂��Q�{�ڂ�����B
��ŏ������Ƃɂ��邪�A�F����������Ă��邩������Ȃ��B
���̓��������ł��x�z�l�͔����ŃX�L�[�������Ă���(�r�`�i�̃X�L�[�w�Z�ł͂Ȃ�)�A�悭�u�ٓ��Ȃ�ĕ����������Ȃ��A����ς蔪���̂P������v�Ȃǂƌ����Ă����B����̐l�B��������̒r�Ƃ������������쌧�œ����l�������̂ŁA���̃X�^�[�g�̎��͊F���X�^�[�g�n�_�Ō��Ă����B���̔N�̂R���ɏ��w�����ɍ��i���Ă�������A�x�z�l�␣��̂悤�ɒm���Ă���l�͂����u�ٓ��Ȃ�āE�E�E�v�Ƃ͌���Ȃ��������A�m��Ȃ��l�ɂ͂܂��u�����̂P���������痎�����v�Ȃǂƌ����鎖���������B
���̂悤�Ȑl��ɂ��Ă��d�����Ȃ����A���͂b��������ɂ����i���Ă�������u�����ʼn����āA�������短���ɂȂ�Ȃ���v�Ȃǂƌ����Čy�������Ă����B�����狣�Z�X�L�[�̌o�����Ȃ��ƌ����Ă����w�������B�����ȒP�ɕ������ɂ͂����Ȃ��B�S�[���������̃^�C���́A�����Ƀg�����V�[�o�[�ŃX�^�[�g�ɒm�炳��A���삪�X�^�[�g����B���ǁA�\���^�C�����0.2�b���������������D���ƃ��b�v�܂̊��S�D�����ʂ������̂������B�����č������x���ł͂Ȃ����A�������炢�̒��Ԃ��{�C�Ń^�C���������Ă��邩��ʔ����̂��B
���̔N�́A���삪���w�����̔N�������Ǝv���B���̏����̎x�z�l�́A�Ⴂ�����Z�X�L�[�����Ă��āA�i�V���i���`�[���̑I��Ȃǂ̖��O���o�Ă��邵�����̃f���Ȃǂ��m���Ă��āA���Ȃ��肢�̂��B
�ނ͍��܂Őe�r�X�L�[���ɎQ�����Ă��D�����ē�����O������o�Ȃ������̂����A���̔N���w�����Ə��w�����҂�ɎQ�����邱�ƂɂȂ�A����������Ȃ݂Ȃ݂Ȃ�ʓ��u��R�₵���B����ɐ���͎��ɑ��郊�x���W�������ς��B�Ƃ͂����O���͑呛���ɂȂ鎖�ɕς��͂Ȃ��B�k��̎x�z�l�̃X�L�[�̏�肳�͒m���Ă������A�O�N�̎��Ɛ���̐킢�Ȃǂ��\�ɂȂ�A�Q���҂������ԑ����Ă����悤�������B
��̂��Ƃ���͑呛���ŁA��������̃����o�[�B�͎��X�Ƀ^�C����\�����Ă����B���ǁA�x�z�l�A����A���̂R�l�������^�C����\�����āA���b�v�܂ƗD���̉\�����c���Ďn�܂����̂������B���ʂ͐��삪�\���^�C�����P�b�������胉�b�v�܁A�����O�D�W�b��������D���A�x�z�l�̓R�[�X�A�E�g���ċL�^�Ȃ��������B
���̔N�̂T�����{�������Ǝv���B
���͖k��̖k�ǂɒ��킵�āA�낤�����𗎂Ƃ��Ƃ��낾�����B
�[���A�d�����I��菭�������Ǝv���X�L�[�𒅂������A���̓��͒�����₦�Ă��āA�Ⴊ�d�������̂��B�T���ƌ����Ă��}�C�i�X�P�T�x�Ȃǂƌ����������邮�炢���B�y���l���Ă������͎Ζʂɔ�т��B�Ƃ��낪�G�b�W�͂܂����������炸�A���̂܂܂̎p���ʼn����o���Ȃ��܂܂Q�O�O���������Ă����������������B
�]�炨���܂��A�Q�����قǂ����������Ď���ł��܂��B�K���ŃG�b�W�������悤�ƁA�̂��N����������l���Ă����B���Ƃ��Ԑ��𗧂Ē����Ί��~�œ���(���瑱������)�̕��֊����Ă����ƁA�����܂ł͂P���Ԃ��炢�������ď���Ă������B
�Ȃɂ����w�������A�܂��������������Ȃ��ł͂Ȃ����u���肾�ȁ[�v�Ǝv���Ȃ���A�₵���C���̂܂����ɂ����B�����̎���͑�ϊ댯�Ȃ̂ŁA��i�̓X�L�[������Ƃ���������Ȃ��B���������邩�킩��Ȃ��̂ŁA�u���[�|��������ȊO�͉�������Ȃ������B
���N��A�����Ƃ����Ă������Ԃ��������痎���āA�S���U�����̏d�ǂ����B������Ⴉ�����Ƃ͂������d�Ȏ����������̂��B�F����͂���ȂƂ�������鎖�͂Ȃ��Ǝv�����A�X�L�[��ł������ŁA�X�L�[�͂܂��������S�ȃX�|�[�c�Ƃ������Ȃ��̂Œ��ӂ��悤�B
���͌����Ė`���X�L�[���[�ł��Ȃ����A���܂������̂�����������ȂƂ��낾�������犊���Ă݂��������B�������A����ɔ�ׂ���A�X�L�[��Ƃ́A�ǂ�قLj��S�ȏ����낤�A�����炿�ȂǂƂ悭�����邪�A�܂��������̒ʂ肾�B�P����e�N�j�J���͂��܂��w�����̎��i�����l�B�̓X�L�[����肢�̂��H�Ƃ����Ίm���ɏ�肢�̂��낤���A�ǂ�ȎΖʂł��]���ɍ~����邩�Ƃ����A�����Ƃ������Ȃ��B
���E�������n���A�G�x���X�g�����Ċ���l������B�ǂ�ȂɃQ�����f�ŗ��K���Ă��o���Ȃ����͂�������̂�����A���̂��Ƃ���ɖڂ�D���Ă͂����Ȃ��B�ڕW�Ƃ��ĂP����ڎw�����͂������A�����I�ɗ͂�����Ӗ��ł��A�������낢��ȏ������낤�B���낢��ȃQ�����f�ɒ��킵�悤�B
�����ɂ́A�킩��Ȃ�����������
���āA1�������{�ɂȂ�A����ƃX�L�[�ꂪ�I�[�v�������B�Q�����f�̏���Ȃǂŕ����͓��ɑ����ƍs�������ɂ���ꍇ�������A�^���Ȋ�Łu�����Ă���v�Ȃǂƌ�������̂�����A���ɂ��������B�ǂ��炩�ƌ����Α����́A�Y���O�����Ă��邵�A���͐����ׂ��A�����Ă��Ă��������o�ł��낤�͂����Ȃ��B��U���ɕ\������ƁA�������}�Ζʂ������Ă���ƃQ�����f����ꂻ���Ȋ����ŁA�Ƃɂ����p���[�����邩�炢�ł��S�͂Ŋ����Ă���悤�Ɍ�����B
���R�̎��������w�������i�̃��x���ɂ͏\���B���Ă����Ǝv���B�������A�ǂ�ȂɐS���ɖт������Ă���悤�Ȑl�ł����T���ĕs���Ȃ��Ƃ������A�u�m�A���Ă��ꣂȂǂƌ����Ċ����Ă���̂������B����������u��������Ȃ��ł����v�ƌ����Ă��Ȃ��Ȃ��[���͂��Ă���Ȃ������B�Ȃɂ���N�w�Ȃ��o�Ă���w�m�l�������łȂ̂��B�����Ɏ����g�̊��o���`�����̂����A��l��l����ē��R�A���̎��͗������Ă��炦�Ȃ������悤���B
�@���ꂩ��5�N�قnjゾ�����Ǝv���B�ٓ��X�L�[��Ŏw�������C�����A���łɈ��ނ��Ă������B�́A���ƒ��삩��o�����Ă������B��͂Ƃɂ����呛���ŁA�܂�őS���̂ɖ߂����悤�������B���܂�Ɋy�����A���܂�ɉ��������Ď��Ƒ����͌��C��I����A�����ꔑ���Ċ����čs�����ɂ����B�@���̎��A�p�g���[�������B�͉�X�������̍��A���w���⍂�Z���������A���ŁA��X�͂����Ɉ����������ɍs�����B�i���֎~���ɍs���Ă̓��[�v��������A
�@���сu�m�A����ȏ��֓�������p�g���[���ɓ{���邩�ȁv
�m�@�u�܂��������炪�A��X�ɕ��匾���Ȃ��ł��傤�v�Ȃǂƌ����Ă͐̂ɖ߂��āA�������肢���N���������K�L�ɂȂ��Ă��܂��B�����Ȃ�ƁA�ǂ����Ă����t�g�̉������肽���B�猩�m��̃��t�g�W��������ẮA�~���ł��q����̏�������t�g�̔ԍ����A�����Ȃ������m�F����ƃV���v�[�������܂���̂��B�@
�v���Ԃ�ɉ�X���X�L�[�ɗ����̂ŁA�X�L�[�w�Z�̖ʁX��p�g���[���B���ꏏ�Ɋ��낤�Ƃ��Ēǂ������Ă���B��������X�̍s����X�Ń��t�g�̕������B���u���������t�g�Ɂ����搶���������v�Ƃ��u�������t�g�Ƀp�g���[�����������v�Ƌ����Ă���邩��A���Ɍ������Ă���Ƃ����\�z���ړ����Ă͈�����������̂������B
���R�A�G�����t�g����ł́u���т���Ɛm������܂����H�v�ȂǂƏ����W�߂邪�A��������X�L�[���m��s�����Ă��邩��A�����ȒP�Ɍ����鎖�͂Ȃ��B
���ǁA�����ɉ��։���čs���Ɓu�������t�g�̉��������ł��傤��Ƃ��u�����͊����Ă͂����Ȃ���ł���v�ƃp�g���[���Ɏ�����̂����A�u�o�J�A����ȏ�����킯���Ȃ����낤�A��Ȃ�����Ȃ�����ƌ�����X�̌��t�ɁA�X�L�[�w�Z�̃����o�[�S�����������̂������B�����t�������ł���A�݂�ȉ�X�̂�鎖�͒m��s�����Ă���B�ߌ�ɂȂ�Ɩ���̎Ⴂ�O��1������̂ŋ����ɗ����B�搶���̓��b�X�������邽�߉�X�������鎖�ɂȂ�B
���̎����̓��b�X���P�ɏ����������������̂����A�ꏏ�ɕ����Ă������т���́u�킩��₷���A�ȒP���Ȃ��v�ƌ����Ă����B���̎��A���т��̔N�ɂ���������b�����̂����A���̎��͂킩���Ă��炦�Ȃ������B�@
�m����1���Ƃ�2���Ƃ����i����B�����Ă����Ƃ����ʂ����邪�A����������Ȃ��̊��o�����̎��M�Ƌ��Ɋm���ɃA�b�v�������ɑ��Ȃ�Ȃ��B�����ɂ킩��Ȃ����o�������Ƃ͎v�����A�����Ă����邱�Ƃ͂Ȃ��B�K�����Ȃ��̊��o�A�b�v�Ƌ��ɗ����o���鎞������Ă���B
�@�@�@�@�Ƃɂ����ڂƎ��ɏĂ��t����
�@���āA���̔N����p�g���[���ɐV�l�������Ă����B���ɂ���y���ł����̂��B���Z�𑲋Ƃ��A����ɏA�E������ҒB�Ŏ�(1��)�A�����A�a�O(1��)��3�l���B
���쑺�ł̓X�L�[��̑��A�z�e����N�A�n�E�X�ȂǁA�Ƃɂ������낢��Ȏ��Ƃ�W�J���Ă���B�������Ƃ͂����A�����ɔz������邩�͂킩��Ȃ��B�X�L�[��͊ό��ۂ���̂ŁA�֎�Ȃǂ͉ď�z�e���œ���12���ɂȂ�ƃX�L�[��ւ���Ă���̂��B
����Ȓ�3�l�̎�҂͏��������҂���A���ŃX�L�[��֗���悤�ɂȂ����B�{���̎d�����x�݂̓���i�C�^�[�ŗ��K���āA���i������čs���̂��B��Ƙa�O��1���������Ă����������͉����Ȃ������B���̑��ɂ��A�q���̍����狣�Z�X�L�[�Ŋ��Ă�����w���A�q�v(1��)�a�O(2��)�Z��A�����ĔV��(2���j�̓��A�V�����p�g���[�������邱�ƂɂȂ��C�ɓ��₩�ɂȂ����B�݂�Ȓ��w�����炢��1����2���ɍ��i���Ă����B
��ɔV����������5�l�͊F�A�w�����⏀�w�����ɂȂ�B���ł��A�q�v�Ƙa�O�̌Z��́A�f�����X�g���[�^�[��ڎw���I�茠�ɂ��o�ꂷ��悤�ɂȂ����B�q�v�͋Z�p�I�̖{�I�ɉ��x���i���A�a�O�̓f���I�܂Ői�B�ɂ������f���ɂ͂Ȃ�Ȃ������̂����A���ŃX�L�[�G�������Ă̓n���n�����Ă����̂��o���Ă���B������3�l�Ƃ��X�L�[���ŁA���ɔV���̓W�����v�̑I��ɓ]�����Ă�������A���낢��Ə킹�Ă��ꂽ�B
�ٓ��X�L�[�w�Z�ł́A��{�I�ɁA���w�����ɍ��i����܂Ńp�g���[���Ƃ��ė��K���Ă����B�X�L�[�Z�p�͂������~�}�@�́A�����̏��h�m�ŏ��w�����̉|�{����ѐD����B���u�K���鎖�ɂȂ�B���i�͑����⎄���Ⴂ���������ɁA����̎d���ƂƂ��ɋ����Ă����̂������B
���̎����w�����̎��͍Z������u�Ⴂ�O�����w���������܂ł͑S�����O�̐ӔC���v�ƌ����Ă����̂ŁA�ނ炪����Ƃ��ł���������܂킵�X�L�[�������Ă����̂������B
�����Ɏ����̏�B�̂��ߕq�v�B������ƈꏏ�Ɋ����Ă����B������Ȃ��X�L�[�͂����Ə�肭�A���w�����Ƃ����Ă��ނ�ɋ����鎖�ȂǂȂ��B����Ƃ���Ύ��̐l�Ԃ̑傫���������鎖���炢���낤���B
����͏�k�����u�����Ă���v�ƌ����Ă��ނ�����܂������邱�Ƃ͂ł��Ȃ�����A���̊��o����납����čs�����������B
���̍��͕����̓p�g���[���y���̓X�L�[���t�Ƃ��������ŁA���b�X�����I���Ƃ����p�g���[���̃��b�P�ɒ��ւ��Ⴂ�A���Ɗ���B�i�C�^�[�ɂȂ�搶�������C���n�߂�Ǝ�ҒB��a���A�q�v�����Ɗ���̂����ۂ������B
20�ŏ��߂ăX�L�[���o�����Z�o���̂Ȃ������A�ނ炩��z�����鎖�͂����������B�ނ���X�L�[�w�Z�Ō�����Ɓu�����s�����v�ƌ����ẮA������蒅�ւ������Q�����f�֘A��o���̂������B4�l�Ń��Y�������킹�Ċ������肵�Ȃ���A���̃G�b�W�̎g������̂̎g�������A�����̖ڂƎ��ɏĂ��t���ė��K����悤�ɂ��Ă����B���̂��Ԃ��ɂ͎��̐Ȃł̉���|�Ȃǂ������A�u�����w��������ăf���ɂȂ�v�ƌ����Ă͂͂��ς�������̂������B
�@�@�@
�@�N�����ē�������ʂ��
���������Ă���ƁA���������Ă��u�͂��v�Ɠ������K�𑱂���p���A�܂�ł����֗������̎����𑼂̐l�ɂȂ��Č��Ă���悤�������B
���ꂪ�x�݂̓���i�C�^�[�ɂ���Ă��Ă͗��K���Ă����B�ޓ��͎d�����I����ƐH�����Ƃ炸�ɃX�L�[��ւ���Ă���B�����g��5��30�����ŏI�p�g���[�����I����ƁA�[�H�����6���ɂ̓Q�����f�ɏo�Ă����B���܂ɂ͔��ċx�݂�����������B
�i�C�^�[�ł͉���l�����Ȃ��l�ߏ��ɑҋ@���Ă��Ă����͏��Ȃ��A���̂悤�ɃX�L�[��S�̂ł͂Ȃ��A�ꕔ�̃Q�����f�݂̂����璼�s����ɂ��Ă����Ԃ͂�����Ȃ��B����ł������̒��ʼn��������߂Ă����������̂��낤�A�l�Ԕ�ꂽ��v���悤�ɏ�B���Ȃ��ƁA�����ɂȂ��ăT�{���Ă��܂�����B
�ޓ��̓Q�����f�ɏo��ƈ�l�ŗ��K���Ă��鎄���݂��A���K���n�܂�B
�����������g���A�����̊��o����ԑ�ɂ��ăX�L�[���o���Ă����̂ŁA���܂�J�b�R�̎��͌��킸�A�Ƃɂ������Ԃ�������Ȃ��悤�ɁA��������J�����_�ɂ��ċ����Ă������B
�����͏������o�������A���̋����������������̂�������Ȃ����A�����^�[���̂��тɃs���R���A�s���R���Ƃ����V������Ȃ�����Ȃ��̂ŁA�w���ɖ_�����Ă�����B����ł����G�ȕ\��Łu�L��������܂��v�ƌ����Ċ����čs���̂������B
�@���A���ɃX�L�[�N���u�̉��Ȃǂ𐿋�����͔̂ނ̎d���ŁA�������ɓY���Ă���莆�́A�t���l����n�܂�A�ٓ��X�L�[�N���u�����ǁA�r�`�i���w�����@�����@�����ŏI���̂ł���B
�w���ɖ_������ꂽ�肵�Ȃ���A���̊��o��̂Ɋo�����܂������̕��ɂ��鎖�ɂ���āA�K���C���X�g���N�^�[�ɂȂ��̂��B
��͉��������Ă��킩��Ȃ��ƌ����悤�Ȋ�����Ă����B�����������Z���Ɂu�����Ă鎖�킩�邩�v�ƕ�����u�����ς�킩��܂���v�Ɠ����A�����^�����Ċ����Ă��������������������v���o�����B�܂������̊��o���Z�p�ɒǂ����Ȃ��̂��������Ȃ��ē�����O�A��肭�Ȃ�ΕK������悤�ɂȂ�B
���͂Ƃɂ�����U���ɂ���Č����A�^������ނɁu���̂��ׂ�́A����Ȃɓ����ĂȂ����H�v�ƕ����Ɓu���������Ă܂����v�Ɠ�����B�u�}���͑S�R�����ĂȂ��棂ƌ����Ă͉��x���������𑱂���B���i�I�ɂ��m���r�����Ă����ނ��R�c�R�c���K�����č��ł͗��h�Ȏw�����ł���B
�@���q�@�a�O�͎����w�����̔N�ɏ��w�������������s���i�ɂȂ��Ă��܂����B���̔N�͐Ⴊ���Ȃ��A�i�C�^�[�̉c�Ƃ��o�������K���܂܂Ȃ�Ȃ��N�������B�d�����I���A�X�L�[�w�Z�̌���ߕ����Ńr�[��������ł���ƁA8�������Ǝv���A
�@�a�O�u����ɂȂ�܂����i������j�v
�@�m�@�u�ǂ������v
�@�a�O�u�X�L�[�w�Z�̌��݂��Ă��������v
�@�m�@�u�����Y�ꕨ���v
�@�a�O�u�����A���K���悤�Ǝv���āv
�@�m�@�u�悵�A���Ă��v
�������ĔނƎ��̎Ԃ�����ׁA���̃��C�g�ŃQ�����f���Ƃ炷���X�L�[��S���ł́A�ق��50�����̋��������x�����x�������Ă���̂������B�ꎞ�ԂقǃA�h�o�C�X���Ă������������ɖ߂��Ă���A�ǂ̂��炢�̎��Ԃ����������낤�A����Ԃ��ɗ���ނɃr�[���𒍂��Ȃ���
�@�m�@�u���K�ł��Ȃ��đ�ς����ǁA�K�����O�͍��i�����v
�@�a�O�u���v�ł���ˁv
�@�m�@�u������O���A�����������������P�Q�O�_�o�����v
����Ȓ��q�ŗ���������������܂��̂������B�c�O�Ȃ���ŏ��̎ł͕s���i���������A����ȃX�L�[���t���a�����Ȃ��͂����Ȃ��E�E�E��x�ڂ̎Ŕނ͏��w�����ɂȂ����B
�V����1����w�����ɂ́A�܂������������Ȃ��悤�������B
�������q���̍����狣�Z�X�L�[�𑱂��Ă������A�������鎖�����l���Ă��Ȃ������̂��B���͎����̗����̎d����b���������A�X�L�[�͑����������ق�����肢�A�Ȃ�Ό��肾���đ������ق��������_���o�ē��R�Ȏ����B���̔V����1���ɍ��i���鎖�͊ԈႢ�Ȃ��B�������A����360�_�͒������Ȃ��Ɖ��x���������̂������B
�������Ĕނ�1����w�����ɋ��������ĂA�q�v��a�O�Ƌ��ɁA�����ٓ��X�L�[�w�Z����f�����X�g���[�^�[���a������̂ł͂Ȃ����ȂǂƎv���A���̐��E�Ɉ������荞��ł�낤�Ǝv���Ă����̂��B���ǔނ�1�������鎖�ɂȂ�A���̎v����ɂ͂܂��Ă��܂����킯���B
�u�m����ɂ͐�ɕ����܂���Ɖ��x�������Ȃ���A����Ɍ������Ă������B���j���Ƃ������Ŏ��͔ނ̊�������鎖�͏o���Ȃ��������A������i�����B�������R�T�X�_�A�킸���ɂP�_����Ȃ������̂��B�������ޔނɁu���ꂪ���肾��Ɖ��x���������̂������B
������u�m����ǂ�������A�����Ɠ_���o��̂ł����v�ƕ����Ă����B���͓��S�A���߂��߂ƌ������Ƃ��낾�����B�u�V���A�ł��^�C���łȂ��Ɣ[�������Ȃ����낤�v�ƕ����Ɓu����ς�_���̍���������肢�̂�������܂���A��b�X�L�[�͂����������̂ł��傤�B�Ȃ�ƂȂ�����悤�ɂȂ��Ă��܂����B�����͑�l�ɂȂ�����ł����ˁv�Ɠ������̂������B
�������Ă܂���l�X�L�[�w�Z�̉a�H�ɂȂ��čs���̂��B���ǔނ͂��̐�ɂ͐i�܂Ȃ������̂����A���̎��͖{�C�ɂȂ��Ă����Ǝv���B�����āA�a�O���P�����������A��͂蕨��������B�R�U�U�_�A���̂R�U�O�_�́A��������X�V�����B�ޓ��̓X�e�b�v�^�[���Ȃǂƌ����ė��K���Ȃ��B��X���Q�C�R�x�����Č����Ă��ƁA�͂邩�ɍ��������Ő^�����Ă��܂����A���Ƃ��Ǝ����Ă���|�e���V�������Ⴄ�̂��B
���ꂩ��o�b�W�e�X�g�����悤�Ƃ���F����Ɍ��������B���Ȃ����ςݏd�˂����̂�����Ɍ����A��肯��ׂ������Ƃ��l���Ȃ��Ă��K�����i����B�������A�_���ō��ۂ����܂�̂�����A�o���ꂽ�_���͑f���Ɏ~�߂Ȃ�������Ȃ��B���̎����s��������A���i�_���o�Ȃ������Ȃǂƍl���Ă͂����Ȃ��B�����������^�[���̎��s�ŁA�s���i�ɂȂǂȂ�͂����Ȃ��̂��B
�_��������Ȃ��̂́A���ׂĂɂ����đ���Ȃ��Ƃ�������ǂ��������Ăق����B���̎������������āA�����̊��o���čs���A����قǓ�����̂ł͂Ȃ��B�����ƊȒP�ɁA�����ƋC�y�ɍl���Ăق����B
���̖{�̒��ʼn��x�������Ă������A�F����͂��܂�ɂ���ڂɂ������߂��āA���������K���Ă��Ȃ����낤���H�X�L�[�͂����ƊȒP�Ȃ̂��B�ǂ̂悤�ȏł����S�ɁA�����ł����������悤�ɗ��K����悢�B�����ăX�L�[���t�B�͂��ł��A���̂��Ȃ��Ɉ�ԕK�v�Ȏ����A�h�o�C�X���Ă���邩��A�����M���ĂЂƂЂƂ̂Ɋo�����܂��čs���������B
�@�@�@�@������Ɨ��K���Ă���ΕK�����i�����I
�@���āA���̔N�A�t�����(�t�F�j�Ƒ��������w����������B�t�����͎w�����Ȃǂɋ������Ȃ��Ƃ��������������̂����A���̂܂ɂ������N�̎������w����������Ă��܂������ł��C�ɂȂ����悤�������B�������ނ�
�@�t�F�u�m�ȂS�R����Ȃ������̂ɁA���w����������ȁv
�@�m�@�u�t�������ȁv
����ȉ�b�������Ă����B
�ނ̓X�L�[�w�Z�̏C��������ŁA�d�C�W�ɏڂ���������ꂽ���̒S���҂ŁA�Ƃɂ����J�b�R�̎����C�ɂ��Ȃ���A�قƂ�ǂ̂��̂��Ă��܂��B�T�����[�}���œy���ɃX�L�[��ɗ��Ă̓p�g���[�������Ă������A��X�͕����ɉ����s���̈������̂�A��ꂽ���̂�����ƁA�ނ��������̂��߂ɂ��ׂĂ�u���Ă����̂������B�������������̎�(�ڂ�ڂ�̒��Îԁj�̃X�e���I���A�A�b�Ƃ����ԂɂW�X�s�[�J�[�ɂ��Ă��܂����B
�R���ɂȂ�t�����Ƒ����͌�����̐ΑŊێR�X�L�[��ւƏo�����čs���A�ٓ��X�L�[��ł͐�����Ȃ��m���r���Ƃ������킪�����Ă����B�����Ƃ����̓�l���s���i�ɂȂ�Ƃ͎v���Ȃ��̂ŁA�d�����I���Ɠ�l�̘b��Ŏ�������ł����B���ׂĂ��I��������A�d�b�����薳�����i���������`������A�c���Ă�����X�́A�������i�j���̉�����z�����̂������B
���̎��A�t�����͎d�����x�݂̓������������K���o���Ȃ��Ƃ������ŁA�O�ɂ����������V�����łT�ԂƂ����f���炵�����тō��i�����̂������B�q���̍����狣�Z�X�L�[�𑱂��A���Ƃ��Ǝ����Ă���|�e���V�����������Ƃ͂�����ςȎ����B�������O�ɂ͎�ڂ̗��K�����邯��ǁA�����́A�����������鎖��A�ǂ�ȎΖʂł��]�Ȃ������l���Ă��邾�����B
�F��������̎����悭�킩���Ăق����B���������܂�����A�@�̉��������Ƃ��낢��Ȏ�������������ǖ����ɍ��i�����B���̘b���̒��S�ɂ͂��������������̂ŁA�����F������Ȃ�ƂȂ������̎��̓C���[�W���Ă���������Ǝv���B
�ނ͎��قǂł͂Ȃ�����ǃX�L�[����肭�Ȃ��܂ܑٓ��X�L�[��ɂ���Ă����B�w�����ォ��u�ꍂ���ŃA���o�C�g���Ȃ���X�L�[�����Ă��āA�����Ė{�i�I�Ɏ��g��ł����킯�ł͂Ȃ��A�y�����X�L�[�𑱂��Ă����̂��Ǝv���B�����P�V�̎��ɏo��Q�O�̎��ɃX�L�[�������Ă��ꂽ�H�@���̎��͂Q������������A���ɂ��Ă݂�Α�ςɏ�肢�l�������B
�Z���ȂǂɌ��킹��Ђǂ������炵�����A��͂���K�����ď�肭�Ȃ������ɊԈႢ�͂Ȃ����A�ނ��܂����i�����ڂ̎��ȂǍl���Ă͂��Ȃ������Ǝv���B
�Ƃɂ����N�������Ă��Ȃ��V������鎖���D���ŁA�V��ɔ������V���v�[�����c�������ނɂƂ��ď�肢�A��肭�Ȃ������߂���������������Ȃ��B�Ⴊ�~�������̓��ɂ́A�}�ΖʂɎ���A��čs���ƑO�����点�A���Y�������킹�Ă͂W�̎��ɃV���v�[����`���A����������Ă����B
�u�m�A�X�L�[�͐V�Ⴞ���v�Ȃǂƌ����Ă͕`���ꂽ�V���v�[�������グ�A���ɂ��悾��𐂂炵�����Ȃ��炢���������Ȋ������̂������B���t�g�̉��ɗ�����������ƁA���łɎ����E���Ă��܂��Ă��鎖��m���Ă��Ă��A�E���U������Ă͊����čs���̂������B
�@��̗��������E���̂ɉ��l���̃p�g���[�������t�g�̉��������Ă��ẮA�V��ł���Ǝv��ꂩ�˂Ȃ����A���܂���������Ȋ�����Ċ���̂��������Șb��������A�����čs���^�C�~���O������B
�m�������P������������̔N�������Ǝv���B�p�g���[���͎d���ア�낢��댯�Ȏ��������B���̍��͐���������t�g�̉��Ƃ����Ă��A�{�P�b�Ƃ��Ă�����t�g�ɓ����Ԃ��Ă��܂����Ƃ����čl�����邩��A�[��̒��ł��Ƃ����Ɏ~�܂�����o���Ȃ��Ă͑�ςȎ��ɂȂ��Ă��܂��̂��B����������������̐Ⴊ�~�蒆���Q�����f�̒[�ɑ傫�Ȑ�݂��ł��Ă��܂����B����͐�Ƌ��ɋ����������������A�n�ʂ̐�ڂ���Ⴞ��������o���Ă��܂��A���R���̏�ɏ��Ε���Ă��܂��̂ő�ϊ댯�ŁA�X�L�[���[�̂��߂ɂ����Ƃ��Ă��܂�Ȃ�������Ȃ��B
���S�ɍ�Ƃ�����Ȃ�A���Ƃ��Ƃ̒n�ʂ̐�ڂɉ����ča���@���čs���̂����A��X��l�ł�����̂ł͉������������Ă��܂��̂ŁA���������낤�Ƃ������ɂȂ����B���[�v�����݂��̍��ɔ���A�����������Q�����f�����莄�����̋��ڂƎv����Ƃ��������A��̉������葬���ʉ߂��Ȃ�������Ȃ��B�_�����ߊo������߂�ƈ�C�Ɋ���n�߂��B
����̒��قǂ�ʉ߂������A���̑����͌����ɗ������B�������͂ň�����������̂������ŁA���̍��������낤���ăQ�����f�ɂ��������̂������B���̎��͒N�ɂ��b�����ɓ�l�Ŏ��s�����A�Z���Ɍ����Ύ~�߂��鎖�������Ă�������E�E�E�B����Ȋ����łƂɂ��������傫�Ȏd�����I��点�ẮA�X�L�[�̗��K������̂������B
������Ɨ��K�𑱂���ΕK�����i����̂����A�Ԉ��Ȃ��łق����B���K�Ƃ͌����Ď�ڂ���ɂ��������̂łȂ������A�킩���Ă������������B�����͐V������肽���ĐV�������K����A���x�]��ł��N���オ��V�������B����𑱂��鎖�ŁA���ꂼ��̎�ڂɑ��āA�����ƍ��������̋Z�p���g�ɂ��Ă��܂��Ă���̂��B
�@�����̊��o�̒��ő������邽�߂ɂ͉��������炢�����A���̎Ζʂ������悤�ɂ��邽�߂ɂ͉��������炢�������A��ɍl�����o���A�b�v������Ɠ����ɁA�Z�p���g�ɂ��Ă���̂��B�����āA����O�ɂȂ��Ă�������Ǝ�ڂ̎��𗝉�����悤�ɂ��悤�B���Ȃ������i���猟���ڂ���ɖڂ�D���āA���̗��K�𑱂��鎖�ɂ���āA�t�ɋZ�p�̕��������Ȃ��Ă��܂��Ă͂����Ȃ��̂��B���K�Ƃ͍ŏI�I�Ɏ����͂ǂ����ǂ̂悤�Ɋ��肽�������l���āA����Ɍ������ēw�͂��鎖���Ǝv���B
�@��X�͂܂��P���ɍ��i���邽�߂̃p�������^�[�����o���Ȃ������ɁA�V��œ]�Ȃ��悤�ɗ��K���āA�����B������B�P���ɍ��i���邽�߂ɕK�v�ȏ���肪�o����悤�ɂȂ�O�ɁA�R�u�Ζʂ�]���ɍ~��鎖��B������B���@�͉��x�����x�����鎖�������B�ŏI�ڕW�Ɍ����������x�����킷�鎖���A���K���Ǝv���Ă���B����̎�ڂ�����Ƃ����ăV���e���^�[������������K���Ă��A�R�u�Ζʂ������킯�ł͂Ȃ��̂�����A���K���@���ԈႦ�Ȃ��łق����B���ꂳ���ԈႦ�邱�ƂȂ�������ΕK����肭�Ȃ��A�����ĕK������ɂ����i�ł���B����ȗ��K�𑱂��Ȃ���A�X�L�[���t�ɍׂ����_�����Ă��炤�̂��������낤�B�����ăA�h�o�C�X���ꂽ������K����悤�ɂ��悤�B
�@�@�@�@�X�L�[���t���ē���H
�R����{�A�ٓ��X�L�[��̕������܂����B�Ⴊ�Ȃ��Ȃ�X�L�[��̉c�Ƃ��I�����鎖�ɂȂ�B���̃X�L�[��ł́A���Ȃ��ƌ����Ă��܂��\���ɉc�Ƃł���̂ɑٓ��͏I���Ă��܂����B���̍����������Ŏw�������C�����A�݂�ȂŎQ�������B���w�����ɍ��i���������͌��C��I���ΐ_�˂ɋA��B
���͂��̔N�̂U���A���߂ɓo�ꂵ���r�q����Ƃ̌��������܂�A���N���X�L�[��ɗ���邩�ǂ������킩��Ȃ��Ȃ��Ă����B�����āA�X�L�[���t�Ƃ������x�ɂ��A���낢��ȕύX���\�肳��A���̔N�̏��w�������i�҂͓���ŁA���N�̎w�������F�߂��邱�ƂɂȂ����̂��B
���́A�����Ƌ��Ɏł���Ǝv������A�������g�̎w�����̌��_�͐摗�肳��鎖�ɂȂ����B
�߂����b�ł͂��邪�A��X�̂悤�ɐ�̂Ȃ��n�����痈��҂ɂƂ��āA�X�L�[���t�𑱂��鎖�͓���B�n���̐l�����͎d���̋x�݂𗘗p���Ċ����ł���̂����A���Ȃ��Ƃ��_�˂��ォ��ٓ��X�L�[��܂ŋx�݂̓��ɒʂ��ȂǂƂ������͕s�\�ł���B�����̊�Ղ������ɂȂ���A������͋����čs�����ɂȂ�ɈႢ�Ȃ��B��{�I�ɑ������A���̔N���Ō�Ɉ��ނ��鎖�ɂȂ��Ă��܂����B
�X�L�[���t�ɂȂ鎖�́A�ꐶ�������K���Ė����ɂȂ��Ă��A����������ł͂Ȃ��Ǝv���B�������A�X�L�[���t�𑱂��鎖�́A�{���ɓ���Ǝv���B�ٓ��X�L�[�w�Z�ł��A�������Ƃ������ʂ͂����Ă��A�l���ٓ��Ŋό��ۂ��痣��Ă��܂��A��͂�x�݂̓����������o���Ȃ��Ȃ�A��u�t�Ƃ��ăX�L�[�w�Z�ɂ��邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B
����������Ă���̂͂Q�O�O�O�N�ŁA���ł͍Z�������Č��݉ے��ɂȂ��Ė����X�L�[��ɂ͂��Ȃ��B����⌤�C��ɂ́A�S���{�X�L�[�A���̐��ψ�������s���Ȃ�������Ȃ����A���ł��X�L�[��ɂ��ĉ�X�Ɗ����Ă������́A�����̘̂b���ɂȂ��Ă��܂����悤���B
����������Ő������Ă��āA�N�Ɉ�x����x�X�L�[�ɏo�����邭�炢���낤���A����ȊO�ł͎w�������C��Ŋ���̂������������B�������Ă܂�����������ԂɈႢ�͂Ȃ��B
�������w�����ɍ��i����������A�Z���͐��������ƁA�K���u�m�A��������߂Ă������A���O�����Đ��������邾�낤�B���w��������������A�{���ɂ���߂Ă��������v�ƌ��Ȃ̂悤�Ɍ����悤�ɂȂ����B�܂��ʂ̓��ɂ́A�u�����R�N���ɑ̂�a���Ȃ����H�Ă͖���̎d���������������Ȃ����v�Ƃ������Ă����B���̂R�N�ƌ��������͎����w�����ɂȂ�̂ɕK�v�ȔN����������������Ȃ����A�������̂R�N���o�߂�����A�Z���͎��ɉ����������̂��낤���B
���Ȃ��Ƃ����̐l�����̂��̂܂ł�S����S�z���Ă���Ă��������A�����\���Ɋ����Ă����̂͊ԈႢ�Ȃ��B
�@���̕ӂŘb�����ɖ߂����A���̌��C�ɍs���O�X�L�[��ł�
�@�Z���u�m�A�ǂ�������A�邩�H�@���肽����Α��̃X�L�[�w�Z�֔������Ă��v
�m�@�u���肢���܂��v���S�悻�ł���čs���邩�ǂ����s���͂��������A�܂��R�����߂��B���A��̂͂��������Ȃ��A�������̂Ȃ犊�肽���B�����Ďw�������C��s���閭�������r�̕��X�L�[����������B�w�����͖��N���C��ŁA���̋Z�p�����コ���w���ɂ�����������Ȃǂꂵ�Ă��āA���ꂪ�I���Α������_�˂ɋA��B
���C����I���A�ٓ�����Q�����������o�[�Ɨ��V�[�Y���̍ĉ�����ƁA���͍Z���ɘA����A�r�̕��o���r�X�L�[�X�N�[���Z���̂Ƃ�����������B�����̍Z���͎������w�����������Ƃ��̖ʐڊ��̓`�c�搶�������B�Z���́u���Ⴀ�m�A�撣���B�d�����I���������A��O�ɉƂɊ���čs���v�ƌ����ċA���Ă������̂����A���̌�p�G�ȋC�����Ŏ��͌��������̂������B
�@�@�@�@�l���ꂼ���������悤�ɃX�L�[�w�Z�ɂ����������B
�@�o���r�X�L�[�X�N�[���ł����b�ɂȂ鎖�����܂������́A�܂����낢��Ȏ���m�鎖�ɂȂ�B�����ł͑ٓ��̕z�{���A���w�������i�܂œ����Ă����炵���B�z�{����͏��w�����ɍ��i�������N����A�ٓ��X�L�[�w�Z�œ����悤�ɂȂ����B���傤�Ǔ����N�Ɏ����ٓ��ɍs���悤�ɂȂ�������A�������Ђł���B�����ĂQ�N��A�������w�����ɍ��i�����N�ɁA�z�{����͎w�����ɍ��i�����B
��Ƀo���r�X�L�[�X�N�[���ň�ԁA���𗝉����Ă���鎖�ɂȂ��J��C�u�t�͎w���҂�����Ȃ����A�ٓ��X�L�[�w�Z�։��x�����������肢�������A�z�{������͂��ߒN�����Ă���Ȃ��B�u�ٓ��X�L�[�w�Z�Ȃ匙�����v�Ɛ���Ɍ����Ă����B�ٓ��X�L�[�w�Z�͍u�t�����Ȃ��A�Ȃ��Ȃ��o�čs�����͓�����A���̂悤�ȃX�L�[�w�Z���m�̂Ȃ������Ȃ̂��B
�o���r�X�L�[�X�N�[���́A��C���͂��ߐ����̗L���i�҂��Q���肵�Ȃ��烌�b�X�������Ă���B����ɁA���ɂȂ�ƒʂ��̏�u�t�B���R�ɓo���Ă���B���̑��͑�w�̃X�L�[���⓯�D��̘A�����A�A�V�X�^���g�Ƃ��ē����Ă��邩��A�����Ȑl�����X�L�[�w�Z�ŐQ���肷�鎖�ɂȂ�A���͂Ƃɂ����ٓ��X�L�[�w�Z�Ƃ̋K�͂̈Ⴂ�Ƀr�b�N�������B
�R���ƌ����Ίw���B�͏t�x�݂ŁA���Ȃ����ł��R�O���ȏオ�Q�H�����ɂ���B�ٓ��ł͊זv���܂��������@�_����߂Ă���A�y���ɔ��̐l�B���W�܂鎞�ȊO�́A�����Ǝ�����ɍZ�����ڋʂ̃}�[���������x���������A�Z�����}�[������ƒ낪����A�ƂɋA����͑����Ǝ��̓�l�Ŗ���߂����������������B
�ٓ��X�L�[�w�Z�ł́u�����搶�v�ƌ����Ăѕ��́A���������Ȃ��������������Ȃ������̂����A�w���B�Ɂu�m�搶�v�ȂǂƌĂ����̂�����A�̒����y���Ȃ�悤�ȋC�������B�����ł́A�d���̂������Ē��H�Ɨ[�H���p�ӂ����B���H�͌��ő��N�����č�鎖�ɂȂ��Ă���B
��T�Ԃ�����Ƃ����̕��͋C�ɂ�������Ȃ���ł��܂��A�V�l�ɂ�������炸������Ԓx���N���čs���悤�ɂȂ��Ă��܂����B�{���͖�����������ŋN�����Ȃ������̂��B�m���ɐl������������ǂS���Ɏ��̋r���̂Ăɍs�����A�Q�O�O�{�߂��������悤�Ɏv���B
���̂W�����A�F����ɍs���P���ԂقǂŖ߂�A�P�O�����烌�b�X�����n�܂�A���b�X���������Ȃ��w���B�͗��K���A�[���ɂȂ�ƂS��������A�������K�ƌ������̗��K���n�܂�B��ԏ�܂Ń��t�g�ŏ����K���Ȃ���~��Ă���̂����A�S���S�����قǂ���A�����Â��Ȃ�U�������܂ő����̂ł������B
���̎��Ԏ����w���B�ɋ����鎖�������A�ނ�ɂ͂������Ȏ������点�Ă����B���i����l���������W�ł��܂肨�����Ȏ��͂��Ȃ��悤�ŁA�����v���b�V���[�������Ă��ƊF�����ɓ]�Ԃ̂Ŗʔ��������B�F�A����킩�炸���̐^�������Ċ����Ă͓]��ł������A�����̊��o�ŗ������鎖���茾���������̂ŁA����I�ɏ�B����w���������B
�����̏�B���킩��Ɣޓ��͊��ӂ̋C�������̉���|�ŕ\���Ă����A�|�B�҂Ȋw���������{���Ɋy�������X�������B
����Ȃ�����A�����搶(�P���j�Ɉ��݂ɍs�����ƗU��ꂽ�B�����搶�́A���낻���N���}���悤���Ƃ����N��A�x�݂̓��͎ԂŒʂ��Ă���x�e�����X�L�[���t�ŁA���̂��炩�Ȏw���ɂ̓t�@�������������B���͂R�����Ƀ��b�X�����I����ƒ��ւ����̂����A��������B�̓X�L�[�E�F�A�̂܂܂Ȃ̂ŁA�u���ւ��Ȃ��̂ł����v�ƕ����Ɓu���������ԑq�֍s���̂�����A��������܂��傤�v�ƌ����̂ŁA�����Ăђ��ւ���������̎Ԃɏ�肱�B
���v�S���A�P���Q���A���w�����Q���Őԑq�X�L�[��ɓ������A�X�L�[�����낷�Ɓu���͍����A�m����ɋ����Ă��炨���Ǝv���ėU������ł���ƌ����A���ދC���X���������͋C���������߂�̂������B�ނ炪�����ɂ́A���͑��̃X�L�[�w�Z���痈�āu��������Ⴄ�悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��v�ƌ����̂ŁA���̊��o�͗]�����ƂȂ��`�����B�X�L�[���t���������l�B������A���̌������͂����ɗ������Ă��ꂽ�悤���B���ǂW�������܂Ŋ���A�������֍s���A���čs���̂������A�����������ȒP�ɍl���Ă��鎖�ɋ����Ȃ�����{���Ɋ��ł��ꂽ�B�A��̎Ԃ̒��Łu�����͏��������āA��������ł������Ƃɂ��ĉ������v�ƌ���ꗹ�������̂������B��͂�l���������������K�����ł͖����ł��Ȃ��ʂ��������̂��Ǝv���B�@�@�@�@
�@�@�@�@������͗ǂ��킩��Ȃ��̂ł����H
��ɂȂ�ƕ��Ƃ̊w���B��(�o�b�W�e�X�g������҂�����j�ǂ����₵�ɗ���A�u�m�搶�A�V���e���^�[���͂ǂ̂��炢�J���o�������̂ł����v�ȂǂƗ��邩�獢���Ă��܂��B���������u������͗ǂ��킩��Ȃ��̂ł����v�Ƃ������̂�����A��C�����ꂪ���ȂɂȂ��Ă��܂��A���̂܂ɂ��u������͗ǂ��킩��Ȃ��̂ł����v���X�L�[�w�Z�̗��s��ɂȂ��Ă��܂����B
�X�L�[���J���̂����āA���̎Ζʂ�X�s�[�h�ɂ���ĕK���Ⴄ�̂��A���Ȃ������₷�������J���Ηǂ������Ȃ��̃^�C�~���O��\�����������ɂ���Ē��߂�������̂��B���������āA�ǂ̂��炢�J���o�����������l���ė��K������A�X�L�[�ɂ��Ȃ��̍l���Ă��鎖��͂��`���Ƃ���ɏ����K�����鎖������B���ꂪ�o����悤�ɂȂ�A
�u�����A�J�����v�Ɩ��߂������ɑ̂��ȒP�ɔ������Ă����̂��B
�@�@�@
�@�@�@�N�ׂ̈ɃX�L�[���t�͕K�v�Ȃ́H
�@������J��C�����̖{��ǂ�A�R�c�̓d�b���邩������Ȃ��B�ނ͓����S�R�������Ǝv�����A�Ƃɂ����ڂ�������(�ڂ�����������������Ȃ�)�̂��傫���A�ꌩ���Ă��̋̐l�ɂ��������Ȃ��B���k����B�������|�����Ă������낤�B���̂܂܂ł͍R�c�̓d�b���肻���Ȃ̂Ŗ{���̂Ƃ���������Ă������B
�@�ꌩ�|���̂����X�L�[��S���爤�����M����f���炵���w�����Ȃ̂��B���Ǝ������ނƂ��ł��A
�u�m�����A���ꂾ����������X�^�b�t������̂ɁA�܂Ƃ��ɃX�L�[����������z�����Ȃ����v�ƌ����Ă͒Q���̂������B���������ł͏C�w���s�ȂǂŖK���X�L�[���[�������A�Z�������ɂ͂�������̋��t���K�v�ɂȂ邽�߁A��w���ɂ��肢���鎖�������B���̐l�B�ɂ͋������K�ȂǂŎw���̎d���������čs���̂����A��͂�L���i�ҒB�ƈႢ������������B
�@�L���i�҂ł��o����l�̂ق������Ȃ���������Ȃ����A��C�͂��ł������鑊��̂��Ƃ�����l���Ăق����Ƃ����������������̂��B�Ⴆ�u�R���̃V���e���^�[��������Ă���������ȂǂƗǂ��������B�w���B�͉��Ō��Ă���Ă��邩��A��肭���낤�Ƃ��肷��B�������A�u�F�������郌�x���̐l�ɁA����Ȋ�������������Ă킩��킯���Ȃ��v�ƌ����̂������B
�R���̃V���e���^�[���ŁA�J���o�����X�L�[��f���������āA�s�^���ƃX�L�[�����낦�Ċ��鎖�ȂǗv�����Ȃ��B���̎������������̂��B�X�L�[���t�́u���߂��銊������߂�l�ׂ̈ɁA�����Ă����Ȃ�������Ȃ��v�Ɨ͐�����l�������B����������Ƃ̂���l�������Ǝv�����A���ׂĂł͂Ȃ�����ǃX�L�[�w�Z�ɂ���Ă͑O�����o���Ă����Ƃ��������B
���̊�������āu�������ȁ[�v�Ǝv���̂ƁA�u���̂��炢�ł����́H�v�Ǝv���̂Ƃǂ��炪�悢�̂��낤�B���́u���̂��炢�̊���ō��i�ł��܂���v�ƌ�������������Ă�����̂��悢�Ǝv���Ă���B�R���̃V���e���^�[���̑O�������鎞�A�ǂ��炩�ƌ����Ώ��߂���I���܂Ńv���[�N�Ŋ���A�������̃^�[���ɂȂ�O�ɏ��������X�L�[�s�ɂ��Ă��B
������������ɁA�u���̌�������肾�ȁv�ƐS����v����Ƃ�����Ɖ������C�����邪�A����ł����Ǝv���Ă���B��X�͎d�������Ă���̂�����A�����ł��҂ɗ����������C�����Ŏ��Ă������������̂��B�F����������̎��ɁA�O��������l�����̂悤�Ɋ����Ă��ꂽ��A�]�v�Ȏ��͍l�����ɑf���Ɂu�����̂ق�����肢��A���̒��x�ł����̂��v�Ǝv���Ď��M�������ăX�^�[�g���悤�B�����₽��Ə�肭����l��������u���̐l�͉����킩���ĂȂ���v�Ǝv���Čy���C�����ŃX�^�[�g���悤�A�Ƃɂ��������̂Ƃ��芊������̂�����ȒP�Șb�����B
�@�@�@�@
�@�@�@�@�����W
���܂ɂ͒��̗ǂ��y���V�����̃I�[�i�[�ɗU���ėV�тɍs����������B�����̃y���V�����ɂ́A����Ƃ����Ē��[�Ɏ�`�������Ē��ԃX�L�[������l�B�����āA�����m�荇���̃y���V�����ɌĂ��������ł���ƁA�ߏ����炱�̂悤�Ȑl���W�܂��Ă���B
�^���ɏ�B��ڎw���l�B�̓X�L�[�w�Z�̃V�[�Y�������āA���ꂱ�������̂悤�ɃX�L�[�w�Z�ɗ���̂��B�Ƃɂ�����肭�Ȃ肽���Ďd�����Ȃ��̂������B���ɂ́u���A�R�[�`�̔ǂɂȂ�����������܂��v�ȂǂƂ�����������B���R�X�L�[���t�ɑ��铲������邩��A�ޏ��B�̃X�L�[���t�ɑ���C���[�W������Ȃ��悤�ɁA���ƂȂ������肷��̂������B�u�R�[�`�A�ޏ��ɂ��ĉ������v�Ȃǂƌ�������邱�Ƃ�����B
���鎞�́A�u�m������ɗ{�q�ɗ��Ȃ����H�v�Ȃǂƌ���ꂽ���Ƃ��������B���ق̖����X�L�[�w�Z�ɓ���A���̔ǂɂȂ�C�ɓ����Ă��܂����炵���B�����m��Ȃ��l�́u�X�L�[���t�̓��e�邩��A�V��ł���ɈႢ�Ȃ��v�Ǝv����������Ȃ��B�������A�قƂ�ǂ̏ꍇ�A���b�X�����I���Ύ����̗��K���B���ɂ͗V��ł�l�����邩������Ȃ����A�����͂����Ȃ��B�j�����珗���͍D��������ǁA�X�L�[�͂����ƍD�����B
���Ȃ��Ƃ��V�[�Y�����̓X�L�[�̎��œ��������ς�������A�X�L�[���t��_���l�̓��b�X�����I����Ă���A�������(�����Ă���邩�ǂ����킩��Ȃ����j�V�[�Y���I�t�ɘA�������ق����`�����X�͍������낤�B�Ɛg�̃X�L�[���t�Ȃ����Ă���邩������Ȃ��I�@�@�������A����͋G�ߘJ���҂�����A�����̈�������߂鎖�͂�����߂��ق����ǂ���������Ȃ��B
�@�@�@�@�X�L�[�w�Z�͑̈��n�̃m���I
���āA��C�͕|��������Ă���Ə��������A���Ɠ����N�̃R�E�X�P(�w�����j�ƃR�E�C�`���E(��N���̎w�����j�����Ɗw�����N�ɂ́A���낢��Ȏ������炵�čs���̂������B�܂��A�₭���f��̂悤�Ɏ�C�̎��́u�I���W�v�ƌĂсA��X�R�l�́u�I�W�L�v�w���B�̃��[�_�[�̃}�T�V�́u�A�j�L�v�B����������Ƃ��̓h�X�̕��������łȂ�������Ȃ��B
�������C�ɓ���Ɓu�I�W�L�A���炵�܂��v�ƌ����ĂR�l���炢����ɑ����A�̂����Ă��ꂽ�肷��B�����o�J�Ȏ��Ǝv���邾�낤���A���E����u�����ꂽ���E�Ő��������߂����̂�����A�j����Ŋy�����V�Ԏ�����l���Ă���̂��B
�������t�B�͎����ʂ̗�����ʂ��Ă���̂ŁA��Q�鎞�A�ޏ��B�ɓ����Ń��j�t�H�[��������ĐQ����A���ĐQ���肷��̂��B��X�I�W�L�R�l�͎��ɐ����ƁA�w���B�Ɂu���Ō��Ă邩���{�����ė����v�Ȃǂƌ����ĈÈł̒��X�L�[��S���œo���čs���̂����͂���Ɛ�ɐQ�Ă��܂����肷��B���������ɂ����āA�邾���i�C�^�[�̃Q�����f����������A�ǂ�������킯���Ȃ��B
����ł��������݃X�L�[�̘b���肷���X�̌��ŁA�������𗧂ĉ������������Ƃ��Ă���ޓ��͒��ւ��ďo�čs���B����Ȏp���������Ă��邩��A�����ɂ͂܂��ނ����肭���悤�ƕK���ɂȂ�̂��B
��y�B���J�̒��A�т���G��ɂȂ��Ċ��鎄�B���悤�ɂт���G��ɂȂ�Ȃ���A���܂ł����Ă��Ă��ꂽ�悤�ɁE�E�E�B
�@�@�@�@����|
�@�w���B�͉�X���X�L�[��������ƁA�K���ɂȂ��Ă�������Ă����B���ꂪ�܂������܂����B�������ݐ����Ă���Ɖ�X�́u���낻��A�����������ȁv�ƌ������t�����}�ɁA�|���I���Ă����̂������B�������ɐ�y�ɒb�����Ă���̂��ʔ����̂������B
���ł����j���͍ō��������B�S���ꎅ�܂Ƃ�ʎp�ɂȂ�A�u���[�C�h���v�̐��Ƌ��ɃQ�����f�����R�`�ʼnj���ōs���̂��B�X�L�[�w�Z�̑O����Q�����f�̔��܂ōs���ƃ^�[�����Ė߂��Ă���B���̃^�[�����Ȃ�ƃN�C�b�N�^�[���Ȃ̂�����킹��B���R�r�̊ԂŃu���u�����Ă�����̂���������̒��A���ڂ낰�ɕ����яオ���ď��]����B
����x���P�O�����̘b���������ʂ͓���A�C���������������ł���邩��A�S�[�������҂��畗�C��֔�т���ōs���B�����������ꂽ���͕z�c�̒��Łu�����͂ǂ�����ď�肭���Ă�낤�v�Ȃǂƍl���Ȃ���A�S�n�悢����ɂ��̂������B
���������X�L�[���t�̑f��́A����Ȋ����łǂ̃X�L�[��ł��卷�͂Ȃ��Ǝv���B�\�I�L���̂悤�Ŏ����X�L�[�A������j��ȂǂƂ����Ă͍���̂ŁA�قƂ�ǂ̃X�L�[�w�Z�ł͂���Ȃ��Ƃ͂Ȃ��Ƃ������ɂ��Ă������B
�����ɏ��������́A���̖��̒��ł̏o�����Ǝv���Ă������������B
�@�@�@�@�N�������킯�ł��Ȃ�
�S����{�A�S���X�L�[�w�Z���u�ꍂ���ōs���A�W���A�R�E�X�P�A�R�E�C�`���E�A�e�c�̂S�l���I��Ƃ��ĎQ�����鎖�ɂȂ����B����͖��N�V�[�Y���̏I���Ɋe�X�L�[�w�Z���S�l��g�Ńf�����X�g���[�V�������s���A������ɂ��̓_����A�|�[���̃^�C���ƏW�v���ꏇ�ʂ�������B
�R�[�X�ɂ͂Q�ӏ��ɃW�����v�䂪����A�S�l�̑I��̓N���X�����肵�Ȃ���A���̔������Ƒ��������������B��X�͑�J��C���R�[�`�ɒr�̕��ŗ��K�����Ďu�ꍂ���ɏ�肱�̂����A�c�O�Ȏ��ɃX�^�[�g���Ă͂��߂̃W�����v���I�����Ƃ��A�e�c���G�̐x�т���Ă��܂����B�ǂ����V�[�Y��������ɂ߂Ă����炵���B���Ղ�̂悤�Ȃ��̂����疳�������鎖���Ȃ��̂�����ǁA�ނ͂܂��߂Ȓj�����疳�����Ă��܂����̂�������Ȃ��B
���ǔނ͂��̓��ƂA���čs���A�����͎c�����R�l���|�[�������肷�ׂĂ��I�������B���т��U���Ȃ������̂͌����܂ł��Ȃ����낤�B���������X�L�[�w�Z�̔[��s���A���߂��ɓ����������̃����o�[�́A�q���̂悤�Ɋ���̂������B��ɂȂ�ƂT�O���قǂ̑剃��Ńw���փ��ɂȂ�A�V�[�Y���͏I���Ă������B
�����X�L�[��ɖ߂�ƁA�X�L�[�w�Z�̉c�Ƃ��I���A�������肩���Â����Ă��āA���̓����Ō�Ɏ����A�鎖�ɂȂ����B���̖�݂�ȂɁu�ٓ���߂ăo���r�ɗ����B�v�Ȃǂƌ���ꂽ�B
���ɂƂ��Ă�������ϋ��S�n�ǂ��A����͉����Ȃ��Ƃ��낾�B�����̎��Ԃ����Ă������邵�A�����������B
�ٓ��X�L�[��ł́A�W���ɃQ�����f�����ĉ��ƂX���T�O���ɒ��ւ��ăX�L�[�w�Z�ɏo��B�P�Q���ɏI���H�����ς܂��ƁA�P���R�O���Ɍߌ�̃��b�X�����n�܂�O�ɁA������x�Q�����f�����Ă��Ȃ�������Ȃ��B���������ăX�L�[�C��E�����͏o���Ȃ��B�R���R�O���Ɍߌ�̃��b�X�����I����ƁA�����ɒ��ւ��ăp�g���[���̎d���ɖ߂�A�i�C�^�[�ŗ��K���ďI���ƁA����Ԃ̃I�y���[�^�[�Ƒł����킹������B��̂Ȃ��Ƃ��ɂ͓O��Ő�������Ă��鎖������B
�ł́A�o���r�X�L�[�X�N�[���͂ǂ����낤�B���H���ς܂��Ɗ���ɍs���̂��ǂ��A�x��ł���̂��ǂ��A�ߑO�̃��b�X�����I����ƒ��H��A���Q�ł����Čߌ�̃��b�X���Ɍ������B�R���R�O���Ɍߌ�̃��b�X�����I����A�S���R�O����������K���V���O�ɗ[�H�A��������ŐQ�Ă��܂������B�����Ƃ����ł������킯�ł͂Ȃ��̂��Y�݂̎킾�낤���B�Z�����͂��߂��N���(�{��ꂻ����)�̊F����ɂ��������Ă������A�Ⴊ�Ȃ��Ƃ������͂Ȃ��B
�X�L�[�̗��K������̂ɂǂ��炪�K���Ă��邩�ƌ����A�����肾����ǎd��������̂ɑҋ��������̂͂ǂ��炩�ƌ����A�����͖����������B�ٓ��X�L�[��ɖ߂�A�����̍u�t�Ƃ��ė��鎖�͂����Ă��A����������ƃo���r�X�L�[�X�N�[���ł́A�y�������������͍Ōォ������Ȃ��B�����Ȃ�A��������ƂS���܂ŃX�L�[���o���鎖�ɊԈႢ�͂Ȃ��B
���낢��Y�݂���������ǁA�ٓ��X�L�[�w�Z�ɖ߂邱�Ƃɂ����B�ٓ��ɖ߂�ƂɊ���������Z���́u����J�������ȁB�v�ƌ����āA�����̂悤�Ɍ}���Ă���A���x�����x���u����ꂳ��A�݂�Ȃɉ������Ă���������H�v�ƌ����Ȃ���r�[���𒍂��ł����̂������B�Z���Əo����ĂS�N�ɂȂ邪�A���̓��̍Z���͍��܂Ŏ��̒m��Z���Ƃ͏����Ⴄ�悤�ȋC�������B
���̐l�Ƃ̏o����Ȃ���ΐ�ɁA���͎w�����ȂǂɂȂ�Ȃ������͂����B�X�L�[�ɑ���l������A�������܂Ŋw�ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B�����đ��������킯�ł͂Ȃ��A�o�J�Ȏ����茾���Ă��钆����A���̂��ׂĂ��z�����Ă����B�������A���̃X�L�[��ɍs�����鎖���{�ӂłȂ����́A���̒Z�����t��U�镑������A�ɂ��قǓ`����Ă����B
�N��������ł��Ȃ��A�Ⴊ�~��Ȃ����������̂��B�ٓ��X�L�[�ꂾ���ł͂Ȃ��A��������Ɖc�Ƃ��Ă���X�L�[�������̂ɁA�Ȃ���̂Ȃ��X�L�[�ꂪ����̂��낤�B���R�n���ɂƂ��Ă��X�L�[��͑傫�Ȏ�����������A�c�Ƃł��Ȃ��̂͑傫�ȒɎ�ɈႢ�Ȃ��B����Ɠ����ɁA���̕Ћ��ŋꂵ��ł���X�L�[���t�����đ����B
�����i�ݎ����u�f���ɂȂ�v�Ȃǂƌ����o������A�����̍Z���ɖ߂�u�����Ȃ�Ȃ������̂ɁA�m���Ȃ��킯�Ȃ����낤�B�v�ƌ����čZ���̘͐b������̂������B
�X�L�[���t�̂��ׂĂƂ͌���Ȃ����A�F���������Ē��킵�čs���B���̒��Ő�y�B�̋������ė��K�𑱂���B
�ڕW���B���ł��Ȃ��l�������̂́A�킩�肫�������Ȃ̂����A�����̗��K�ʂ�����Ȃ�������������Ȃ��B���ׂĎ����̐ӔC���B�Ⴊ�~��Ȃ����܂Ŏ����̐ӔC�Ƃ͌����Ȃ�����ǁA�����A���Ȃ����M���[���ł�����K�����悤�B�������ɂ͏�肭�o���Ȃ�������������ǁA���Ȃ����w�͂�ςݏd�˂čs���ΕK�����ʂ������Ă���B
�@�����X�Ƃ����Q�����f�̌�����ٓ��X�L�[��ŁA�Q���قǂ̂�т�Ƃ������͑��ւƌ��������B
�@�@�@�@���Ɏw��������̔N������Ă����I
�P�X�W�W�N�P�Q���@�ٓ��X�L�[��ʼn߂����̂��T�V�[�Y���ڂƂȂ����B�����킩�炸�A�w�����Ƃ����ڕW���������킯�ł��Ȃ��A�����l�Ƃ̏o��Ɉ������܂�ĂS�N�O�����ւ���Ă������ɂ����͖ڕW������B�w�������i�����ăf�����X�g���[�^�[�ɂȂ鎖���B
���_���珑���Ă��܂��f�����X�g���[�^�[�ɂ͂Ȃ�Ȃ������B�I�茠�ɏo�ꂷ�鎖���Ȃ��ٓ��X�L�[�w�Z�����ނ����B�������w�����ɂ͍��i�����B�Ȃɂ�������͂Ȃ��A������肭�Ȃ肽���A�]���Ɋ��肽���Ǝv�������������K�������ʂŁA�F����ɂ��K���o���鎖���B
�@���̔N���ё����͒���Ŏd���ɂ��A�w��������O�̈ꃖ����ٓ��ʼn߂����������܂�A�w�����҂͎��Ƒ����A�֎�A�t�����ɏG�B����̂T�l�ƂȂ����B�����@�G�B����͓����S�O�Έʂ������Ǝv���A�{���ɃX�L�[���D���Ō��F�p�g���[���̎��i�������X�L�[�̎�����l���Ă���l�������B���V�[�Y�����ߎS����������ǁA���̔N���܂���͍~��Ȃ������B�N�������鍠�܂ł̓X�L�[��Ńl�b�g�����肵�Ă������S�R�X�L�[���o�����A���܂�ɂ��܂�Ȃ����d�����Ȃ��̂�10���قǗV�тɍs�����������ꂽ�B
�@�@�@�@�������{���Ɋ���Ȃ������̂��낤��
���߂ăX�L�[�������̒r�ł́A���������Ă����R�����̎x�z�l�����b�W���n�߂Ă��āA�����b�ɂȂ����B�F����͕s�v�c�Ɏv����������Ȃ����A���\���낢��Ȑl�ɉ������Ă��Ēm�荇�������������̂ŁA�����̃X�L�[��ɍs���Ă����܂鏊�ƁA���ݐH���ɂ͍���Ȃ������B
�����łȂ���Ύ��ȂǁA�����͑����ɕn�R����������X�L�[�ȂǏo����킯���Ȃ��B�x�z�l�Ɗ���ɍs������{���ɋ����āA�u���̒m���Ă����肢�z�̒��ł��A�m��3�{�̎w�ɓ����v�ȂǂƑ�U���Ɍ���ꂽ�B���w�����ɍ��i�����N�ɂ���������ǁA����1���Ȃ̂ł��̎��Ƃ͐Ⴊ����Ă��邵�ō����B
�n�߂ė����̂�1�������獡�̂ق�����Ԃ͋߂��B
�@�Q�����f�̓r���Ŏ~�܂�ƁA�����œ]�B���̎Ζʂ͐K�ŃY���Y���ƍ~��čs�����Ǝv���o���B���߂Ċ�����2���̒��ň�ԍD�����������̂Ȃ�u�Q�����f�ł́A����Ȃɕ��炾�������ȂƎv�����B����₷�������ƌ����Ă��A�����Ƌ}�������L�������Ȃ��B
���ƂƂ��������͎�ւ�����Ă����������Ԃ���������A����݂�Ǝv���o���Ђ܂��Ȃ������B
��B���邽�߂ɂ͗��K���K�v�����A����Ȃ�̍l����������B�������A���Ȃ����l������ς��Ď��g�߂ΕK����肭�Ȃ�B��肭�Ȃ����Ǝv������A����������Ȃ������Q�����f�ɋA���Ă݂悤�B���Ȃ����ς��ΎΖʂ��ς��A���̎��͋Z�p�ɂ�������A�}�Ζʂ��������芊���悤�ɂȂ�����A�ɎΖʂɍs���Ă݂悤�B
���܂ŕ\���ł��Ȃ������ׂ����Ƃ��낪�A���Ƃ����₷���\���ł��鎖�ɋC�����͂������A��J���Đg�ɂ��������ȒP�Ȃ��ƂɎv����ɈႢ�Ȃ��B����肭�o���Ȃ�����ƌ����āA�����鎖�͂Ȃ��B�K�����Ȃ����g�̊��o���g�ɂ����Ƃ��ɂ͊ȒP�ɏo����悤�ɂȂ��Ă���I
�@�@�@�@��l�ɂȂ�ƖY��ĂȂ��H
4�����܂Ŋ����āA��X�̓V�����[���n�ɖ߂����B�A���o�C�g�⋏��7�C8�l����悤���B���q����̐H�����I���A�]�ƈ��̐H�����n�܂�ƁA�݂�ȃ`���`�����̎������Ă���B�d�������Ȃ��玄�̂��Ƃ͕����Ă���悤�ŁA�u�l�̒m�荇���̐m�N�A���w���������疾�����Ă��炦�棂ƏЉ�ꂽ�Ƃ���A�ޓ��̖ڂ̐F���ς�����B
���H���I����ƁA�҂����킹�̎��ԂƏꏊ�����ߎ��͈ꑫ��Ɋ���ɍs�����B�W�܂����݂�Ȃ́A�������ɖ��������Ă��邩���肢���̂ŁA����4�����܂ŃX�L�[�������ċA���čs���̂������B�r�����܂�ɂ��A�݂�ȋْ����Ă���̂ł킴�Ɠ]��ł������A�{�C�ŏ��Ă��܂����B
�u�킴�Ƃ�����v�ƌ���������������ǁA���܂�ɂ���Ԃ̂Ŗق��Ă����B�ޓ��͖{�C�ŏ�肭�Ȃ肽���Ǝv���Ă��邩��A�]�������ɁA���낢��Ǝ��₵�Ă����悤�ɂȂ����B
�Ō�Ɂu�������Ă�������킯�ł͂Ȃ�����A�����Ŋ��鎞�ɍ����������Y��Ȃ��悤�ɂ��Ȃ��ƃ_������B�̂��o���Ă��܂��ΖY��Ă�������v�ƌ����Ă������B
�X�L�[���t�ɉ����A�h�o�C�X����A��l�Ŋ��鎞�Ɍ��ʂ�Ƃ����l�������B���̓��Ƀ��b�X���������k�������Ă���̂��A���t�g�̏ォ�猩�����鎖������B���b�X�����͗ǂ��Ȃ��Ă��Ă��A���ɖ߂��Ă��܂��Ă���B
���肢������A�V�������o��m�������Ȃ��E�E�E��l�Ŋ��鎞���A�Y�ꂸ�ɑ̂ɖ��߂��Ăق����B����قǒ������Ԃ͕K�v�Ƃ��Ȃ��A���Ȃ��̑̂��o���ď���ɍČ����Ă����悤�ɂȂ�܂ŁA�����Ă������̎����B
�m���ɏ�ɖ��߂��Ȃ���A���ӂ��Ȃ��犊��͖̂ʓ|�Ȏ����B�������A�����̊����ς�����͎̂����������Ȃ��̂��B�������������������ăX�L�[�w�Z�ɓ���̂�����A���Ȃ��̑̂��o���Ă��܂��܂ł́A���Ӑ[�����K�𑱂��Ăق����B
�@�@�X�L�[��ɂ���ă��x�����Ⴄ�́H
���̌�A�ʂ̒m�荇����K�˂Ĕ����ɍs�����B����1����������N�̉ď�A����̐l�B�́A�u1���Ƃ����Ă��A�ٓ��Ȃ�ĕ����������Ȃ��X�L�[�ꂶ��_�����B����ς蔪���Ŏ��Ȃ���v�@�ʂ̐l�́u�u��ŎȂ����棂Ȃǂƌ����Ă����A�F����̒��ɂ����̂悤�ȍl�������l�����邩������Ȃ��B�������A������ɂ��Ƌ�������B
���w�����͂b�����F������A�w������A,B�����F������Ƃ����悤�Ɏł���Ƌ����Ⴂ�A���R���Z�Ɗw�Ȃ̎������č��i�����l�B��������ƂȂ�B���̖Ƌ��ɂ����N���C�����S���A��ɖڂ�b���Ă���̂��B���������āA����������1��������Ȃǂƍl����K�v�͂Ȃ��B����ł������łȂ���Ƃ����l������A����͂��̐l�̉��l�ςł���A�������͂Ȃ��B
���ɂ͏��w�����ɍ��i�������ɁA�u�����Ȃ�1�������Ȃ���v�Ƃ����l�܂ł����B�������A���̂悤�Ȑl�́A�����m��Ȃ�����������ʂɑ���ɂ��鎖���Ȃ����낤�B
��������X�L�[��ŕs���i�ɂȂ����l���ʂ̃X�L�[��ō��i�����Ƃ��Ă��A���ꂼ��̃X�L�[��̃��x�����ǂ��Ƃ������ł͂Ȃ��B���̐l���s���i�̌�A�K���ɂȂ��ė��K�������̊��o�������̕��ɂ��������Ȃ̂��B�ǂ��l���Ăق����A�e�X�L�[�w�Z�ł̓o�b�W�e�X�g�p�̍u�K�����Ă���ł͂Ȃ����B����͒P�Ȃ�q�ł͂Ȃ��B
����������ĐS����A�S���̐l�ɍ��i���Ăق����Ǝv���Ă���B���O�u�K�����āA�X�L�[���t�͍��i���Ă��炨���ƕK���ɂȂ��ċ����Ă���̂��B�����A���x���������悤�ɁA���̃��x���ɒB���Ă��Ȃ��l���Q�C3���O�Ɏ�ڂ����Ă����������Ƃ����āA���i�ł�����̂ł͂Ȃ��̂��B
�������S�������̃��x���ɒB���Ă���Ȃ�A���錟��ł͑S�����P���ɍ��i����̂��B�Ƃɂ����A���Ȃ��̊��o���čs��������ŁA���ꂳ���g�ɂ��Ή����̃X�L�[��ł��낤�ƊW�Ȃ��B
�@�����I���M�������Ă��Ȃ����R�c�R�c�Ɛςݏd�˂����̂�]�����Ă��炨���B
�w�����⏀�w�����́A�قƂ�ǂ�������̎��i�������Ă���B�猩�m��̃X�L�[���t�Ɂu���낻��Ă݂���v�ƌ���ꂽ��H�@�@�@
�@�����������肾�낤�B���Ȃ��̃��x���͊ԈႢ�Ȃ����i���C���ɒB���Ă���̂��B�S�O���鎖�͂Ȃ��A���M�������Ď��悤�B
�@�@�@�@�Ƃ�ł��Ȃ����I
�@���̌�A���ɂƂ��ďՌ��I�Ȃ��Ƃ�����A����I�ɏ�B���鎖�ɂȂ�B
�ٓ��ɂ́A����������肻���ȏꏊ�̘A����́A�u���Ă��Ă����B�����ցA�t�����A�����������B���́A�Ⴊ�~���ăX�L�[�ꂪ�I�[�v�����邩��A���ė����Ƃ����d�b�Ǝv������A�����ł͂Ȃ��A�����X�L�[��ōs����I�茠�\�I�ɏt����o��̂ŁA��l�ŐS�ׂ����痈�Ȃ����Ƃ����̂��B
�����������������ւƌ��������B�ނ����K�s���ɂ͈Ⴂ�Ȃ�����ǁA���w��������T�Ԃ��A�������҂��Ă��������낤�B���O�ɍ���������X�́A�R�[�X�̉����ɏo�������B���̎����̎d���͔ނ��T�|�[�g���邱�Ƃ��B�I��B�͑҂����Ԃ����������̂ŁA�ނ炪�E�����㒅���S�[���n�_�܂Ŏ����Ă������肷��킯���B
�}�ΖʃE�F�[�f�����̃R�[�X�̓J�`�J�`�ɓ����Ă��čō��̃o�[���������B���̂Ƃ��떈�������Ă������͐�D����
�u�T�|�[�g�̂ق����A�������肷��Ȃ�v�ȂǂƏt��������Ă����B�V�[�Y���ɓ����Ĕނ͂܂���x�������ĂȂ�����A��t�̎��Ԃ��肬��܂Ŋ����ďh�֖߂����B�y���r�[�������݂Ȃ���
�@�t�F�u�m�͐\�����݂��Ȃ������́H�v
�@�m�@�u�Ⴊ����W���j�A�̑����邶���A�Z�������N�͉䖝������āv
�@�t�F�u�\�����݂������Ă����Ηǂ������̂Ɂv
�@�m�@�u����Ȏ��ɂȂ�Ȃ�A�\������ǂ��Ηǂ������ȁv
�@���́A���w�����ɍ��i�����N����u�����o�Ă݂����v�ƍZ���ɂ͌����Ă��āA����������N���A���ċ��N�����͂�����Ă�������A�{���͂��̔N�Q������͂��������B�������A�P�Q�����{�X�L�[�w�Z��
�@�m�@�u���A�I�茠�s������_���ł����v
�@�Z���u�W���j�A�̑����邩��A���O�������Ȃ������B������N�䖝����v
����Ȃ���肪�������B���̍��͕����̃X�L�[�w�Z�͏���T�l�A�p�g���[���͏��т����ނ��Ă������玄��l�A�ƂĂ�����Ȃ����o�čs������̂ł͂Ȃ��B
�u���N�͕K�����Ƃ����Ă�邩��v�ƌ����Z���̌��t���₵���C�����ŕ��������������B
���āA�����}�ΖʃE�F�[�f�����ł̎����B�b�M�z�\�I�Ȃ̂ŁA����A�R���A�V���̑I�肪�o�ꂵ�Ă��āA���R�f�����X�g���[�^�[���o�Ă���B�R�[�X���͖Y�ꂽ���}�Ζʂ̓J�`�J�`�ɓ����Ă����B�I��̃X�^�[�g���X�g�����Ȃ���A�t�����̏㒅�������~��čs�����Ƃ������������B
���͈�l�̑I�肪�o�����Ɋ������o���A�K���ł��̉��������̎��ɏĂ��t���悤�Ƃ��Ă����B�n�Ӂ@����f��������n�߂��̂��A���ꂪ�Ռ��I�ȏo�������B����܂ł̑I��B���A�K�K�K�A�K�K�ƌ������ō~��čs���̂ɁA�ނ̓J�b�A�J�b�A�J�b�ƌ������ō~��čs���̂������B�킩��ɂ����������Ő\����Ȃ����A���̊��o�Ȃ̂ł��������������B�v����ɑ�σG�b�W���O���Z���̂ł���B
���̉������ɏĂ��t���鎖�ɂ���āA���̊��o�͔���I�ɃA�b�v�����Ǝv���B�F�������肢�l�̊����ǂ����āA�����āA�����̖ڂƎ��ɏĂ��t���鎖���A�K�����Ȃ��̊��o���A�b�v����ɈႢ�Ȃ��B�����ďĂ��t�������ƁA�������ɂȂ�悤�ɉ��x�����K����Ηǂ��B
���x�������̊��o�Ə����Ă��邪�A���Ȃ������������͂��Ȃ��ɂ����킩��Ȃ��A�����炱�����Ȃ��̊��o����Ȃ̂��B
���ǁA�t�����̐��т͎Q���P�N�ڂْ̋������邵�A�ӂ��Ȃ������B�������A��ςȎ��n�ċA���čs���̂������B
�@�@�@�@�X�L�[���t�B�̖�
�ٓ��X�L�[��ɉ����m��Ȃ��܂ܗ���悤�ɂȂ����������A���낢��Ȏ����o���邤���ɁA�ŏ��̔N(�܂��P��������Ă��Ȃ��j����A�f�����X�g���[�^�[�ɂȂ肽���Ǝv���悤�ɂȂ��Ă����B��y�B���������������A�����Ɍ����ēw�͂��Ă�������ǁA�c�O�Ȃ���ٓ��X�L�[�w�Z����f�����a���������͂Ȃ��B
�܂��f���ɂȂ낤�Ǝv���A�I�茠�̗\�I��ʉ߂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�I�茠�ɏo�����ƌ������ɍZ�����o���������Ƃ́A�f���̂悤�ɔ��������鎖�ł��A�^�[���𐳊m�ɕ\�����鎖�ł��Ȃ������B
�@�Z���u�m�A����葬���Ȃ�����o�Ă�����v
�@�m�@�u�E�E�E�E�v�@�@�@���ꂾ���������B
�F����͐M�����邾�낤���A���ɂ��S���{�X�L�[�A���̐��ψ��Ŏw���������I�茠�̖����A�����������l���������Ƃ��B�������A���ꂪ�S�Ă��Ƃ��������킩���Ăق����B
�X�L�[�̓X�L�[�A�]���ɑ�������~�肽�ق�����肢�̂��B���܂��l�ɂ͂��ꂾ���_�����o��B
���N�R���ɂȂ�ƁA���q��������Ȃ��Ȃ��X�͊y�����߂��������l����B�����Œa�������̂��A�ٓ��X�L�[�w�Z�t���D�g�b�v�����X�L�[���B�Q�����͂T�O�O�~�A�D���҂��S�z���B�D���҂͌��ǃW���[�X��������肷�邩��A�����c��Ȃ��̂����A���ѕ\�̓X�L�[�w�Z�ɒ���o�����B
�X�L�[�w�Z�ł͗D���҂���ԏ�肢���ƂɂȂ邩��A�݂�ȕK���Ŋ���̂������B�R���̐��ꂽ���Ƀ|�[�����Z�b�g���āA�������Ȃ�����d���f�����g���s���B���͏��w�����ɍ��i�������̔N�A�Ƃ��Ƃ��Z�����R���}���b�̐��E������Ǒ����������B���̎��́A��ɑI�茠�̏�A�ƂȂ�q�v�Ƙa�O����w���ŁA�ނ�ɂ̓n���f���v���X���ꂽ�̂����A����ł���X��葬�������Ǝv���B���N�I�茠�ɏo�ꂵ�Ă����a�c���A�q�v���������������łP�ʁA�֎悪�Q�ʁA�����R�ʁA�Z�����S�ʂ������B
�Q�O�������Q�����āA�݂�Ȋy�������Ɋ����Ă��邪�A�{���̏��͌v��m��Ȃ��A�X�^�[�g����Ζ{�C���B�a�c����̓S�[������Ƃ��������̃^�C�������āu�m�ɏ������v�ƌ����Ă������A�֎���K�b�c�|�[�Y���o������A���������͏�肭�Ȃ����ƔF�߂�ꂽ�悤�ȋC�������B�Z���͉��������Ȋ�����Ă�������ǁA�����ߊ���ăK�b�c�|�[�Y������Ƃ������������Ȋ�ɕς�����B
���������ăX�L�[�w�Z�֖߂�ƁA���ѕ\������o�����B��������Ȃ��烏�C���C�����̂��܂��y�����B�������A�N��l������͂��Ȃ��B�V�ѐS����n�܂������ł��A����o���Ε��������Ȃ�����{�C���B���i���瑬���ق�����肢�ƁA�݂�Ȃ��������Ă��邩�炻��ł����̂������B
�X�L�[���t�B�̗����̎d���̂ق����A�F������ȒP�ł͂Ȃ����낤���B
�|�[���ȊO�ł́A��͂�]���Ɋ������ق�����肢�Ɨ������Ă���B�����āA��ɂȂ�Z���Ǝ�������ł���Ƃ�
�@�m�@�u�I�茠�A�o�Ă������ł���ˁv
�@�Z���u������v�@�@�@
�@�܂��A���Ȃ��o�����Đ��т��o����̂ł͂Ȃ��Ǝv���B�������A�o�Ă݂����A�f�����X�g���[�^�[�ɂȂ肽���B���x���t�Ɍb�܂ꂽ�Ə��������A��x�����č\�����ǂ��́A�X�L�[�̊J�������ǂ��̂Ȃ�Ă��������������ꂽ���͂Ȃ��B���낢��Ȑl���X�L�[�������Ă��ꂽ����ǁA�O�����ƌ���ꂽ���͂Ȃ������B�X�L�[�����ɏ����Ă��鎖���킩��Ȃ��Ƃ������ɖڋʂ̃}�[�����
�u�m���f���ɂȂ�A���O�̊��肪�X�L�[��������Ȃ����v�Ɠ������̂������B
�f���ɂȂ肽���ƌ������ɁA�u�����Ȃ�Ȃ���������A�m���Ȃ��킯�Ȃ���A�܂���肭�Ȃ�̂͂��ꂩ�炾����킩��Ȃ����ǂȁv�Ƃ��u���K����Ȃ�邩������Ȃ���v�Ƃ��A�Q�O�ŏ��߂ăX�L�[���o�����l�Ԃ��f���ɂȂ��킯���Ȃ��Ƃ͒N��l����Ȃ������B
�����āA���̉\�������邱�Ƃ����������Ă��ꂽ����A���͂Ђ�������K�𑱂���ꂽ�ɈႢ�Ȃ��B
�@�@�@�@���̎��̐搶���߂�Ȃ���
�ٓ��X�L�[��ɖ߂萔�������������A�܂��c�Ƃł����ɖ����ދ��ȓ��X���߂����Ă���ƁA�˓�����(���w�����j������Ă����B�˓�����́A�������w���������O�ɂ͂��܂Ɍ��Ă��ꂽ�̂����u�m�̊���́A���ƌ����������A�y����Ȃ��v�ƌ��������ŁA�ǂ����ǂ��Ƃ͌���Ȃ������B
���͈�l�ɂȂ�Əd����������悤�Ɨ��K����̂����A�̏d�𑝂₹�����̂��ȁH�ƌ��������ŁA���܂����킩��Ȃ������B���������������G�b�W�̎g�������킩�������A�˓�����͎��̊�������āu�y���Ȃ��ˁv�ƌ������B�{���Ȃ炵������イ�X�L�[�w�Z�ɗ��ăX�L�[�������Ă���͂��Ȃ̂����A����Ȃ��̂ʼn����ł��Ȃ��B
�R�[�q�[�����݂Ȃ���F�Řb���Ă���ƁA�˓����V���������Ō����炵�����A�ׂ̃X�L�[��ɃC�^���A���珗�����t�����Ă��邩��A�ǂ�Ȋ��肩���ɍs�����ƌ����̂������B�F�́u�X�L�[�w�Z�ɓ����āA�K���Ă�����������v�Ȃǂƌ����n�߂�B���ǎ��ƌ˓�����̓X�L�[�w�Z�ɓ��邱�ƂɂȂ����B�������A������Ȃ�ł����w��������l����Ȃ��Ƃ����Ă͂����Ȃ��̂ł͂Ȃ����H�@�@�r�`�i�̃X�L�[�w�Z�ł͂Ȃ����C�^���A�l���t�͏㋉�ǂ������Ă��邩��A���b�X�����n�܂�Δ���Ζ��Ȃ����낤�ƌ����b�ɂȂ�A�o�����Ă�������X�͐\�����ɂ͂P���Ə����ă��b�X����҂����B
�N���X�������n�܂��X������ƁA�ޏ��́u�I�[�E�}�C�l�v�ƌ����ĎႢ�j�����t���ĂB�����̎�ɕ����Ȃ��Ɣ��f�����炵���A�Ⴂ�j�����t���S�����鎖�ɂȂ�A������Ƃ������肵����l�������B���낢��Ȏ�����点��̂����A�S�Ă��Ȃ��Ă��܂����A�{���ɂ��ɂ��������Ǝv���A�u���Ă��ĉ������v�ƌ����Ċ���o���ƁA�ǂ����Ă��ǂ����Ă��܂��ނ̃X�L�[��ł��܂��B�}�ΖʂŖ{�C�ɂȂ��Ċ����čs���̂ɓ��܂��̂�����A���炩�Ɍ�납�痈��l�̂ق�����肢�B
�@��ϋ��k���Ă������A�����܂ŗ���Ɩق��Ă������Ȃ����A����킯�ɂ������Ȃ��̂ŁA�w������A�{�C�ŋ��Z������Ă����ƌ����Č떂�����̂������B�{���Ɉ������������Ǝv�����A���̔��ʁA���̒��J�Ȏw���͌��K���������������B�@�r�h�`�̃X�L�[�w�Z�̎w���̂������������������Ē����āA��X�̃v���X�ɂȂ������͊ԈႢ�Ȃ��A���̏����āA����Ƃ��l�т��������Ǝv���B
�@�@�@�@�����̖ڂƎ���M���悤
������A���Ƃ�����~��c�Ƃ��n�܂�A���ё������������ē��₩�Ȗ������n�܂����B�֎�����w�������i�̗��N����A���t�g�W�̐ӔC�҂Ƃ��ăX�L�[��ŋΖ����Ă���A���ǂ����A�h�o�C�X�������Ȃ�����K����̂������B�q�}������Z�������Ă��ꂽ�B
���̍��̎��͂Ƃɂ������̉����o�����ɖ����������B�J�b�A�J�b�A�J�b�ł���B�Q�����f���A�C�X�o�[���ɂȂ�ƕK���ōČ����悤�Ƃ��Ă����B�J�b�R�Ȃǂǂ��ł��ǂ��A����ɂ���͎̂����̎������A�͂̓������ς�����A�Ƃɂ������낢��Ȏ��������čs���̂������B���x������ԂɁA��x�����ł����A�����������o��I�@�@���̉��������Ă͂����Ȃ��B
�����炭�Ζʂ��Ⴄ���A�Z�p���Ⴄ�A�S�����������o����͂��͂Ȃ��B�������A�����Ŋ����鎖�̏o����͈͂ŁA�����������߂�̂��B���������o��A���̎��̑̂̎g�������Č�����Ηǂ��B��x�������������o�āA��͑S�R�킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����Ƃ��ǂ�����B�������A�����鎖�͂Ȃ��B��x���������o���Ƃ������Ƃ́A���Ȃ��̑̂��o���Ă���Ƃ������ƂŁA�ǂ����������A�K���Ăяo����Ƃ��o����B
�^�����A���̓��[���h�J�b�v��I�����s�b�N�Ȃǂ�ڑO�Ō������Ƃ��Ȃ����A���������邱�Ƃɂ���āA�����Ə�B�ł���͂����B��肢�l�̊��o�͉�X�ɂ͌v��m��Ȃ����̂��B���������āA�����̌����Ƃ���A�������Ƃ��芴�o���čs�����B
�����Đ�����A�����̒ʂ��������ł���ƁA�Z�����u�m�������̓G�b�W�̎g�������킩���ė����ȁv�ƃ|�c���ƌ������B�ȑO�A�`�������W�R�[�X���������Ƃ��Ɂu��肭�Ȃ����ȁv�ƌ��������Ɠ����\��ŁB
���̏u�ԁA�����u�ł��Ζʂ����鎞�̉��łЂ�߂����v�Ƃ����ƁA���܂Ŏ��Ɍ��������̂Ȃ��悤�Ȋ��������Ȋ�������̂����ł��Y����Ȃ��B
���̎��������ď��w�����ł���B�G�b�W�̎g�������킩��Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B�������A�Z���������o�Ƃ̓��x��������Ă����̂��B�F����ɂ��A���̎����킩���Ē��������B��肢�l�ƁA�����łȂ��l�̊Ԃɑ傫�ȍ�������A�Ⴆ�Z���̊��o�Ǝ��̊��o�ɑ傫�ȕǂ�����A�P�ɃG�b�W�̎g�����ƌ��������ł́A�b���ɂȂ�Ȃ��̂��B
�G�b�W�̎g�����ƌ����Ă������[���A�X�L�[���X����Ƃ������b�����ł͍ς܂��Ȃ����A�F����ɂ��K���킩�鎞������B���āA�Z���Ǝ��̕ǂ݂����Ȃ��̂́A������������x�J�b�A�J�b�A�J�b�Ƃ������������̕��ɂ��鎖�ɂ���Ď�蕥���Ă��܂��B�^���ɃX�L�[�Ɏ��g�ݎ����̊��o���ɂ��čs���A����قNJȒP���ƌ������𗝉����Ăق����B
���Ȃ������ē������B���Ȃ��̊��o���A�b�v������܂ŏo���Ȃ����������ˑR�o�����肷��B�������A�����̊��o���ӎ����đ�ɂ��Ă��Ȃ���A����Ȏ��͋N����Ȃ��B�J���ĕ��ĂȂǂƂ����O������ɖڂ�D���Ă��ẮA��ɐg�ɂ��Ȃ��̂ł���B
����A�����i�K�ŁA����ƃX�L�[���͂̎��ɂ��Ċ����悤�ɂȂ����l�ł��������A���̎���ǂ��������ė��K����悤�ɂ��Ăق����B��������A���Ȃ��������悤�ȃX�s�[�h�ŏ�B���čs���ɈႢ�Ȃ��B ���̍��̎��͂Ƃɂ������̉����o�����ɖ����������B�J�b�A�J�b�A�J�b�ł���B�Q�����f���A�C�X�o�[���ɂȂ�ƕK���ōČ����悤�Ƃ��Ă����B
�@�@�@
�@�@�@�@�����̊��o
�Ȃ������̊��o������Ɖ��x���������ƌ����A���Ȃ����ǂ����ǂ̂悤�ɓ������A�X�L�[�����Ƃ��~�܂�Ƃ��킩��Ȃ�����A�ǂ�Ȃɋ��ȏ���ǂ�ł������ł��Ȃ����炾�B�Ⴆ�A�X�L�[�G���̉���ŁA�u�R�R�}�߂̎ʐ^�ł́A��ʂ̂Ƃ炦���Â��Ȃ��Ă��܂��Ă���̂Œ��ӂ��܂��傤�B�v�ƌ������͂�����Ƃ��悤�B�ǂ�����ΊÂ��Ȃ�Ȃ��̂��A���ꂪ��Ԓm�肽�����ł͂Ȃ����B
�J�Z�b�g�f�b�L�̎g�����Ȃ�A��������ǂ߂ΒN�ł������悤�ɓ�������B�������A�X�L�[�͈Ⴄ�B���ꂼ��̃X�L�[���t�ɂ���Đ����̎d��������ē�����O�Ȃ̂��B����Ȃ̂ɖ���Ⴄ�{��ǂ�A�Ⴄ�X�L�[���t�ɋ����Ă�������肷��̂��������Ȃ��Ă��܂��B���������l�ɋ����Ă��炦�ƌ����Ă���̂ł͂Ȃ��B�o���邾���A�����̐l�ɋ����Ă��炤�ق����ǂ��Ɍ��܂��Ă���B
�����A��̎��𗝉����čČ�����̂́A���Ȃ��Ȃ̂�����A���Ȃ����g�̌��t�⊴�o�ŗ������A�̂ɖ��߂��Ă�鎖������B�m���ɓ�����Ƃ�������Ȃ��B���Ȃ��ɂ킩��₷���������Ă����l��������Ȃ���������Ȃ��B�������A����͂���ł������B���Ȃ����A���̐��������K���A���܂łƈႤ���o�ɂȂ�A������x���Ă��炦�����̂��B
�u����ł����v�Ƃ��u�����ł͂Ȃ��v�Ƃ��������Ԃ��Ă��邤���ɁA���Ȃ��͊m���ɏ�B���čs���B�����A���܂łƈႤ���o�łȂ���Ή��̈Ӗ����Ȃ��̂Œ��ӂ��K�v���B����Ȏ��́A�Ƃɂ����ɒ[�ɑ̂����Ă݂悤�I
�ŋ߂̃X�L�[�̓T�C�h�J�[�u�������Ȃ��āA�F������J�[�r���O���������₷���Ȃ����Ǝv���B�X�L�[�̐��\�⍡�܂ŏ�肢�l���������鎖�̏o���Ȃ��������o���A���₷���m�鎖���o���đf���炵�������B
�������A��̂�|���ĂȂǂƊO������^�����Ă���ɏ�肭�����Ȃ��B�����܂ł��X�L�[�ɗ͂�`�������ʂ��O���ɕ\���̂��B
���Ȃ����X�L�[�ɗ͂�`���鎖�ɂ���āA���̃^�[���ʂ�X�s�[�h�ɂ������p�����o��������̂��B�O����������Ă��܂�����A���̃^�[���ɕK�v�łȂ��p������낤�Ƃ��Ă��������Ȃ�B���Ȃ��̊��o�ŃX�L�[�ɗ͂�`���鎖������B
�@�@�@
�@�@�@�w�������肪�n�܂���
�@�w��������͑S���T���Ŏ��{�����B��X�͍b�M�z�u���b�N�Ȃ̂ŁA���̔N�T�l�S�����V�����A�V�ԑq�X�L�[��ł̎ƂȂ����B���Ɗ֎�͏��w��������Ɠ������ɂȂ�B�Z���͌�����Ƃ��Đ�ɏo�����Ă��āA��X�͏t�����̎Ԃŏo�����Ă������B�ٓ��͐Ⴊ���Ȃ��}�Ζʂ͊���Ȃ���������A��X�͐�̂���X�L�[�ꂪ�������āA��t�̎��Ԃ܂Ŏq���̂悤�Ɋ����Ă����B
�ŏ��̎�ڂ́A�������~�ł���B���̓��̎��̃X�L�[�͏o���O���ɁA�q�v���`���[���i�b�v���Ă���Ċ����ȏ�Ԃ������B�l���������S�R�[�X�œ����悤�ɃZ�b�g����A�S�l�������ɃX�^�[�g���čs���B�Q�l�����ɃX�^�[�g�ƌ����̂͗ǂ����邯��ǁA�S�l�ƂȂ�Ƒ�ϔR����B
���܂��܁A���̗�̃X�^�[�g�W���Z���ŁA�u�m�A�ꔭ����Ă݂�B�F�A�{�C�Ŋ���Ȃ�����ʔ����˂���v�ȂǂƂ����������A���̋C�ɂȂ��ăX�^�[�g�������́A�r���]�т����ɂȂ����B���A���Ƃ������Ȃ����S�[������ƁA�t������ɂ��āu�m�A�����Ă邶���v�ƌ������B�����u�]��v�ƌ����Ɓu���Ă����[�v�ƌ����ď��̂������B���i���C���͊�^�C���̂P�Q�O���Ȃ̂ō��ۂɂ͖��Ȃ����A������A���Ŋ���l���x���͕̂������B
�������~�ɂȂ�ƁA�Z�����łP�O����������Ȃ��悤�ȏ̒��A����͑�����ꂽ�B�g�����V�[�o�[�Łu�[�b�P�������ԃX�^�[�g���܂��v�ƃX�^�[�g�W����S�[���֓`������̂����}�Ɏ��B�̓X�^�[�g���čs���B������̓R�[�X�̓r���܂œo������A�~�肽��Ɩ��̏�Ԃɍ��킹�ē����Ȃ���̓_���Ă����B�قƂ�ǂ̏ꍇ�A���Ŕ��f�����Ԃ������Ǝv���B
�����F���o�b�W�e�X�g�ȂǂŁA���̂悤�ȏɂȂ����Ƃ��Ă��S�z���鎖�͂Ȃ��B����ȏł�������́A��������Ƃ��Ȃ��̋Z�p�������Ă����B�����������A�����̎��ԁA���邱�Ƃ��o����Ή��̖����Ȃ��B�P���Q��������F����Ȃ�u�����Ȃ��̂ɓ_�Ȃt������̂��낤���v�Ǝv����������Ȃ����A�����F������̎��i�������A�����悤�ȏ��o�����Ă��邩��A������Ɠ_�����o���Ă���鎖���^�����̂͂��Ȃ��B
�X�^�[�g���߂Â������A�܂����͔Y��ł����B�����Ȃ�������S�Ɋ����Ă��������A����Ƃ��{�C�ōs�������A���̂悤�ɔY�ގ��͂낭�Ȏ����Ȃ��B
�O�̐l���S�[�����������g�����V�[�o�[�̉��Œm�������A����ƌ��܂�A�u�ʓ|������Ă������v�A���낢��l���Ă����ْ̋����̒��ŏo����킯���Ȃ��̂��B
�����āA���������Ȃ����X�^�[�g���ĂR��]�ڂ��I��낤�Ƃ������A�ˑR�S�[���|�[�����ڂɔ�э���ł����B���̌����ł̓S�[���̊O�ɏo�Ă��܂��A�Q�ĂăX�L�[�������́A�R�[�X�̒[�ɂ��܂�����ɃX�L�[������A�]��ł��܂��B�^�ǂ��X�L�[�͒����Ă����̂ŁA�N��������Q�C�R���i�ނƃS�[���������B
�u�_����������Ȃ��v�Ǝv���Ȃ���A�S�[������o��Ə��т������Ă��āu�m�A�قƂ�ǃS�[�����Ă��炾������v����ƈԂ߂Ă��ꂽ�B
���͖{�ԂɎア�̂�������Ȃ��B�������A�����̐ςݏd�˂Ă������̂����o����킯���Ȃ��B�ǂ�ȎΖʂł��]�Ȃ�����ڕW�ɂ��ė��K���Ă����͂����B�@
����Ȃ̂ɍ��]�ԂƂ͂ǂ��������Ƃ��낤���B�]�Ȃ��������ɂƂ��ď�肢��������߂��Ȃ̂�����A���͌���Ȃ�����Ȏ��ɂȂ��Ă��܂��ł͂Ȃ����H�@���̗������C������ς����Ȃ��܂܁A����͑����Ă������B
�E�F�[�f�����ł͂Ƃɂ����m���Ɋ��鎖�������l�����������ʁA�Ȃ��Ȃ��������G�������B�������A�܂��C�����̐؊����͏�肭�s���Ă��Ȃ������悤�ŁA�p�������^�[���ł͂܂����Ă�����Ă��܂����B�d�����܂����R�[�X�q�悭����S�[������B�S�[���n�_�͉��l���̐l������I���A��̂��܂����Ƃ���ƁA�J���J���ɍ��ꂽ�Ƃ��낪���݂ɕ���ł��āA��̂��܂����Ƃ�����z�������A�ĂѐK�݂����Ă��܂����B
�u���肾�ȁ[�v���̒��́A���̌��t��F�ɂȂ�B
���̎������т���ƏG�B�����Ō��Ă��āu�]�ԂȂ�A�Ǝv���Ă���{���ɓ]��ł₪��́v�ƌ����ď��Ă����B���v���Ɖ��̎����S�[������ƒN���������̂��낤�E�E�E�B
��͂莄�͑�ϗ��������A�����̉��肳�ɕ����������B�������܂ŗ��K���Ă����̂��낤�H�@�����āA�����ɂT��ڂ��I����Əh�֖߂��Ă������B
�[�H�ł́u�����l�ł����v�̌㊣�t�ɂȂ�̂����A���͖{���Ɏt�Ɍb�܂�A���Ɍb�܂�Ă����Ǝv���B�F���ꂼ���肭�����Ȃ��_������s���Ŏd���Ȃ��͂��Ȃ̂ɁA���т��тƃr�[�������ގ��̎����܂��Ă����̂������B�{���͎����̎��Ő���t�Ȃ̂ɁA�F�A�������w�����Ȃ̂ɁB
���������̐e�ɕ������ꂽ���Ƃ�����B�����ɂȂ��Ă��q���͎q���A���������̂܂܂��B�݂�Ȏ��ɐڂ��鎞�A���N�O�̊���Ȃ��������̎p���������Ă��Ȃ������̂�������Ȃ��B���ł��A���̍��̎��̎p���v�������ׁA���ɐڂ��Ă��ꂽ�ɈႢ�Ȃ��B
�@�@����͈ꔭ�����ł͂Ȃ��A�Ō�܂ł�����߂Ȃ��ŁI
����ڂ̎��́A��������Ɨ��������Ă����B�݂�ȓ������w�����Ȃ̂��B���͂����Ə��ڎw�������A���i�A�s���i�̃��C�������낤�낵�����ȂȂ��B���̓��͑S�͂łԂ����Ă������B������ɑ��Ă��A���̎��ɑ��Ă��A�R�[�X���K������l�b�g�̎���Ō��Ă����ʂ̃X�L�[���[�ɑ��Ă��A
�u���̊�����A�悭���Ă�v�ƌ����C�����ŁA�[���������肪�o�����B���̌�A�w�Ȃ̌�����I���F�A��ϔ�ꂽ�l�q�ł܂��A���t����̂������B
����ڂ̎��s�͂���������܂��B�������A����ڂɎv���ʂ芊�ꂽ���ƂŁA�P���̍��i���\�̎��Ɠ����C�����ɂȂ��Ă����B�����̐ςݏd�˂Ă������̂��]�������Ȃ�A�K�����i�ł���B�s���ȂǏ����Ă����B���̃����o�[�́A�]�Ԃ悤�Ȏ����Ȃ�������I���A�F���S�z���Ă����͎̂��̂��Ƃ����������B�������A�����g�͗��������Ă��āu�悵�A���ނ��v�̐��E�ɓ����Ă����B
�@���̌���ɏo������O�̑ٓ��X�L�[��͐Ⴊ���Ȃ��A�Z������σC���C�����Ă����������p�g���[���A���R�C���C�����Ă����B���̏�A�v���悤�ɗ��K���o���Ȃ��A���������^��ł���̂��B
�����������̂��o���Ă��Ȃ���
�u�m�A�w��������͉��������������C�����룂ƃC���C�������Z�����f���̂Ă�悤�ɂ������B
�@�m�@�u������͂�������܂���A���Ƃ�����̂Ȃ痎�Ƃ��ĉ������v
�@�Z���u���ܔ����Ă�̂��v
�@�m�@�u���́A�f���ɂȂ��ł�����A�w�����𗎂���킯����܂���v
�@���̓f���ɂȂ肽���ȂǂƖ��̂悤�Ȏ���{�C�ōl���Ă����B���ǁA���̖������Ȃ����͂Ȃ���������ǁA�X�L�[�ɂ͖{�C�Ŏ��g��ł����B��͂�A�j���m���A�S�̒��ł͂킩���Ă��Ă��A����Ȍ��t���o�Ă��܂���������B
�@�@�@�@
�@�@�@�f���炵���X�L�[���t
�@�����āA���i���\�̎��������B�w��������̓[�b�P�����ɍ��i�҂����\�����B
�[�b�P�����Ă�ăz�b�Ƃ��Ă���ƁA�N���ɐK���R����ꂽ�B�U������Ə��Ȃ���A
�@�Z���u�Ȃ��̓_���́A���ꂶ��f���ȂɂȂ�˂���v
�@�m�@�u��]�Ⴂ�܂����v
�@�Z���u�o�J�A�]�獇�i�_�o�Ȃ����낤�v
�@�m�@�u��Ƃ��A�قƂ�ǃS�[���ł�����v
�@�Z���u�܂�������A�����������ė����B�A�낤�v
�@�֎�ƏG�B��������i�����̂����A��ώc�O�Ȏ��ɏ��т���Ət����s���i�ɂȂ��Ă��܂����B�Z���͂Q�l�ɑ���
�u�܂��������������A�܂�����Ȃ������v�ƌ����ƁA���т́����̃p�[�L���O���ƌ��߂ďo�Ă������B���ʂƂ��āA���w�������i����P�N�ڂ̎ƂQ�N�ڂ̎̍����o�Ă��܂����悤���B
�@�����ŊF����ɂ킩���Ă������������̂́A���̃��x���ɂȂ��Ă��A���̒i�K�ɐi�ނ̂ɂ́A����Ȃ�̎��Ԃ��K�v�Ȏ����B�O�N�ɏ��w�����ɍ��i���āA��Ϗ�肢�l�����Ȃ̂ɁA���̂��̂悤�Ȍ��ʂȂ̂��悭�l���Ăق����B
���Ȃ��������̊��o�ŃX�L�[�𗝉����鎖�ɂ���āA�K�������悤�ȃX�s�[�h�ŏ�B����Ɖ��x�������Ă����B�������A��̎���̂Ɋo�����܂���̂ɁA�Œ���K�v�Ȏ��Ԃƌ������̂��K������B�Ƃɂ��������炸�ɁA���o�����܂��Ăق����B
�P���ɍ��i���鎖�͊m���ɁA���Ȃ��ɂƂ��ē����������Ȃ��B�������A�l������ς���A�����ƊȒP�ɍ��i�ł���Ɛ\���グ�Ă���̂ł���B�ȒP�ɍ��i����ƌ������́A���Ȃ����ȒP�ɍl����ƌ��������B�����āA����������鎖�Ȃ�A���̂悤�Ȋ��ɂ��Ȃ�����э���ł݂Ăق����B
�����炭�A�����ǂ܂����́A���̂悤�ɑS������Ȃ����������A�������̂ق��������Ǝv���B�X�^�[�g�̎��_�Ŏ����O�ɂ���̂�����A�t�Ɍb�܂�A���Ɍb�܂ꂳ������ΕK���T�N�Ŏw�����͎���B
����ɁA���P���������Ă�����Ȃ�A�R�N�ō��i�ł���̂ł���B���o���A�K���ɂȂ��ė��K����ΕK�����i�ł���̂ł���B�S���{�I�茠�ȂNj��Z�X�L�[�Ŋ����l�B�́A���Ƃ����₷���R�C�S�N�Ŏw�����ɂȂ��Ă��܂����낤�B�������������������̂́A���߂���|�e���V�����̍����l�̂��Ƃł͂Ȃ��B�Y�u�̑f�l�ł��K���߂������P����w�����ɍ��i�ł���B
�����āA�f�����X�g���[�^�[�ɂȂ鎖�͓����������Ȃ�����ǁA�f���炵���X�L�[���t�ɂ͐�ɂȂ��̂��B
�@�@�@�@�{���ɏ�肭�Ȃ����̂��낤���H
���������𖽗߂��Ȃ�����K���鎖�ŁA�K����B���鎖�ɊԈႢ�͂Ȃ����A����ɂ����i�ł���B�m���Ɏ��̂悤�ȑf�l�ł��A1���A���w�����A�w�����Ƌ����悤�ȃX�s�[�h�ŏ�肭�Ȃ����B�������A������Z���A�}�[�����֎�A���ɂ�����܂œo�ꂵ���l�����A��肭�Ȃ������H�ƌ����Ή���Ɏv����B
�O��������A���ꂼ��Ɍ������邵�A������X�L�[�Ƃ͉��������ɋ����Ă��ꂽ�l�B���B�������̐l�B�ɃX�L�[�Ƃ́H�Ȃǂƌ�����͂����Ȃ��B����������̂́A�X�L�[��ʼn߂������N�����y�����������ƂƁA�܂���������Ȃ������j���A�w�����ɂȂ����ƌ��������������B��͎�������ł́A�o�J�Ȏ����茾���āA���̍������������v���o�������낤�B
�܂��A1���ɍ��i����O�A�i�C�^�[�ň�l����Z���������B���t�g�����O�Q�����f�����グ��ƁA�Q�����f�̈�Ԓ[���Z�����E�F�[�f�����ō~��Ă����B�����n���Ȃ��Ƃ��茾���āu��Ȃ�����������~��悤�v�ƌ����Ă���Z���́A�����v���ɁA�ԈႢ�Ȃ����K����p�������邱�Ƃ͌����ɈႢ�Ȃ��B�������A���̎��Z���͈�l�A�{�C�ɂȂ��Ċ����Ă����B
�Q�����f���A�C�X�o�[���ɂȂ�Ɓu�d���Ċ���Ȃ��v�ƌ����搶���Ɂu���̈ʂȂ�A�ォ��p�`�����ē��߂�����v�ƍZ���͗ǂ��������B���ꂪ�C�ɓ��������́A���Ȃ̂悤�Ɂu�ォ��p�`���v�ƌ����悤�ɂȂ�u�ォ��p�`���v��K���ł������Ƃ��Ă����B
�@�������Ɂu���O�͎̂p������������A�����Ə������Ȃ��Č���v�ƌ����Z���́A���̎��̊���́A�p���������Ȃ�Ă������̂ł͂Ȃ������B�u���̂���Ȃɍd���Ƃ�����A����ȃJ�b�R�Ŋ����̂��낤�v�Ƃ��̊����Ȃ��A�傫�Ȍ����J���Ă��邾���������B�����炭�A���̎����玄�́A�Z���̗��ɂȂ��Ă��܂����ɈႢ�Ȃ��B
�ٓ��X�L�[�w�Z�����ނ���10�N���߂������ł��A���̓��ɂ́A���̓��̍Z���̊��肪�Ă��t���Ă���B�����āA���̓��������̊��肪�o���Ȃ���A�ǂ�Ȃɗ��K���ď�肭�Ȃ����Ƃ��Ă��A�{���ɏ�肭�Ȃ����Ƃ͎v���Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A���ɂƂ��ẮA���̊��肪�X�L�[���n�߂������ɂƂ��āA��Ԃ̖ڕW�������̂�����B
���R�X�L�[��œ������ɂƂ��āA1���͕K�v�Ȏ��i����������ǁA2���̎ƌ�����̓I�Ȃ��̂��ڂ̑O�Ɍ��ꂽ�̂́A�̐����O���B�����ɖ{�l�́A���i���邩�ǂ������킩��Ȃ��������A���������̃��x���ɒB���Ă��邩�ǂ������A�킩��͂����Ȃ��B����Ȏ����A�ڕW�Ƃ�����̂�1���ł�2���ł��Ȃ��A���̊��肾�����B
�@�w������f�����X�g���[�^�[�Ɍ��͂��߁A���K�𑱂�����X�B�K�����̓��A��������́A���̒��ɑ�ɂ��܂��Ă������B���ł��W���J����ƁA�����̓��ɕ����яオ���ȕ��������A���ł���ɂ��܂��Ă���B���ɂ��}�[����̂�����̊���A�����̊���A�f�����͂��߂Č����Ƃ��ȂǁA��������͂��邯��ǁA���̂Ȃ��ł���ԑ傫�Ȕ��̒��ɓ����Ă���B���̔�����D���Ȏ��Ɏ��o���A�Č��ł���悤�ɂȂ�Ȃ�����A��ɍZ������肭�ȂǂȂ��Ȃ��B
�@���̔��Ƀ��{���ł����āA��y�B�Ƀv���[���g���Ă�ꂽ��ǂ�قǑf���炵�������낤�B�߂������ɑٓ��X�L�[��ɂ���ԂɁA�v���[���g���Ă�鎖�͏o���Ȃ������B�����炭�A���̐���s�\���낤�B�m���Ɏ�����肭�Ȃ������́A�N�̖ڂ��猩�Ă����炩�Ȏ����B�������A�N����y�̐S�̒[�ɁA���̊��肪���ɂ��܂��Ēu����Ă���̂��낤���E�E�E�ƍl����Ƌ^�₾�B
�@�����g�͍Z���Ɉ�ԑ����X�L�[����������B���A�����o���Ȃ�������ŁA�C���C�������ė����ɈႢ�Ȃ����A�w�����ɍ��i���������A���̐�������Ɠ��������낤�B
�@�F����ɓ`�������B��肢��肭�Ȃ��́A����Ȃ�_���ɁA�|�[���Ȃ�^�C���Ɍ����̂����A�����͂���Ȋ�����������ƌ��������A��������ƃC���[�W���鎖���B�����āA���Ȃ��̊��肪�N���̔��̒��ɁA���܂�ꂽ�����{���ɏ�肭�Ȃ��������B�������A���̂��Ƃ����Ȃ����m��p�͂Ȃ��̂�����A�{���ɏ�肭�Ȃ�Ȃǂƌ������́A���蓾�Ȃ���������Ȃ��B�����A���������̎v���`����������������鎖�����́A�Y��Ȃ��łق����B�@�@
�@�@�@
�@�@�@�@
�@�@�@��肢�X�L�[���[�ƌ���ꂽ��
���x��������������͈ꔭ�����ł͂Ȃ��B�ꔭ�����ł���Ȃ��ڂ͈�ő����B�����炱���A������߂Ȃ��łق����B���肪�ꔭ�����łȂ��Ƃ������́A�X�L�[���ꔭ�����ł͂Ȃ��ƌ��������B�Q��ڂœ]��ł��܂����������A������ƍ��i�ł����ł͂Ȃ����B
�o���ꂽ�_������X���m�鎖�͏o���Ȃ����A�K��ǂ���Ȃ���H��ځi�}�Ζʁj�w����ځi�ɎΖʁj�e�T��ڂ̓��A�P��ڂ����i�_�ɒB���Ă��Ȃ��Ă��A�����_���B���Ă���Ηǂ����ƂɂȂ��Ă���B���������Ď��́A�]��ڂ��B���Ă��Ȃ������Ƃ��Ă��A�����_���B���Ă������ɂȂ�B���̏ꍇ�A��Ƃ��}�Ζʎ�ڂ���������A�ǂ��炩�͓]��ł����i�_���o�Ă������ɈႢ�Ȃ��B
�@�Z���͌���������炻�̓_�������邱�Ƃ��o����B�u�]��ō��i�_���o��킯�Ȃ�����Ȃ����v�ƌ��������Ɓu�Ȃ��̓_���́v�ƌ����������l����ƁA����Ȃ�ƍ��i����Ǝv���Ă����̂ɁA�M���M�����������炠�̂悤�Ɍ������̂�������Ȃ��B�P����Q�������ē������A����i�_�ɒB���Ă��Ȃ��Ă����͂Ȃ��B����������i���Ă���̂ق�������ƌ�������Y��Ȃ��łق����A�V�O�_���傤�ǂ̍��i���A�V�R�_�̍��i���P���͂P�����B
��肢�P���A��肢�w�����ƌ�����悤�ɂȂ肽���ł͂Ȃ����B�����āA�ŏI�I�ɏ�肢�X�L�[���[�ƌ���ꂽ���B�����ق�����肢�Ƃ�������������A���Z�X�L�[�Ŋ���l�B����肭�Ȃ�͖̂��������A�ǂ�ȎΖʂł������Ƃ����_�ł̓G�x���X�g�������Ă��܂��l����肭�͂Ȃ�Ȃ��B�������A���ł���肭�Ȃ肽���Ƃ����C�����͎������������B
�u�D���������̏��Ȃ�v�ƌ������Ƃ킴�����邪�A�N�����X�L�[�������鎖���o����A���̐l����ԏ�肢�ɈႢ�Ȃ��B
�@�@�@�@������߂��ɗ��K�𑱂��悤
���A�X�L�[�̏�B��{�C�Ŗ]�ނ��Ȃ��ցE�E�E������߂Ȃ��łق����I
�X�L�[�͂����ƊȒP�ɗ����ł���̂�����B���͍��A���ŁA�قƂ�ǃX�L�[�����鎖���Ȃ���炵�Ă���B�������A�߂������A�K���ǂ����̃X�L�[�w�Z�ŃX�L�[���t�����Ă���͂����B�Ȃ��Ȃ�X�L�[��S���爤���Ă��邵�A�X�L�[���t�ƌ����E�Ƃ��D���ł��܂�Ȃ�����ł���B
�����ɏ������悤�Ȑ������痣��ĂP�O�N���o���Ă��܂������A���̎v���͍����S���ς��Ȃ��B����ŊF����ɃX�L�[�̂��Ƃ�b������A��������o����K�������A���ꂪ�o���Ȃ����A��B��ڎw���F����̎菕���͂ł��Ȃ����̂��Ǝv������������Ă���B
�ׂ������K���@�͂������邵�A�X�L�[���t�ɕ����Ă��炦�킩�邱�Ƃ��������낤�B���������鎖�́A���Ȃ��̎��g�ݕ�����ƌ��������B�ЂƂ̗��K���@�̒�����A���Ȃ�������͂ނ��Ƃ������ł���B���l���̑f���炵���X�L�[���t������ȏ�A�������e�ł����Ȃ��ɂ��܂��������o�͈Ⴄ�̂ł���B
�ǂ̂悤�ɂƂ炦�邩�H�@�ǂ̂悤�Ȋ��o�Ȃ̂��́A���Ȃ��̖��Ȃ̂��B�������g�̊��o�ŗ����ł��Ȃ���Ζ{���ł͂Ȃ��B�{���łȂ�����o�b�W�e�X�g�ɗ����Ă��܂��̂��B�{�������߂悤�I�@����Ɠ����ɑf���炵���X�L�[���ԂƂ̏o����̌����Ăق����B
�c�O�Ȃ��炱�̔N�̑ٓ��X�L�[��́A���قǂ����c�Ƃł��Ȃ������B
�w����������I���߂�����X�ɁA��������Ƃ���͎c����Ă��Ȃ������B
�o���鎖�Ȃ�A�S������Ȃ��������������܂Ō���葱���Ă��ꂽ�l�B�ɁA�w�����ɍ��i�����A���̓��̊�������Ă��炢���������B
�w�����̊Ŕ�w���������̍ŏ��̊�����I
�@���i��������ƌ����Č���O�ƁA�ˑR�ς��킯�ł͂Ȃ��B�������A�ٓ��X�L�[��ʼn߂����āA�f���炵���X�L�[���t�B�Ƃ̏o����Ȃ���A�w�������i�Ȃǂ��蓾�Ȃ������B���̊��ӂ̋C������\���ɂ́A���̓��̊�������Ă��炤�̂���ԑ�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B
�~��X�L�[��œ��������o�[�B���A�ꕔ���c���ĉĂ̐E��ɖ߂�n�߂Ă͂������A���̓��p�[�N�z�e���̉����ɂ́A�قƂ�ǂ̃����o�[���W�܂����̂������B
�������F�̑䎌�͌��܂��Ă���B
�u���̐m���w�����ˁ[�H�v�B
�@�������ĂQ�P�ƂW�����A�ٓ��X�L�[�w�Z�ւ���Ă��������w�����ɂȂ������A�Q�T�ƂP�P�����A���������łQ�U�ɂȂ낤�Ƃ��Ă����B
�@�@�@�@�{�������ɂ߂悤
�������đS������Ȃ��������͂T�V�[�Y���ڎw�����ɍ��i�����B�������A���낢��ȖʂŌb�܂�Ă������ɈႢ�Ȃ��B
�X�L�[���B��������A�P�U�N�ƌ������ɂȂ�B�ŏ��̔N�ɂP���ɍ��i����ƌ����Ă��A��ʃX�L�[���[�̂R�N���͊����Ă���̂����瓖����O�̎����B���������������̂́A���̓v���[�N�{�[�Q����V���e���^�[���A�p�������^�[���ȂǂƎ�ڂ��l���ė��K���������Ȃ��B���ɂ��d���̓p�g���[�����K�B�@
��ԑ�Ȏ��͓]�Ȃ����B�͂��߂͎Ί��~�ƃL�b�N�^�[���A�Q�����f�̒[����[�܂Ō��Ă���t�������č~��Ă������B���q�������Ă���Ǝז��ɂȂ�Ȃ��悤�A�[�ɍs���ĉ�����ō~��čs���B���̒��œ]�Ȃ����߂ɕK�v�Ȃ��̂��o���Ă������̂��Ǝv���A���������K�����̂ł͂Ȃ��B�]�Ȃ����߂̋Z�p�Ƃ��Ċo�����̂��B
�F����͉���������鎞�����l���邾�낤���H�@�O���X����邽�߂̗��K�ȂǂƎv���ĂȂ����낤���A�{�������ɂ߂Ăق����B���ɂ������肪�ł���A�ǂ�Ȃɋ}�ȎΖʂł��A�]���ɍ~��čs����ł͂Ȃ����B���ꂱ���ō��̊��肩������Ȃ��B�����A���Ԃ��������Ă��܂��������B
�m���Ɏ��͊��ɂ��b�܂ꂽ�B�������A���������������A�X�L�[���t�������Ă��ꂽ�킯�ł͂Ȃ��B�搶�������K���Ă���Ƃ���ւ́A���ꑽ���ē����čs���Ȃ������B�����A����Ȃɒ������ԋ����Ȃ��Ă��A�ЂƂ���������Ƃ��������g�̊��o�Ƃ��ė�������ɂ́A�������Ĉ�l�ŗ��K����ق����ǂ��������Ă��邾�낤�B
�X�L�[���[�͂������������A���낢��Ȏ�����x�Ɋo���悤�Ƃ���B�������A�^����ꂽ�ۑ肪�o���Ȃ������ɁA����Ȃɂ��낢��Ȏ����o����킯���Ȃ��̂��B������肭�Ȃ肽����A�ЂƂ̉ۑ�������ł������̂Ɋo�����܂������B
�@���ɂ́A���鎖�����Ŏd���Ȃ��������邾�낤�A����͉��̂��H
�̂����Ă��邩�炩������Ȃ��B�������A���������肭�o���Ȃ����̂ق����傫����p���Ȃ����낤���H�@�@�����̎�����x�ɂ�낤�Ƃ���A�ЂƂ�ӂ��Y��Ă��܂��A�u�A�[�܂��o���Ȃ������v�Ǝv���̂�������O���B�����ƁA��B�������ł���悤�ɁA�ЂƂ̎��ɏW�����ė��K���悤�B����Ȃ�A��B����Ɏ����ł��邩��y�������K�ł���B���x�������悤�ɁA�̂��o���Ă��܂��Ώ���ɍČ����Ă����B�ЂƂ̂��Ƃ��Č��ł���悤�ɂȂ�����A���̂��Ƃ��o���čs���Ηǂ��B
�X�L�[�͊ȒP�Ȃ̂��A�y�����̂��B���Ȃ�������l���邩�����Ȃ��āA��肭�s���Ȃ��̂��B�ǂ����Ă��Y��ł��܂�����A�S�Ă�Y��悤�B
���Ȃ��̈�ԍD���ȃQ�����f���D���Ȃ悤�Ɋ��낤�B�����l���Ă͂����Ȃ��A�y�����Ȃ�����E�E�E�X�L�[���D�����Ɗ�����ꂽ��A�Ăї��K���n�߂悤�B
�@�@�@�@�@
�@
�@�@�@�@����̘b
���āA�X�L�[�̗p��Ȃlj��������Ă��Ȃ������������A�ŏ��̔N�X�L�[��֍s���O�ɁA�����̂��Z����̃u�[�c���ꖜ�~�ŏ�����B�ٓ��X�L�[��֎����Ă������̂́A���ꂾ�����B�O�̔N�A�N�����g���Ă������łP�X�T�����̃X�L�[���^������B������̂Ƃ����A�o�R�p�̃J�b�p�̃Y�{�����͂��āA��ɂ̓p�g���[���̃��b�P�𒅂āA��܂͑����̂��Â��g���Ă����B
����ȃJ�b�R�����Ă���ƁA���̂܂ɂ��f�U�C���̌Â��X�L�[�p���c��Z�[�^�[�A�V���c�Ȃǂ��W�܂��Ă���悤�ɂȂ�B�X�L�[�p�i��E�F�A�͉�������������Ȃ�����ǁA�Q�N�ڂɂȂ�Ɓu�m�A������̂��ǂ��Ȃ邶��Ȃ����v�ƌ���ꂽ�B�X�g�b�N����͂�����̂��Â���������ǁA���������C�ɂ��Ȃ���A�X�L�[���t���g�������i������Ă��邵�A���g���Ă���̂�蒷���̂��ق�����A�N���w�̍����l���X�g�b�N��܂�̂�҂Ă����B��l�̐l���܂�Έ�g�̃X�g�b�N���o��������A��͒�����肻�낦�āA�悳�����ȃO���b�v�ƕς��Ďg���悤�ɂ��Ă����B
���N����A�V�����X�L�[���x�����ꂽ�B���̔N�̃j���[���f���Ȃ̂ŃX�L�[�̔����ȈႢ�Ȃǂ킩��Ȃ����́A�V���������������Ďd���Ȃ������B��肭�Ȃ��āA�ق��̐l�̃X�L�[�Ǝ��ւ����肵�Ă��邤���ɁA�Ⴂ�����邱�Ƃ��킩��悤�ɂȂ�B
�s�v�c�Ȃ��̂ŁA�F���ꂼ�ꎩ���̊��o�ɍ����X�L�[���g���悤�ɂȂ�̂����A���̏ꍇ�A������֎�̎g���X�L�[�͏d���������肵���B�������A�Z�����g�����͎̂g���₷���������B�ǂ̃X�L�[���ō������f��������A�d����\�ɑ傫�ȍ�������킯�͂Ȃ�����ǁA�d���������肷��̂������B
���_���猾���Ə�肭�Ȃ��āA���낢��ȈႢ���킩��悤�ɂȂ�܂ł́A�������ڎw���l�Ɠ����悤�Ȃ��̂��g�������̂ł͂Ȃ����낤���B���ꂩ��X�L�[���n�߂悤�Ƃ���l�́A�X�L�[�V���b�v�ɍs���\�Z�������đI��ł��炦�������낤�B�u�ȒP�ɉ���X�L�[�A���̒ɂ��Ȃ��u�[�c�v�ƌ������炢�̒����ŁA�\���ɗǂ����̂�������B
�����������A���ŃX�L�[�����Ǝv���A�X�L�[�V���b�v�ŃX�L�[�����Ă�����A�X�������āu���̃X�L�[�̓^�[���̌㔼���ǂ��́A�g�b�v���ǂ��́v�Ƃ������������Ă��ꂽ�B���͓��S�u���Ȃ��͂���Ȏ�������قǃX�L�[�����Ȃ́H�v�Ǝv���A�������̂��ʓ|�Ȃ̂ŋA���Ă����B
�X�L�[�̔����ȈႢ�ȂǏ�肭�Ȃ�Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��A�f�U�C���◬�s�őI�ׂΏ\�����Ǝv���B��肭�Ȃ��ĉ���悤�ɂȂ�����A�����̂ق������̂�������܂ŒT�������B
�E�F�A�͂������A���Ȃ��̂��C�ɓ���Ŕ��������Ȃ����낤�B�����牽�܂ő����Ȃ��Ă��A���ɒ�����͕̂��i���Ă��镨�̒�����A�����₷�����̂�I�ׂΏ\�����B�n�߂ăX�L�[������l�́A�]��N��������J��Ԃ�����A�C�����Ⴍ�Ă����\����~���̂ŁA�����z���₷�����̂̂ق����悢�Ǝv���B
�@���̂��Ƃ��u�Y�������v�ƌĂ�ł������J��搶�́A�����T�O���Ă������A��X���X�L�[�p���c�̉��ɗ����^�C�c�̑���ɁA������̃p���X�g�𒅗p���Ă����B���͒��J��搶���V�����X�L�[�A���̈̂��l�Ȃ̂ŁA�����ǂl�ɕςȖڂŌ�����ƍ���̂���A���������̘b���ɂ��Ă����Ăق����B�F���ŃX�l�т������Ƒ�ϋC�����������{�l�́u�g�����āA�����₷���v�ƌ����Ă�������A���p���Ă݂�̂��ǂ���������Ȃ��B
�����̎��̓p�g���[���ƌ�����������A�X�R�b�v��������̒�������������������B���������āA�C�̒����ʂ�Ă��܂�����A�ʂ�Ȃ��C�ł���ō��������B�Z���̌C����N�ڂɓ������N�A�x�����ꂽ�X�L�[�̋�����A�Z���̌C�ɍ��킹�ĕt���Ă��܂�����A���Ɏ���鎖���@�m�����Z���́A�u�m�A��邩�獡�N��N�҂��Ă���v�ƌ����Ă������A���X�ɕt���_���V�[�Y�����Ύ��̂��̂ƂȂ����B
���̑傫���͎����Q�U�����A�Z�����Q�T�C�T�������������A�Q�V�[�Y���͂������̂�����C���i�[�������Ė��͂Ȃ������B���̌C���C�ɓ��������́A���̌�S�N���������A���v�U�N�Ƃ��Ȃ�Ƃ�͂�w�^�b�e���܂����B�����g���l�łȂ���A���N���\���Ɏg������̂����A�����ɂ��̂̓X�L�[�����C�܂łȂ����Ă��܂����˂Ȃ��̂ŁA�C�͂�������ƑI�Ԏ���i�߂�B
��������ɗ]�T������A���N�V�������̂��g�������̂��l��ƌ������̂����A�ǂ�Ȃɂ�����������g���Ă��A�����̋Z�p�⊴�o���Ⴏ��ΐ��\���甭�����Ă���Ȃ����낤�B��肭�Ȃ��ĉ���悤�ɂȂ�܂ł́A�X�L�[���t���肢�l�̘b���āA�Q�l�ɂ���Ƃ悢���낤�B
�ٓ��G�Z�c
�ǂ��̃X�L�[�w�Z�ł��������Ǝv�����A���낢��Ȏ�����K����B�X�L�[�G���ȂǂŏЉ��Ă�����̂�����̂ŁA�F��������낢��Ȏ�����K����Ǝv���B�������A������x�A��肢�l�B���W�܂�ƁA���ƊȒP�ɏo���Ă��܂��Ėʔ����Ȃ��B���K���@�̏��ł����������A�G�X�J���[�g���čs���̂��B
�Ƃɂ����A���낢��Ȏ����l���o���A�s�����s������тȂ�����Ȃ�Ď��͊F������o�������邩������Ȃ��B��X����������ƁA���n���鎞�ɕ��s�A�͂̎��A�t�͂̎��ƂȂ�B(�}�P�j
|
|
�@
�}�P
|
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�Ƃɂ����A�N�����]�т����Ȏ����l���o���̂������B�F������������Ǝv�����A�ڂ̑O�Ŏw�����⏀�w�������]�ׂA�ʔ����Ă��܂�Ȃ��B�ȒP�����Ɏv���Ă��A�Ȃ��Ȃ�������͂��낢�날��B
�@���ɁA�X�L�[�̑O���J���Ē����~����̂�����B
|
|
�i�}�Q�j������A�Ȃ��Ȃ��^�������ɂ͊���Ȃ��B
�����͐^�����������Ă������ł��N�����Ɖ���Ă��܂��B
�@�v����ɁA�X�L�[�ɗ͂��`���Ȃ��̂��B���������āA�X�L�[�ɖ������͂�`������K�ɂ͍ō����B
|
|
�@�X�L�[���A�����Ȃ�G�b�W���O���銴�o��̂Ɋo�������邽�߂ɁA�ɒ[�ɕ\��������ǂ��Ȃ邩�B�i�}�B�j�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�}�B
�@�Ί��~���獶�̃X�L�[�̃g�b�v�̈ʒu���O�ɉE�̃u�[�c���o�čs���B�Ƃɂ��������ɂ������āA���̎��̊��o���A
��x�ł�������̂Ɋ��������Ă��܂��悤�ɂ����B���̂悤�Ȏ����Z����擪�ɍl���o���čs���̂��B�������A�̂̎g�������o����̂ɂ́A�m���ȗ��K���@�ƌ����邾�낤�A�F������A����̐l������o�J�Ǝv����������Ȃ����A����Ă݂�Ƃ悢���낤�B
�@�O���ɉd���邽�߂̗��K�Ƃ��ĎΊ��~���Ȃ���A�����������グ�鎖�͗ǂ����K����Ǝv���B�������X�����ƁA���낷���ɕ��s�A�͂̎��A�t�͂̎��Ƃ����悤�ɂȂ�B����Ƀ^�[�����Ȃ���A�����������A���̎��͓����Ń^�[�����Ȃ���O���ł�������B
�@���̂悤�Ȏ����`����ɖڂ��s���ƁA�X�L�[�̌`��ς��鎖����l����肭�s���Ȃ��A�����Ȃ����������Ȃ�������Ȃ����A�ǂ��l���鎖���K�v���B�����̌`��ς���Ƃ���������ɖڂ������Ă��܂����������A�{���̂Ƃ���O���ɂ�������d���鎖�̗��K�Ȃ̂��B�O���ɏ�鎖��̂��Č������Ԃ������A���Ƃ����₷���o���Ă��܂��̂��B���x�������Ă����悤�ɁA��������̎�����x�ɂ�낤�Ƃ��Ă���肭�s���Ȃ��B��ԏ��߂ɂ��Ȃ�������Ȃ������A��������ƃC���[�W����悤�ɂ��Ăق����B���̂悤�Ȏ������鎞�A���̏ꍇ�Ȃ�ŏ��ɍl����̂͊O����{�ɏ��A�������Ȃ鎖���l���Ċ���n�߂�킯���B�������g�̊��o������A���Ȃ��͊���n�߂鎞�ɁA�����l����̂��낤���B
�@���̂悤�ȗ��K�ɂ̓X�s�[�h��Γx�����E������A��肭�Ȃ�}�Ζʂł��A�����X�s�[�h�ł��o���Ă��܂���������Ȃ�����ǁA�����܂ŋ��߂鎖�͂Ȃ��B�ɎΖʂł��w�����⏀�w�������]�肷�邩��ʔ����̂��B���i�A���q�����k����̑O�ł́A��ɓ]�Ȃ��Ƃ����ْ����������Ă���l�B������A�ȒP�����Ɍ����ē]�肷��ƊF�A��Ă��܂��B�u�N�\�[���ŏo���Ȃ���ȂǂƑ吺���o���ĉ��x�����킷�邩��y�����̂��B�X�L�[�͊y�����Ȃ�������Ȃ��A�F������y���݂Ȃ�����K�����Ăق����B
�@�@�@�@�X�L�[���ʔ������ǃ{�[�h���ʔ���
���́A�����P�Q�N�R���w�������C��Ŏ��Ƒ����͑�������B�����炭�A�X�L�[���n�߂Ă��獡�܂łň�ԏ����̂ł͂Ȃ����낤���B���̎��́A���̒m�l���X�m�[�{�[�h������̂ŁA��ォ��ΑŊێR�X�L�[��܂ňꏏ�ɘA��Ă����A��X�����C��̊ԁA�ނ̓{�[�h�����Ă����B�����{�[�h�����Ă݂悤�Ǝv���A���Ԃ̂��ЂƂ�Ă������̂����A���_�I�ɍl���Ă��u�{�[�h�ɂ��T�C�h�J�[�u������A�^���ɏ���ď������Ȃ�����̂�����ȒP����Ȃǂƌ����Ȃ���A�[�H�Ńr�[���Ȃǂ����݂Ȃ���b���Ă����B
�����֖߂�A���炭���Ď����u�{�[�h���Ă���v�ƌ����Ƒ������s�����ƂɂȂ����B�R�U�̎w�����ƂS�Q�̏��w�����A�X�L�[���͂P�U�N�ƂQ�Q�N�̃x�e�����ƌ������ɂȂ�B
�@�{�[�h�����A�D�u�Ɗ���n�߂�B�T�C�h�J�[�u���������āA�J�[�r���O�̘A���B�X���[�Y�ȑ̏d�ړ���S�����āE�E�E�Ǝv������A�Ȃ�Ɨ��ĂȂ��ł͂Ȃ����B�����������Ă��Q�����œ]�ԁA���݂��ɑ���̎p������Ə��Ă��܂��ė���������Ȃ��B�������܂܂ŁA�������܂������A�ǂ���Ƃ��Ȃ����������芊��n�߂�B
��ɓ]�ق����������B���Ă��܂��Ċ���ǂ���ł͂Ȃ��A�Ƃɂ������Ă��܂��Ċ���Ȃ������B���ǁA�Ȃ��鎖�͏o���Ȃ���������ǁA�R�O�����͗������܂܂Ŋ����čs����悤�ɂȂ������낤���A�ƂĂ��ɂ������̂́A�����܂ł��Ȃ����낤�B
���ƃ{�[�h�͖ʔ����̂��낤�A����قǏ����̂͋v���Ԃ肾�����B�������ЂƂ��������Ă����Ȃ�������Ȃ��B����قǎS�߂Ȏv���������̂́A���߂Ē̒r�ɍs�������ȗ����B
���̍��X�L�[�ɋ������悤�ɁA���{�[�h�ɋ������ƌ����A����Ȏ��͂��蓾�Ȃ��B�o����{�[�h�X�N�[���ɓ����āA�Ⴂ�������t�ɋ����Ă�����ăj�^�j�^���Ă���悤�ȁA���N�{�[�_�[�ɂȂ肽�����̂��B
�����A�����̊��o���ǂ��̂����̂Ǝn�܂��Ă��܂�Ȃ��悤�ɒ��ӂ������B�������N���o���āA�ǂ����̃X�L�[��Őe�q�A����������āA��������̓X�L�[����肢�̂����{�[�h�𗚂����r�[�A�q���Ɏ��������]��ł��肢��l��������A����������Ȃ��B
�ʂ����Ď��̎q���B�́A�X�L�[������̂��{�[�h������̂����ɂ͂킩��Ȃ����A�ǂ�����y�������ɈႢ�͂Ȃ��B�ޓ����傫���Ȃ��āA�����Ă݂����ƌ����o������A���ő���o���Ă��������B
�@�@�@�@�X�����v�͂ǂ̂悤�ɍ�������H
�@�����܂Ŏ����w�����ɍ��i����܂ł̂T�V�[�Y�����������Ă������������A�y����ł��炦�����낤���B���ꂩ��X�L�[�̏�B��ڎw���l�Ɂu����Ȓj�������B���������ė��K����P��������A�w�����ɂȂ��v�Ƃ������M�������Ă���������Αf���炵�������Ǝv���B
�@���Ȃ������ď��߂ăX�L�[�𗚂����N�ɁA�P��������̂��B�����A�����Ȃ�Ƃ������͋]���ɂ��Ȃ�������Ȃ���������Ȃ��B�x�݂̑����w���Ȃ�܂������A�Љ�l�ɂƂ��ăV�[�Y���ɂR�O�����T�O�������鎖�́A����ƌ��������Ȃ����A�X�L�[�ꂪ�߂������i�C�^�[�ɍs����l�Ȃ�A��ɏo����B�����łȂ��l�̓X�L�[�w�Z��L���ɗ��p���鎖���l���悤�B
�������A��O��ƂȂ鎖���ЂƂ�������E�E�E�E�X�L�[�������Ă��鎖�B�����g�������������悤�Ɂu�����͊��肽���Ȃ��v�ƌ��������K������A������������邽�߂ɕK�v�Ȃ̂��A�X�L�[�������Ă��鎖���B��y�B�������������悤�ɁA���ɂ͉������X�L�[�������Ȃ��Ă͂����Ȃ��������āA���邩������Ȃ��B
���̏ꍇ�A������w�����ɍ��i���邭�炢�܂ł́A���鎖���y�����Ďd���Ȃ������B�Ⴊ�~��Ȃ������W�����Ǝv�����A����Y�݂������Ȃ��āA��肭�Ȃ�X�s�[�h�͊m���ɒx���Ȃ�B�͂̎��Ŋ���l�̃X�L�[�������A���肵���o���Ȃ��l������������悤�ɂȂ�B�R���ɍ��i�����l���A�Q����ڎw�����i����B�O�������B���킩�邵�A�����ł������ł��邩��A�y�����Ďd���Ȃ����낤�B
�������A���Ȃ������ꂩ�瓥�݂������Ƃ��鐢�E�͊ԈႢ�Ȃ��A���Ȃ��̂����Ɗ��o�I�ȕ��������߂Ă���B�X�L�[�w�Z�ŏ��S�҂������Ă���ƁA�ǂ�ǂ��肭�Ȃ邩��A�X�L�[���t�����ɐs����B�������A��肭�Ȃ�ɂꗝ������̂ɂ����Ԃ�v���A���ۂɊ��o�Ƃ��Ă��݁A���ł��Č����Ă����Ȃǂƌ����A�r�����Ȃ���ƂɎv���Ă���B
��X�X�L�[���t���������������A�������čČ����邠�Ȃ��ɂƂ��ẮA�����Ƒ�ςȍ�ƂɈႢ�Ȃ��B�������A��肭�Ȃ�Ȃ�قǁA���̈�ɋ߂Â��ė���ɈႢ�Ȃ��̂��B
����ȂƂ��A���Ȃ��͂ǂ�����H�@���x�������Ă������A�X�L�[���y�����Ǝv���邱�Ƃ����悤�B���̏ꍇ�͒��ԒB�ƃo�J�Ȃ��Ƃ��ł��邤���ɁA����ɏ�B�����悤�ȋC������B����ł��X�����v�Ɋׂ鎖�͕K������A����ȂƂ��͎����Ɍ����������邵���Ȃ������B�����͉���Ȃ̂�����A�l���ꕪ�ł��������K���鎖���B
������K������ǂ����H�ǂ����Ηǂ����H�����킩��Ȃ����ɗ��K����̂͒N�����Č����B�^����ꂽ�ۑ�����Ȃ����g�̊��o�Ƃ��āA�������鎖����Ȃ̂����A���ꂾ���āA���̓��������ʼnۑ�������o���A������T���Ȃ�������Ȃ��Ȃ�A���̉ۑ���������Ȃ������K������̂��B
�X�L�[���t��ڎw������ɂ́A����ȓ������K���Ȃ�������Ȃ��Ǝv���Ă������A���ɂȂ��Ďv���Β����V�[�Y���̐����̎��A�Y�ޕK�v���Ȃ��B
�F����ɂ͓��ɂ��̎���`�������A��ԑ�Ȏ��̓X�L�[���y���ނ��ƁI
���̋C�������Ȃ���A����������B����ɂ��A�]�v�Ȏ��Ԃ��������Ă��܂��B�X�����v�����������ɂ́A���Ԃƃo�J�Ȏ������悤�A���K�̎��͖Y��āA�����r�[���ł�����Ŋ��������Ă����ł͂Ȃ����B
�@�@�@�@�w�����̏h���H
�@�Ⴂ�l���A�j�����l�ŃX�L�[�ɍs�����C���C����̂�����ƁA�{���Ɋy�������Ɍ�����B�l���ꂼ�ꉿ�l�ς��Ⴄ�A�X�L�[�ɋ��߂���̂��Ⴄ�Ǝv���B�������A�y����������ł͂Ȃ����A�ǂ�قǏ�B���Ă������͂Ȃ��B�꒼���ɏ�B��������߂āA�Y��ł��܂�����ł͂܂�Ȃ��B���֖߂�A���x���m�荇���ɗU���ăX�L�[�ɍs������������A���C���C�ƎԂɏ��A�ʃr�[��������ŁB�^�]����l�ɂ͋]���ɂȂ��Ă��炢�A�X�L�[��̒��ԏ�ňꖰ�肷��A���ꂪ���y�����B
�ڂ��o�܂�����ɍs���A���t�g����~�肽�����A�K���ƌ����Ă����قNJF�A���̑O�ɕ���ł��܂��B
�@�m���ɊF�ŃX�L�[�ɍs���Ίy��������ǁA���̐l�B�́A�����Ⴄ�������߂Ă���悤���B����������b���n�߂�܂ŁA���܂ł��^���Ȋ�ő҂�������B���܂��܈ꏏ�ɃX�L�[�ɍs���̂����A���Ɏw����������Ɗy�����X�L�[���A��B���鎖�����߂�̂��B�F����̃X�L�[�͂ǂ����낤�H�@
�@�吨�ŃX�L�[�ɍs���A�O�̐l�̍��ɂ��܂�A�Ȃ��Ċ���B��������Ă݂��������B�m���ɂQ���A�P���Ɛi�ފԁA����̐l�B�̂������Ŋy�����X�L�[���o����ꂽ���ɊԈႢ�͂Ȃ��B�������A���̎q�ƃX�L�[�ɍs���������Ȃ����u���v�H�v�Ȃǂƕ����N�����������Ȃ��B���A�w������P����ڎw���Ă���l�́A����ȃX�L�[���y����łق����Ǝv���B�������̃X�L�[�A���������̃X�L�[�A�y�����X�L�[�A�܂�Ȃ��X�L�[�A�������X�L�[�A�����S�Ă𖡂���Ăق����B�X�L�[�͊y�����̂��A�y�����Ȃ���X�L�[�ł͂Ȃ��I
�@�@�@�@�N����肢�̂��H
�@������ɏ�肢�Ƃ����̂��낤�H�@�P���������Ă��邩���肢�̂��A�w������N���E���v���C�Y�ɍ��i���������肢�̂��B�f�����X�g���[�^�[����肢�̂��A���[���h�J�b�v�ŗD�������I�肪��肢�̂��H�@�S�ĊԈႢ�ł͂Ȃ��B���[���h�J�b�v�ŗD�������l�͐��E�ň�ԏ�肢�B
�@�ǂ̂悤�ȎΖʂł��]���ɑ�������~�肽�l����肢�ƁA���͎v���Ă���B�F����͂ǂ��v���Ă���̂��낤�H���R�P���������Ă���l�͏�肢�A�����e�N�j�J����N���E���A�w�����Ȃǂ����l�̂ق�����肢�Ǝv���̂�������O��������Ȃ��B�������A���[���h�J�b�v�̑I��B�́A�P���͂��납�Q�������Ď����Ă��Ȃ��A�Ȃ�Ή���Ȃ̂��A�ƌ����ΈႤ�̂��B�w�����̒��ł��g�b�v�N���X�̗͂����f�����X�g���[�^�[�����A�����Ə�肢�̂ł���B����Ȃ��Ƃ͊F������킩���Ă��邩��A�{���Ă��܂���������Ȃ����A�������������������Ƃ����A�o�b�W�e�X�g���i��ڎw���l�B���ׂ�₷�����Ƃ����̎����B
���܂�ɂ��P���̃p�������^�[���ɁA���Ȃ��̖ڂ��D���Ă��܂����Ƃ��|���̂��B��ڂƌ������̂ɂ�����邠�܂�A�����ł����Ԃ���茟��p�̊��������K���悤�Ƃ��鎖���|���̂��B
�m���Ɍ���p�̊����ςݏd�˂鎖�ɂ���č��i�ł���B�������A�Ζʂ͂��������ł͂Ȃ����A���Ȃ��̑̒������ĕω�����B�����āA�����ڂ����ĕς���čs���̂��B��ڂ���ɖڂ������ė��K���鎖�ɂ���āA�m���Ɂu�J�����������v�͏o����悤�ɂȂ�B�����A�����Ƃ���ȁu�X�L�[�ɗ͂̓`���ꏊ�ɏ��v�ƌ���������ɂȂ��Ă��܂�Ȃ����낤���H�@���ꂳ���}�X�^�[����A���Ȃ������������悤�Ƃ������ɃX�L�[���v���ʂ�ɓ����̂��B��̓X�L�[���t�̐������������g�Ŋ����āA�Č����邾���ł����B
�O�ɏ��������A�k�䍂�x�̖k�ǂ����͑S������Ȃ������B���w�����̎����B���������č��i���ď�肭�Ȃ��Ă��邱�Ƃ͎������Ă����B�������A����Ȃ����ƂŁA����������ł��鎖��m�鎖�ɂȂ�B���i�̗��K�ł����o�I�ɁA�����Ə�肭�Ȃ邽�߂̗v�f�͉����Ă��ēw�͂�����B�������A�����̗͂̋y�Ȃ��悤�ȎΖʂł́A�ׂ������Ƃ��l���Ȃ��犊��͕̂s�\���B
�Ƃɂ����̂��o���������Č����čs�������Ő���t�Ȃ͂����B���ōl����Ƃ�����A�u�|����Ȃ��v�����炢���낤�A����l���鎖�͂Ȃ��A�P���Ɋ���Ȃ����牺��Ȃ̂��B
�@���肾���ē������A���ْ̋����̒��A���Ȃ��ɏo���鎖�́u����������Ɩ��߂��鎖�������B��͑̂��Č����Ă����B���̎��A����p�ɗ��K�����Ζʂƒ�������������Ă�����A�ǂ��Ȃ�̂��낤�B�w������ڕW�Ƃ��ė��K���鎄���A��ԑ�ɍl���Ă����̂́A�������R�Ə�肭�Ȃ鎖�������B�ǂ��ł��]���ɏ����ł���������~��鎖�������B
�^�����A�k�ǂ�����Ȃ������N�ŁA�s���ɂ��ގЂ��Ă��܂����B���������āA���̎�����肭�Ȃ������ǂ����킩��Ȃ��B�������A���s���A�m���ɖ��𗎂Ƃ��̂ł͂Ȃ����낤���B���̍����̗͂������Ă��邵�A�������Ԃ��ׂ�ڂ��ɏ��Ȃ��Ȃ��Ă���B
���̎����肾�������́A�m���ɂ��̎���艺��ɂȂ��Ă��鎖�͊ԈႢ�Ȃ��B�����āA�Ⴓ�Ɩ`���S�ɔC����т���ł��Ȃ�������A����������Ȏ�����킩��Ȃ�������������Ȃ��B
�@�����������̃X�L�[������ƌ����̂ł͂Ȃ��A���낢��ȎΖʂ�����悤�ɂ��邾���ł����̂��B�������A���ꂷ�炵�Ȃ���Ύ����́u�X�e�b�s���O�����肾�v�Ƃ��u�X�L�f�B���O����肭�s���Ȃ��v�Ȃǂƌ����āA�X�L�[�̖{����m��O�ɏI����Ă��܂��̂ł͂Ȃ����낤���B���̂�������ǂ��������邩�͊F����̎��R������ǁA���́u����ꕔ�����o���Ȃ����牺�肾�v�Ƃ͍l�������͂Ȃ��B
�@�ȑO�]��ł��肢���Ζʂɍs���u������]���Ɋ��ꂽ��A��肭�Ȃ��Ă���v�Ǝv���Ă����B���̂ق��������I�ʼn���₷���Ȃ����낤���B
�F����̏�B���v�镨����������Ƃ���A����͂܂������A���Ȃ��̖ڂ̑O�̎ΖʂȂ̂��B�����āA���Ȃ��ɂ��������鎖�̏o���Ȃ��X�L�[�̓����Ȃ̂�����A�Ƃɂ����ȒP�ɍl���Ăق����B
�����ɂ��b����ƁA������x��肭�Ȃ��Ă���(�ȒP�ɂP���̍��Ƃ��Ă����j�X�L�[������錴���ȂǕ��͂ł��Ȃ������B��ɃX�L�[�ɗ͂̓`���ꏊ�ɏ�낤�Ƃ��Ă�������ǁA��N��A��N��Ƃ͑S���Ⴄ���o�������B�����g�[�^���ōl���A��葬�����肵�Ċ����Ζ������Ă����B
���Ȃ����g����Ɉ����́A�V�������o�����ߑ����鎖����Ȃ̂��B
�X�L�[���t�ɂȂ邽�߂ɗ��K�����āA�������Ă��A����Ȃ����͂�������B�X�L�[�͉����[���A�����炱���A���낢��Ȑl���y���߂�̂��B
����ł������Č��킹�Ă��炢�����B�ǂ�Ȃɏo���Ȃ����������Ă��A����Ȃ��������������Ă��A�X�L�[�͊ȒP�Ŋy�������̂Ȃ̂��B�����Ă������낤�A�����]���Ɋ���~�����悤�ɂȂ�����̂�����E�E�E�B
���Ȃ�������l���邩�����Ȃ�̂��B���܂łR��]������]��ł����l���S��]�ł�����E�E�E�m���ɑO����肢�ƌ�����B
�@�@�@�@���o�ƌ������t�̈Ӗ�
�@���x�����o�Ə����Ă�������A���o�ƌ�������������Ƌ��۔������N�����Ă��܂���������Ȃ��B�Ⴆ�u�L���[���v�ƕ\��������u�|�[���ƊJ���ăq���C�ƕ���v�ƕ\�������肵���B�ǂ̂悤�ɗ�����������̂��낤�A�^���ɓǂݐi�߂Ă������������Ȃ�A�������\�y�[�W���O�ɗ������Ă��܂�����������Ȃ��E�E�E�����ȒP�ɁA�Ƃɂ����ȒP�ɍl���Ăق����B
�@�ǂ�Ŏ��̔@���E�E�E���Ȃ����g�Ŋ����Ċo���čs���̂��B��B��ڎw���A���ȏ���Q�l����ǂ�A�X�L�[�w�Z�ɓ�������ƁA�F����̓w�͂������̎��łȂ������炢�A�X�L�[���t�̎��ɂ͗ǂ��킩��B�������A�����Ă��鎖��A�X�L�[���t�̌������Ƃ��o���悤�Ƃ��Ă��@�u���o�̊��v�@�܂�A���Ȃ��������镔�����Ȃ���Ίo���鎖�ȂǏo����킯���Ȃ��B
�@�K�����̏ꍇ�A��ϑ����i�K�ł��̎��ɋC�������B��y�B���F�A�����o�������̂Ɠ��������o�����āA��肭�Ȃ������ɕς��͂Ȃ��̂����A�q���̍�����X�L�[�����Ă��āA�u�C�Â������ɂ͏o���Ă�����ƌ����̂��������낤�B
�q���B�́A����Ȃɓ����g��Ȃ��Ă��A���낢��ȏ���������Ɏ����̕��ɂ��Ă��܂��̂��B���̏ꍇ20�Ƃ����N��Ŏn�߂�����A�N���Ɋo���Ă��邾���̘b�����B���̋C�������̂��A���x���Z���́u�����ƋȂ��Ă݂�v�ƌ����A�Z��������̂����Đ^������̂����u�Ȃ����ĂȂ��v�ƌ�����B�����͋Ȃ��Ă������ł��A�������������Ă��܂��B
���̂������ɗ��āA�u�Ȃ��Ă邶��Ȃ����A�R�m�����[�B����łǂ����I�ǂ����Ă�A�Z�������ċȂ����ĂȂ�����Ȃ����v�ƐS�̒��ŋ��тȂ��犊�������ł���A�u����ł�����v�ƌ���ꂽ�̂������B���̎��A���Ƃ������Ȃ��������������B�_�߂�ꂽ���������������̂ł͂Ȃ��A�₯�����ŁA�Ƃ�ł��Ȃ���X�ɂȂ�����Ԃ���A�w�L�т��邭�炢(���ۂ͂���قǂł͂Ȃ��Ǝv���j�܂ŁA�̂��������ɁA���܂Ŋ��������̂Ȃ��������X�L�[�������̂������B
���̎����͉����V�������̂��������̂��B���̓�����R���قǓ����������āA�̂��o�����A���ꂪ���̊��o���B���̎��͒��߂��A���̂��炢�Ȃ���ƁA�X�L�[�͂��̂悤�ɓ����Ƃ�����������ōs���̂��B
���ꂪ�A�u���Ȃ��̊��o�Ƃ��Ă��ށv�Ƃ������ɑ��Ȃ�Ȃ��B�����āA�Ȃ��鎖���ӎ����Ȃ��Ȃ������ɂȂ�ƁA�����͋Ȃ��悤�Ƃ��Ă��Ȃ����A�����l�����Ɋ����Ă���̂ɁA�����Z���́u�Ȃ��룂Ƃ͌��킸�ɁA���������čs���ƁA�ق��Ă��Ȃ����̂������B
�@����Ȏ����A��ϑ����i�K�ŋC�Â����Ə������A����ł��ŏ��̃V�[�Y���ł͂Ȃ��A�Q�N�ڂ̌㔼�������Ǝv���B���V�[�Y�����w���������邭�炢������A��肢�P���ɂȂ��Ă��炾�B
�@�����炱���F����ɂ́A�����ɂ��ē`�������̂��B�����g�͂Q�N�ł��̎��ɋC�Â����̂����A��ϑ����i�K�ŋC�Â����Ǝv���Ă���B���̌������Ƃ��A�M����M���Ȃ��͊F����̎��R�����A�M���悤�Ǝv���l�́A���������̎��ɋC�Â����Ƃ��o����B���߂ăX�L�[�����悤�Ǝv���l�����̌������Ƃ�M���Ă����Ȃ�A�F�l�B�������悤�ȃX�s�[�h�ŏ�B���čs�����ɊԈႢ�Ȃ��B
�@���Ɂu��l�Ŋ��鎞�͖Y��ĂȂ��H�v�ƌ������o�����v���o���Ăق����B���Ȃ��̓X�L�[�w�Z�ɓ���A�ǂ��X�L�[���t�ɋ����Ă��炤�@��Ɍb�܂ꂽ�B���̋��t�����Ȃ��ɉ��������������Ă��ꂽ�Ƃ��悤�A���b�X�����I���A���Ȃ��͓����P�����Ȃ�����U����B���H���I���A�������������C���Ōߌ�̃Q�����f�������A�V�C���ǂ��Ꮏ�������A����n�߂悤�Ƃ������̎��A�������������Y��Ă��܂��Ă��Ȃ����낤���H�@
�@�������������鎖���o�����̂ɁA�o���鎞�Ԃ����Ȃ�������E�E�E���Ȃ��̊���͌��ʂ肾�B�����Ċo���鎞�Ԃ���鎖���Ȃ��������A�Q���R���̃X�L�[���I���B�ꃖ����A�ĂуX�L�[�ɏo���������Ȃ��ɁA���̓������������́A�����c���Ă��Ȃ��̂��B���������Ă܂��A���ʂ�̊�������鎖�ɂȂ�A���̓��X�L�[�w�Z�ɓ��邽�߂ɕ������Q�O�O�O�~�́A�����������Ȃ̂��낤���B
�@���U���鎞�ɋP���Ă����A���Ȃ��̓��͍��ł��P���Ă���̂��낤���A�u��肭�Ȃ肽���v�ƔY�݁A�P�����Ȃ��������Ȃ��̓��́A�ĂуX�L�[�w�Z�Ɍ�������B�����Đg������ē����ē������̒�����A�Q�O�O�O�~���o���̂��B�����A���̓��̃X�L�[���t���A���Ȃ��ɉ������������Ă���Ȃ�������E�E�E�����l���������Ń]�b�Ƃ���B���������Ă����A�܂��~����A�������A���Ȃ��͖����������J��Ԃ��̂ł͂Ȃ����낤���B
���肢������A�X�L�[���t�����Ȃ��Ɋ��������Ă��ꂽ����Y��Ȃ��łق����B�Y��Ȃ������ɁA���Ȃ��̑̂Ɋo�������Ăق����A�Y���̂́A���Ȃ����ӎ����Ȃ��Ă��A�̂��Č����Ă����悤�ɂȂ��Ă��炾�B
���x���������悤�ɁA�����鎖�����o����Ίo����̂ɁA����قǒ������Ԃ͕K�v�Ƃ��Ȃ��B
�@�@�@�@��B�ׂ̈ɂ������Ȃ��̐S�̋��ɒu���Ăق�����
�@�Ō�ɁA���̐悠�Ȃ����A�傫�ȕǂɂԂ����ď�B���������Ȃ����������Ă��A�K�������ł���R�c�������Ă��������B������͉����Ȃ��A�����y�������K���鎖���l���Ă�������A�u�X�L�[�ɗ͂̓`���ꏊ�v�����T�������Ăق����B�����ɏ���Ă�����Ȃ��̎v���ʂ�ɂȂ�A�v���ʂ�ɂȂ�Ίy�����ł͂Ȃ����I
�@�S����A���Ȃ��̏�B������Ă���B�����Ď������ȏ�ɏ�B�������B
�@�@�@�P�@�@�ЂƂЂƂ}�X�^�[���悤
�@�@�@�Q�@�@���Ȃ�������l���邩�����Ȃ�
�@�@�@�R�@�@�J�b�R�Ȃǂ��ł�����
�@�@�@�S�@�@���낢��ȎΖʂ����낤
�@�@�@�T�@�@�ǂ�ȎΖʂł��]���Ɋ����ō�
�@�@�@�U�@�@���Ȃ��̊��o����ԑ��
�@�@�@�V�@�@�X�L�[�Ɏ����̎v����`���悤
�@�@�@�W�@�@�킩��Ȃ����̓X�L�[���t�ɕ�����
�@�@�@�X�@�@�����̌��E�X�s�[�h�����߂悤
�@�@�@�P�O�@�y�����Ȃ���X�L�[�ł͂Ȃ�
�@�ȏオ�Q�O�ŃX�L�[���o���ĂT�N��A�w�����ɍ��i����܂łɎ������������ł���B�m���ɓ�����������������A�������A���鎖�̊y�������������S�đł������Ă��ꂽ���獎���ł����Ǝv���B����Ɠ����ɃX�L�[��P���ɗ������Ă��钇�ԒB�ƈꏏ�ɗ��K�ł�����A�V�肵�����炾�낤�A���Ȃ��ɂ��K���o����A�����V�Ԃ悤�ɗ��K���悤�B
�@�Ō�ɁA��������Ȃ��������ɁA�O���邱�ƂȂ��X�L�[��`�����Ă��ꂽ�t���B�Ɋ��ӂ���Ƌ��ɁA�����Ƃ����т������Ȃ��w�������X�L�[�Z�p��S�\���ɂ��ď��������Ƃ��������肢�Ȃ���A�F����̑f���炵���X�L�[���C�t���������ĕM��u�����ɂ���B�܂������c�t�ȕ��͂ł͂��������A�Ō�܂œǂݐi�߂Ē��������Ɋ��ӂ������B